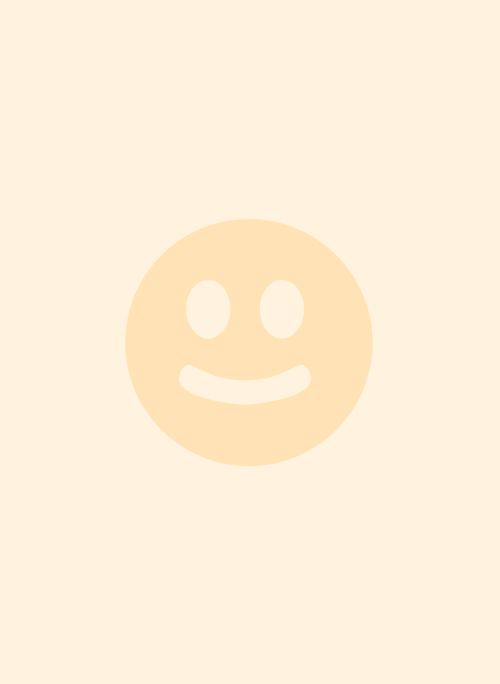高校教師「高校教師と女子高生の恋愛小説です」
高校教師「高校教師と女子高生の恋愛小説です」
高校教師
設定 Situasion
東京郊外のある私立の女子高校で、
一学期の半ば頃、英語担当の女教師が結婚して、他県の高校へ、転任することになったので、今春大学をでて、ある男子校で教鞭をとっていた山武に、彼女から後任のたのみがもちかけられました。彼は彼女と同じ大学で、クラブの後輩でした。山武はこれをひきうけました。山武は女子高の近くのアパートに引っ越して、さっそく女子高で教鞭をとることになりました。山武は英語の担当の他に、二年B組の担当もすることになりました。山武は内気な性格でしたが、熱心なため、生徒達の評判もよかったのですが、でも担任の二年B組の一生徒、根木玲子はなぜか山武が自分にだけはよそよそしい態度のように感じられてなりませんでした。一学期が無事終わり、夏休みも過ぎ、二学期も半ばにさしかかったある秋の日のこと…・。
三日つづけて山武が学校を休んだ日の昼休み、玲子はそのわけを教員室にたずねにいった。すると何でも山武はどこかの男子校に転任するらしいとのことだった。
その日の放課後、玲子は山武のアパートをたずねた。
玲子は山武が自分をさけているような気がしてならなかったのだ。その疑問がわからないまま山武が転任してしまうのはなんともあとくされが悪い。さらに玲子はなんだか山武が転任するのは自分のせいであるような気さえしていた。山武のアパートは学校の最寄の駅から二駅目で、駅から歩いて十分くらいの静かなところにある四階建てのワンルームマンションだった。
周りは一面大根畑だった。このあたりの土壌は、深くてやわらかい黒つちなので、大根、にんじん、ごぼうなどの根菜類に適していた。山武の先任の女教師もそこに住んでいた。以前、玲子は数人の友達と、その女教師のアパートをたずねたことがあったので、場所は知っていたのだ。
先任の女教師が転任して部屋をでるのと入れ替わるように、山武が同じ部屋に入居したのである。玲子は駅前の不二家でマロンケーキとモンブランを買っていった。途中、玲子は通行止めにあった。
小学校低学年くらいのい子供達が四、五人、道にしゃがみ込んで、チョークで絵を書いている。玲子はしゃがみこんで、馬の絵を書いた。
子供達は、
「うまーい。」
と言って拍手した。その中の一人の子は自分達の言ったことばが、しゃれになっていることに気がついて笑った。一人の子が、
「もっとかいて」
と催促した。が、玲子は立ち上がり、
「ちょっと用事があるから、また今度ね。」
と言って手を振って歩き出した。
それから数分もしないうちに山武の住んでいるアパートが見えてきた。
山武の部屋は3階だった。玲子が戸をノックすると鈍い返事がして、足音が聞こえ、戸が開いた。そして中から山武が眠そうな目をこすりながら、ものぐさな様子でぬっと顔を出した。
それをみて玲子はクスッと笑った。山武は予期しない訪問者にたいそう驚いた様子で、へどもどして、さかんに髪をかいて、「やあ。」と返事した、が当惑して
「すまないがちょっとまって。」
と言って戸を閉めた。中でどたばた音がする。5分位して戸はまた開いた。出てきた山武をみて玲子は再びクスッと笑った。山武は、いつも学校へ着てくるスーツを着ている。さすがにネクタイまではしていなかったが。
「よくきてくれたね。まあ、とにかく入って。」
山武は言った。玲子は山武の口調に、かすかに社交辞令ではない真意があるような気がしてうれしくなった。通された部屋は応急手当したあとらしく、多少きれいにかたづいていた。
「あんまりきれじゃなくてすまないけど…・。」
と言って山武は玲子に座布団を差し出した。それはぺしゃんこで生地が光っていた。
玲子はカバンを置いて、座って部屋をみまわした。
さすがに教師の部屋だけあって書物が多い。
まさに汗牛充棟である。山武は英文学が専攻だった。
心理学や哲学の本が多かった。
「先生。ケーキを買ってきました。」
といって玲子はそれを机の上に置いた。
「やあ。それはどうもありがとう。じゃ今、お茶を入れるよ。紅茶でいいかな。」
と山武が聞くと、玲子は「はい。いいです。」と答えた。
山武は台所にポットと紅茶ととティーポットと紅茶茶わんをとりに行った。
紅茶ちゃわんは一つしかなかったのいで、自分は湯のみにすることにした。
幸いポットはいっぱいだった。それをやかんにうつしてあたためなおしたが一分もかからずお湯はわいた。
キッチンからもどって山武は玲子と向かい合わせに座った。
「先生。モンブランとマロンケーキのどっちが好きですか。」
「君はどっちがいい。」
「私はどっちでもいいです。先生のために買ってきたんです。先生が好きなほうをとってください。」
「そう。じゃ、マロンケーキをもらうよ。」
山武はあっさり答えた。もし、モンブランがなかったら、レストランに入るとすくなくても3分はメニューとむきあう、優柔不断度の偏差値が少なくみても65はある山武に、この選択に最低でも一分は費やさせたであろう。山武があっさり答えられたのはモンブランがあったからである。アルコール分解酵素の少ない山武は以前モンブランを食べて、それに含まれている少量のブランデーで顔が赤くなって恥ずかしい思いをした経験があるからである。山武は紅茶を入れた。二人は紅茶が出るのを少しの時間、待った。
「あっ。そうそう。ケーキはいくらした?」
山武はあわてて財布をだした。
「いいです。私のおごりです。」
「いや、そういうわけにもいかないよ。僕が払うよ。」
「先生。」
玲子は少し強い口調で言った。
「人の好意は素直にうけるものですよ。ショートケーキ二つなんて五百円しかしません
。」
「…・わかったよ。ごめん。」
確かにそのとうりだと思って山武は財布を内ポケットに戻した。二人は食べ始めた。山武はなんだか、照れくさくて、うつむき加減に食べた。
玲子はそんな山武がちょっと面白くて、じっと山武をみつめながら食べた。普通こういう時、女同士だったらしゃべられずにはいられない。
だが山武は内気な性格なので、こんな時、何を話したらいいのかわからないのである。
(何か話さなくてはならない。でも何を話したらいいのかわからない。)と山武は困っている。
玲子はそんな山武の心を見ぬいている。
山武は玲子から目をそらすようにして紅茶を飲んだ。重苦しい沈黙を玲子がやぶった。
「先生。どうして転任なさるんですか?」
山武は、たいそう驚いた様子で、口の中に含んでいた紅茶をあわてて飲み込んだ。
「いや、それは、つまり、その…・。」
山武はさかんに髪をかきあげながら、あやふやな返事をした。山武が当惑して口篭もるのを玲子はじっとみつめていた。玲子は何かやさしいことばをかけようかと思った。が、やっぱりそれはやめた。山武の本心をききだすには、こうしてだまってじっとみているのがいちばんいい。玲子は眉を微動だにせず、じっと山武をみつめつづけた。数分その状態が続いた。物理的には短い時間だったっが、精神的には山武にとって長い時間だった。山武はとうとう沈黙に耐えられなくなって、観念して言った。
「僕個人のちょっとした事情のためさ。」
「事情って何です?」
玲子はすぐに聞き返した。
「だからそれはいえない事情だよ。」
山武は湯呑に茶をつぎたした。山武は少しほっとして眉をひらいた。玲子もそれ以上問い詰める気にはならなかった。
「わかりました。それならばもうそのことは聞きません。そのかわり…。」
と言って、玲子は声を少し強めた。
「そのかわり、一つ教えて下さい。」
「ああ、いいよ。」
山武は肩の荷がおりた安堵感でおちついた口調で言った。
「どうして私を無視するんですか?」
(うっ。)
山武は驚きで一瞬のどをつまらせた。
「無視なんかしてないよ。」
山武はあわてて否定した。
「ウソ。先生は授業の時もホームルームの時も一度だって私をみたことがないわ。先生はわざと私から目をそむけるようにしていたわ。」
「そんなことはないよ。もしそうみえたんだとしたらあやまるよ。…ごめん。」
「あやまってもらわくてもいいんです。どうして私を無視するのか、そのわけを教えてください。」
玲子の口調は真剣だった。
山武は大きなため息をついた後、目をつむり、額に手を当てて再び黙ってしまった。重苦しい沈黙が再び起こった。山武は額にしわを寄せ、唇をかんだ。その沈黙を玲子はおちついた口調で破った。
「先生。何か悩んでいらっしゃるんじゃないでしょうか?」
山武の瞼がピクっと動いた。
「なやんでなんかいないよ。」
山武はすぐに否定したが、その声は少しふるえていた。それがはっきりわかったので玲子は少しうれしくなった。
「うそだわ。顔にあらわれてるもん。」
山武は答えない。
「先生。悩み事があるんでしたら教えてください。私でお役に立てることがありましたら何でもします。」
「ありがとう。でもいいよ。これは僕の問題だから…・。」
「ひきょうだわ。先生。」
玲子は間髪を入れずピシャリと強い語調で言った。山武は玲子の発言に驚いた。
「ひきょうってなぜ?」
「だって先生、ホームルームの時おっしゃったじゃないですか。悩み事があったら、どんな事でもいいから一人で悩んでいないで話しにきなさいって…・。」
「それとこれとはわけがちがうよ。」
「どうちがうんですか?」
「それは…・僕は教師で、君達は生徒という立場の違いだよ。」
「そんなのわからないわ。人にいってることを自分はしないなんて、やっぱりずるいわ。それに先生が学校をやめるんなら先生と生徒という関係もなくなるんじゃなくて?」
(うぐっ。)
山武は再びのどをつまらせた。
再び沈黙に入りそうな気配をおそれた玲子は勇気をふるって言った。
「先生。やめないでください。これは私の気持ちであると同時にみんなの気持ちでもあると思います。だって先生はとってもやさしいんですもの。でも私だけは別みたい。私、今日先生が学校をやめると聞いて、それは何だか私のせいのような気がしてしようがないんです。いいえ、きっとそうにちがいないわ。私、先生にやめられたらつらくてしかたがないわ。私のせいで先生がやめるなんて…・。これは私の思い込みでしょうか?」
玲子の目にキラリと一粒涙がひかった。
「教えてください…・。先生。」
玲子は涙にうるんだ瞳をに向けた。
玲子はつかれていた。山武も同じだった。山武はうつむいたまま両手で顔をおおった。再び沈黙がおとづれた。静まり返った部屋の中で置き時計の音だけがだんだん大きくなって聞こえてくる。たまに聞こえるのは夕焼け空をわたる烏の鳴き声くらい…・。
二人はともに悩み、そしてつかれていた。山武はうつむいていたが玲子の気持ちは手にとるように伝わってきた。
(これ以上、彼女を苦しめるのは教師として失格だ。)
山武は決断した。
「じゃ、話すよ。」
その口調にはやや諦念の感があった。
「でもいったらきっとけいべつされるだろうな。」
山武は上目づかいに半ば独り言のように言った。
「そんなことぜったいしません。」
玲子はきっぱり言った。
「いや、するよ。」
「しません。」
山武は大きくため息をついた。
「だれにもいわないでくれる。」
「いいません。」
「ほんとう?」
「私は敬虔なクリスチャンです。神に誓います。」
山武は再び大きくため息をついた。それは以前の悩みのため息とは違う諦念のため息だった。
「実は…・。」
「ええ。」
玲子は少し身をのり出した。
高校生は好奇心のかたまりである。そして教師を説得させたという思いが彼女を少し陽気にさせていた。
玲子は好奇心満々の表情だった。目は、かっと大きくみひらかれ、その照準は寸分たがわず山武の口唇に定められ、そして全神経を耳に集中しているかのごとくだった。まさに満を辞して山武の返答を待っているといった様子である。
そんな玲子をみて山武の言葉はまたとぎれてしまった。玲子の心に少しいらだちが起こった。
「先生。男でしょ。」
この言葉はいかに気の小さい男にでも行動を起こさずにはおかないものである。山武のためらいは完全に消え去った。
「じゃ、言うよ。けいべつされても、もういいよ。実は…・・夜、床につくとなぜか必ず君の顔がうかんでくるんだ。そして…・」
と言って山武一瞬はためらった。が、
「そしてどうなんです。」
と玲子が非常に強い語調で言ったので、山武は(もうどうとでもなれ)という捨て鉢な気持ちになってきっぱり言った。
「そして君がいろんな拷問にかかって、泣き叫んでいる姿が浮かんでくるんだ。」
言って山武は強く目をつむってうつむいた。あと彼女が自分をどう思うか、それはもうすべて彼女に任せてしまったのだ。そう思って山武は恐る恐る顔を上げた。玲子はにこにこしている。山武はおそるおそる聞いた。
「どう。けいべつした。」
「ううん。けいべつなんかしてないわ。ほんとうよ。でもちょっとおどろいたわ。」
玲子の目には確かに軽蔑の念は感じられなかった。山武はほっとした。玲子は無邪気に笑っている。
「でもどんな拷問なの。」
「いえないよ。そんなこと。」
「ずるいわ。たとえ想像でも私を拷問にかけといて…・私知る権利あるわ。」
彼女は子供っぽい口調で言う。山武の心に瞬時に彼女に秘密を話してしまったことに対して後悔の念が起こった。いわなければよかったと思った。玲子の心変わりのあまりもの速さに、さっきの玲子の真剣な表情や、涙の訴えなどは実は多少芝居がかっていたのではないかと、鈍感な山武は今になってはじめて思った。そういえば玲子は演劇部でもある。だがもうおそい。覆水盆に返らず…・である。一度聞かれてしまった言葉は一生忘れられないのである。
「どんな変質的な拷問なんですか。」
玲子はじっと山武を見据えながら聞いた。
「言えないよ。そんなこと。かんべんしてくれ。」
山武は紅潮した顔を下げて哀願した。
「だめです。言ってください。」
玲子は眉を微動だにせず真剣な表情で山武の哀願を却下した。玲子はまるで宇宙人でも見るかのような目つきで黙ったままじっと山武を見つめつづけた。数分そのままの状態が続いた。
山武は何だか自分が刑事の尋問をうけている犯罪者のような気がしてきた。玲子の固定した視線が山武を苦しめた。(もちろんこれは玲子の芝居である。こうすることが山武を最も苦しめるということを玲子は知っている。だが小心な山武にはそれがわからないのである。)いつまでたっても玲子は黙ったまま山武をじっと見つめている。このままでは自分が言わないかぎり玲子はいつまでもこの状態を続けるだろうと山武は思った。また玲子もそのつもりだった。それで、とうとう山武は玲子のこの沈黙ぜめに耐えきれなくなって、尿意は起こっていないが、
「ちょっとトイレにいかせてくれ。」
と言って立ち上がろうとした。だが玲子はすぐさま「だめです。」といって山武の腕をつかんで引きとどめた。この玲子の強引な行為に山武はおそれを感じて、トイレに行くのをあきらめて腰を下ろした。玲子は相変わらず黙然とした表情で炯々と山武をみつめている。ついに山武は玲子の黙視責めに耐えられなくなって
「わかったよ。はなすよ。話すからどうかその宇宙人をみるような目はやめてくれ。」と言った。
「そうです。言ってください。」
「ええと。何についてだったかな。そうそう。今度の文化祭で、何をやるかについてだったね。」
といって山武は手を打った。だがそんな子供だましが通用するはずがない。玲子はあいかわらず真顔で山武をみつめながら即座に、
「ちがいます。想像で私をどんな拷問にかけて楽しんでいたかについてです。」
おそれを感じてすぐさま、
「別にたのしんでなんかいないよ。僕の意思とは無関係におこるんだよ。」あわてて弁明する。山武の頭の中は混乱していた。やっぱりいわなければよかった、とつくづく後悔した。
だがもうおそい。のってしまった船である。山武はうつむいてため息をついた。
しばしの時間がたった。山武の頭は混乱から疲弊状態へと移っていった。
「実家で父親と母親が病気で寝ているんです。」
などとありもしないことを目に涙を浮かべて言いたくなった。
窮鳥もふところにはいれば…・。
それで山武はチラッと玲子をみた。するとそこにはさっきと少しも違わない氷のような無表情の玲子のまなざしがあった。そしてそのきびしい女刑事のような表情は無言のうちにこう語っているように思われた。
「君はもうすでに完全に包囲されてる。いかなる抵抗も無駄である。」
山武はついにこの女刑事に自首する覚悟をきめた。
「わかったよ。いうよ。」
だがそれは彼女に軽蔑の念が全くなかったとしても最悪の羞恥の念なしには言えるものではなかった。言いながら声が震えてきた。
「雪の日に木に縛りつけたり、算盤板の上に正座させて石を膝の上にのせたり、木につるして火あぶりにしたり、体がやっと入るくらいの頑丈なガラスの箱に入れてヘビを入れたり…・。」
「ひどいわ。私ヘビなんていれられたらとてもじやないけど耐えられない。」
言いながら玲子はクスクス笑い出した。
それをみてはじめて、鈍感な山武は玲子の芝居に一杯くわされたことを知って地獄におとされた罪人のようにくやしがった。
「でもどうしてそんなことするの。私がそんなに憎いの。」
「にくくなんかないよ。むしろ…・。」
と言ってあわてて口篭もった。
「じゃ何で私を拷問にかけるの。」
「わからないよ。自分でも自分がいやでたまらないよ。」
「学校やめるのもそのため。」
「ああ。そうさ。こんな性格の教師、失格だよ。」
玲子は今度はさっきとはうってかわったうれしそうな顔である。
「先生。やめないで下さい。私なら別にかまいません。」
「ありがとう。本当なら僕のほうから言うべきなのに。まったくなさけない話しだ。」
「転任するのもそのため。」
「ああ。そうだよ。」
「先生。やめないで下さい。私なら本当にかまわないんです。」
彼女の口調は真剣になった。
「ありがとう。でも君かよくても僕がだめなんだ。こんな性格で女子校の教師をするべきではないよ。」
「そんなこと絶対にありません。先生ほどいい先生めったにいません。授業は誰がきいてもわかるように丁寧に教えてくださるし。とってもやさしいし。」
「ありがとう。僕だってできることならこの学校でつづけたいさ。でもやっぱりやめるべきだ。僕自身苦しいしね。僕のこの変な癖は昔っからだった。たぶん一生なおらないと思う。ここにいれば悩みつづけるだけにきまっている。だから転任すると決めたんだ。」
精神浄化作用が心の重荷を解いた。
玲子はうつむいて考え込んだ。今度は自分が何か言う番だと思った。
窓からさしこむ西日か玲子の頬を照らした。が、しばしの後、行雲によって遮られた。
時計の音は以前のように大きくなってこなかった。むしろ二人の間で時間が止まっているかのようだった。突然、玲子はパッと顔を上げた。
「先生。もしよければ私を拷問してください。そうすればきっと先生の気持ちもはれるわ。でもヘビだけはゆるしてくださいね。」
山武は驚きのあまりしばし呆然と玲子をみつめた。山武が玲子の顔をはっきり見たのはこれがはじめてだった。その目はとても澄んでいた。一瞬山武は我を忘れて玲子の目を見た。だが次の瞬間、頬のあたりから起こってきた羞恥の念が山武の意識を現実に戻した。
「できないよ。そんなこと。絶対に。それに現実に君を拷問にかけたいと言う気持ちはないような気がするんだ。」
「それって空想サディズムね。」
「ああ、そうだね。」
ちょっぴり投げやりな口調で言う。山武が心のすべてを語ってくれたことが玲子に安心感をもたらした。同時に玲子の心にちょっぴり、(いや、かなり)いたずらな気持ちが起こった。
「先生、やめないで。やめたらみんなに先生が変態だって必ずいいふらしますから。」
玲子は子供っぽい口調で言った。山武はおそれで顔が真っ青になった。
「ずるいよ。さっき誰にもいわないっていったじゃないか。」
山武はおおあわてに言った。
「女心は秋の空っていうじゃない。」
そういって玲子は両手で頬杖をついて笑った。
「お願いだからそれだけはやめてくれ。そんなことされたら僕はもう生きてられないよ。」その哀願は真剣そのものだった。玲子はますますうれしくなった。それは生殺与奪の権を手にした人間が感ぜずにはいられない至福の喜びだった。
「そうね…・じゃ考えとくわ。先生が学校をやめないでくれるんなら絶対だれにもいわないわ。」
「そ、そんな…・」
その声は蚊の鳴くほど弱かった。玲子は手を打った。
「そうだわ。私が3年に進級するまではやめないで。だってあと半年じゃない。そうすれば絶対誰にも言わないわ。」
山武はぐったりうなだれていた。自分がばかなことを言ってしまったとつくづく後悔した。しかし心の片隅に、あえて言ってよかったという気持ちもかすかではあるが確かにあった。
山武は大きくため息をついて顔を上げ、玲子をみた。ふたたび雲間からあらわれた西日が玲子の顔を照らした。玲子は無邪気な笑顔で笑っている。その無邪気さに一点のくもりもないのを感じると山武の心の中にあった、あえていってよかったというかすかな気持ちは徐々に大きくなっていった。山武は言った。
「わかったよ。そうするよ。」
そういって山武は大きく一呼吸して窓の外をみた。何度もみなれたつまらない田園の風景がはじめてみた景色ほどに新鮮に感じられた。山武は玲子に再び顔を向けていった。
「なんだかとてもすっきりしたよ。もう一度この学校でやってみようと言う気持ちが起こってきたよ。君のおかげだよ。ははは。変な話だな。教師が生徒に立ち直らされるなんて。」
山武は苦笑した。
「そんなことありませんわ。老いては子に従え、というじゃありませんか。」
「老いては、はひどいな。ぼくはまだ23だよ。」
「それより先生、もう辞表をだしてしまったんでしょ。どうするんですか。」
「それは撤回してもらうようたのんでみるよ。」
やっと一段落した気持ちになった。窓の外には一番星が見える。
秋は日がくれるのがはやい。山武は立ち上がってカーテンをしめ、電気をつけた。
再び玲子と向かい合わせに座った。
「先生、本当にやめないんでくれるんですね。」
「ああ。」
「あしたからまたきてくれるんですね。」
「ああ、いくよ。」
「よかった。これでまた先生のわかりやすい授業がきけるわ。」
と胸に手を当てて半ば独り言のように言う。
「せっかく先生のうちに来たんだから」
と言って玲子は思い出したようにカバンから教科書をとりだした。
「わからないところがあるんです。教えてください。」
と言って玲子は山武の隣にきて教科書のあるページを開いた。
「ああ、いいよ。」
といって山武は玲子のさしだした英語の教科書に少し顔を近づけた。
「ここがわからないんです。」
と言って玲子はあるセンテンスを指した。そこはまだ授業では教えていないところだった。だが勉強熱心な玲子はかなり先まで予習しているらしい。
「えーと、ここのherのとこです。」
「これは前文のa ship(船)のことだよ。英語の名詞はほとんど中性というか無性だ
けど船は例外で女性名詞なんだ。フランス語ではすべての物事に性別があるんだけどね。」
「わかりました。じゃ、ここはどうなんてすか。」
と言って玲子は別のページのセンテンスを指した。
「ああ、これは強調構文だよ。Itとthatの間のin self-sacrificeがthat以下のクロー
ズの副詞句になっているんだよ。」
「わかりました。じゃここはどう訳すんですか。」
と言って玲子は別のページを開いた。そして山武の体にほとんどふれんばかりに近づいた。玲子のストレートの長い黒髪から石鹸のような匂いが伝わってきた。
山武はここにいたってはじめて一つの重大なことに気がついた。それは自分が女性とこれほど近づいて話しをしたことなど一度もないということである。さらに山武はもっと重大なことに気がついた。それは今のこの状況がとてもあぶないということである。閉鎖された密室に男と女か肌がふれんばかりに近づいているのである。山武は心臓の鼓動がだんだん早くなってゆくのに気がついた。顔はだんだん赤くなっていった。同時に山武は自分の下腹部に血流が増加しはじめているのに気がついた。山武はあわててそれを玲子に気づかれないよう腰を少し引いた。山武は必死になってそこへの血流をいかせないようにした。だがそれは意志の力でコントロールできるものではなかった。心拍数の増加も同じであった。それは山武の必死の意志の制止をうらぎり指数関数的に上昇していった。山武が玲子の質問に答えないので玲子は山武の方にふりむいて、
「これはどう訳すんですか。」
と再び聞いた。玲子がもろに山武に顔を向けたことが致命傷を与えた。
「こ、これは…」山武の言葉はひどく震えていた。彼はもうその先を言うことができなかった。これ以上少しでも何かしゃべれば玲子に今の自分の苦境を悟られてしまう。だが答えないわけにはいかない。だが何かしゃべればその震えた口調から今の自分の心境を気づかれてしまう。まさにどうしようもない状況である。頭はますます混乱し、心拍数はますます高まる。
「どうしたんですか。先生。」
答えてくれない山武にしびれをきらした玲子が山武のほうに再び顔を向けて聞いた。だが山武は答えられない。うつむいて真っ赤になっている山武をみて玲子は山武の心を察し、うれしくなった。同時に山武をからかってみようといういたずらな気持ちが起こった。
「先生。何を真っ赤になっているの。」
わざとおちつきはらって丁寧な口調で言う。
山武は答えられない。うつむいたまま頬を紅潮させている。そんな山武をみて玲子のいたずらな気持ちはますます大きくなった。玲子はいきなり山武の手をにぎった。ふるえている。
「な、なにをするんだ。」
山武は声を震わせていった。
「先生、いやらしいこと考えていたでしょ。」
「ば、ばかな。そんなことはないよ。」
「じゃ何で声が震えているの。」
山武は答えられない。玲子の山武をからかいたい欲求は頂点にたっした。
「せえ~んせえ~。」
玲子はめいっぱい、あまい声で言って山武の肩に頭をのせてきた。そして目を閉じた。
山武の心臓は、はちきれんばかりにその拍出量を増した。
「な、なにをするんだ、根木君。」
山武は声を震わせていった。
普通良識のある教師だったら、こういう時、「ばかなまねはやめたまえ。」と言って、彼女をひきはなすであろう。だが小心な山武には、それができないのである。
なぜかというと、一般に女性の方から男に声をかけてきた場合、それをことわることは女性に大変恥をかかせることになる。すぐに彼女をつきはなしてしまっては彼女に恥をかかせることになる。それがこわくて山武は玲子の手をふりほどくことができないのである。
それは山武の本心である。だがそれを大義名分に山武は、確かに、感じてはならないものを、いけないと思いつつ感じていた。
頬にふれる清潔な石鹸のような匂いがする黒髪を…。
肩から伝わってくるふくらみを…。
その谷間から伝わってくる心臓の鼓動を…。
山武の心は、極楽の蓮台の上で身を寄せ合っている佐助と春琴の心境に近かった。
山武の本能は求めていた。
できることならいつまでもこうしていられたら・・・。
だが山武の理性はそれを激しく否定していた。
(こんな状態をみとめることは教師のモラルに反する。)
山武の超自我は山武にそう強く訴えていた。
「や、やめたまえ。根木君。」
山武は声を震わせていった。
玲子に恥をかかせることのできない山武にできる唯一のことは、言葉による制止だけであった。だが玲子は山武の言葉など聞く耳をもたぬかのごとく、うっとりと、柔らかい笑顔で目をつむったまま、手を離そうとしない。
「先生。」
玲子はあまい声で言った。
「好きにしてもいいわよ。」
山武は一瞬、心臓が破裂して死ぬかと思った。全身がカタカタと小刻みに震えてきた。 「な、なにをばかなことをいうんだ。」
すぐさま言うが玲子は聞く耳を持つそぶりもみせない。
「私を拷問にかけたいんでしょ。かけてもいいわよ。」
山武の心臓は破裂するかと思うくらいその拍出量を増した。
「そんなことできるわけがないじゃないか。それにさっきも言ったように現実に君を拷問にかけたいという気持ちなんかないんだよ。ほんとうだよ。」
玲子は何も言わない。うっとりと柔らかい笑顔で目をつむっている。
「とにかくこんなことしててはいけないよ。」
そう言って山武は玲子の手をほどき、彼女をひきはなした。
玲子が体を寄せてきてからかなりの時間がたっていたので、これならもう玲子に恥をかかせないですんだことになると思ったからだ。だが山武の本心を言えば、ちょっぴり(いや、かなり、いや、相当)残念ではあったが…・。
引き離された玲子は笑顔で山武をみている。山武はやっと極度の緊張感から開放されて、ほっとした。山武の心拍数は徐々に平常値にもどっていった。玲子は立ち上がって山武と向かい合わせに座った。玲子はしばし、うれしそうな顔をして山武をみていたが突然、
「先生、恋人いる?」
と聞いた。
「…・。」
「どうなんです?」
「い、いないよ。」
山武はうつむいて答えた。
「イナイ歴何年?」
山武の心に(そんな質問に答えなきゃならない義務はないよ)と言いたい衝動が起こったが、小心な山武は玲子を前にして彼女に何か聞かれると正直に答えなくてはならない義務感のようなものが起こってしまうのだ。それでうつむいて「23年。」と正直に答えた。
「じゃ、いままで一度も恋人をもったことがないんですね。」
玲子はものすごくうれしそうな顔をしている。
「恋をしたことはあるんですか。」
玲子はさらに追い討ちをかける。これにはさすがの山武も少しいらだって、
「そこまで答える義務はないよ。」
と言った。 玲子はうれしそうな顔をして、
「先生。なにかの本で読みましたが、禁欲的な精神状態があまりに嵩じすぎると倒錯し
た感情が起こると書いてありましたよ。」
山武自身そのことは知っていた。そして自分の精神状態がまさにそれであることも…・。
「先生。私のこときらい?」
「な、何を言うんだ。やぶからぼうに。」
「どうなんです。きらいなんですか。」
玲子は即座に追い討ちをかける。
「き、きらいじゃないよ。」
「じゃ、好き?」
(そんな子供じみた質問に、)と、つい思ったが、自分自身に、短気をおこすな、と叱咤して、
「生徒に個人的な感情をもつことは教師のモラルに反することだよ。だが一生徒として
はもちろん好きさ。」
玲子はあいかわらず、うれしそうな顔で山武をみつめていたが突然、
「私が先生の恋人になってあげるわ。どう?私じゃいや?」
と聞いた。狼狽した山武だったが、すぐに、
「だめだよ。そんなこと教師のモラルがゆるさないよ。」
玲子は山武のあまりに融通のきかなさにいささかじれったくなって、
「じゃ今度いつか一回でいいですから、どこかでデートしません?」
「だめだよ。それもモラルに反するよ。」
「もう、モラル、モラルって、かたっくるしいんですね。」
玲子はいらだたしげに言った。
山武はうつむいて「ごめん。」と言った。一瞬の間を置いて、玲子にふと面白い口実がおもいついた。
(これなら山武の律儀さを逆に利用できる)
と思ってうれしくなった。
「一日でいいからデートしましょう。だって今まで私を無視しつづけてきて、私を悩ま
してきたんだもの。その謝罪としてなら先生の心のバランスもたもてるんじゃなくて…。」
山武はしばし考えた後、
「わかったよ。デートするよ。ただし一回だけだよ。こんなことが学校にしれたらたいへんだからね。君も僕も身の破滅だよ。」
「うれしい。じゃ、どこにしようかなー。」
玲子は頬杖をついて天井をみながらしばし考えた。
「そうね。じゃ今度の日曜日。渋谷で。ブティックで洋服買って…。前からほしいと思っていた服があるの。それから他にもほしいものいろいろあるの。そのあとスカイラウンジでフランス料理食べて…・。もちろん費用は全部先生持ちで…。どう?」
「わかったよ。それで謝罪になるならそうするよ。ただし一回だけだよ。こんなことが学校にしれたら身の破滅だからね。」
もう、外は暗くなっていた。
秋の日はつるべ落としである。
もう7時になっていた。
「もう、こんな時間だから帰ったほうがいい。」
玲子は「はい。」と言って、教科書をかばんにしまった。そして、立ち上がって、玄関にむかった。彼女は靴をはいてから、ふりかえり、
「先生。あした必ず学校にきてくださいね。」
「ああ、必ず行くよ。」
「絶対ですよ。こなかったら先生の秘密いいふらしちゃいますからね。」
山武は一瞬、ギョッとして、顔から血の気が引いた。
「いくよ。必ずいくから、それだけはお願いだからいわないで。」
玲子は一瞬、「いまのはジョークですよ。」と言おうかと思ったが、やっぱり、それはやめにした。多少、非常なようでも言わないでいるほうが山武を確実に学校に来させることができると思ったからだ。それで、つつましい口調で、
「先生。今日はどうもありがとうございました。私の勝手な頼みをきいてくださって。
それに勉強もおしえていただいて。」と言って、ペコリと頭をさげた。
山武は内心ほっとして、
「僕の方こそ君にお礼をいわなくっちゃ。またあの学校で教師をつづけようと思うことができたのは君のおかげだよ。」
玲子は再びペコリと頭をさげてから階段を降りていった。
☆ ☆ ☆
玲子を見送ってからドアを閉めると山武は再び机の前に腰をおろした。
山武はしばしの間、我を忘れて、呆然としていた。山武の頭は、まるでるめまぐるしく進行する映画をみたような状態だった。実際、副交感神経優位型の山武にとって、これほど神経の酷使を要求された経験は生まれて一度もなかった。山武の頭はしばしの間、空白状態だった。
だが時間の経過が徐々に山武の意識を現実にもどしはじめていた。山武は無意識のうちに、玲子に対して心のすべてをあかしてしまったことが、はたして本当によかったのかどうか考えだしていた。再び、「やっぱりゆわないほうがよかったのでは。」という考えがあらわれだした。だが、玲子の悩みを解いてやったのだし、再びあの学校で教師をつづけようという決意がもてたのだし、やっばり言ってよかったのだという考えも心の一方にあった。30分ほど、その葛藤が山武を悩ませつづけた。
ポツポツと窓ガラスを打つ音が聞こえ出した。小雨がふりだした。
結局、山武はやっぱり、言ってよかったのだという結論に達した。心のそこからそう思ったのではなく、無理にそう思い込もうとしたのだった。それで気をまぎらわそうと明日の授業の予習をはじめた。山武は書棚から教科書とノートをとり、机に向かった。明日おしえるところは関係代名詞である。わかりにくい授業というのは教師が、わかっている自分を基準にして教えるからわからないのだ。もっと生徒の立場に立ってわかりやすくおしえなければ…・。
「えーと。関係代名詞とはそもそも先行詞とそれを形容する形容詞節をつなぐ代名詞であって、先行詞はその形容詞節の中で、関係代名詞がwhoであれば主格、whomであれば目的格、whoseであれば所有格としてはたらき…。」
(だめだ。だめだ。こんな説明の仕方じゃわかってもらえない。もっとわかりやすく説明しなければ…・。)
それから30分近く、山武は関係代名詞の説明の仕方を考えた。だがどうもうまい説明の仕方が思いつかない。すると再び心の奥にしまいこんた玲子のことが気になりだした。
「やっぱりいわない方がよかったのでは。」という否定論が生まれ出した。そしてそれは加速度的に大きくなり、小心な山武を悩ませ出した。
「よく考えてみれば、ばかなことをいってしまったものだ。何で心のすべてを言ってしまったのだろう。なにも、いわなくてはならない義務などないのだ。」
そう考え出すと山武の心は否定論一辺倒になってしまった。山武は茶を飲みながら、冷静になろうと考え、もう一度何で自分が玲子に心を開いてしまったかを考えてみた。
「彼女に心を開いたのは彼女が真摯な態度で悩みを打ち明けてきたからだ。生徒の深刻な悩みに応じるのは教師の責任だからだと思ったからだ。ましてや自分が生徒を悩ましてるのであればなおさらだ。」
そう思うと山武の心に再びいってよかったという気持ちが起こってきた。そう思うと山武は急にうれしくなって、歌でもうたいだしたい気分になった。外ではあいかわらず小刻みに小雨が窓ガラスをたたいている。山武は再び関係代名詞の説明の仕方にとりくんだ。だがどうもうまい説明の仕方が思いつかない。髪をかきむしり、呻吟して考えた。一時間ほど経った。するとまた一つのことが気になりだした。それは、彼女が誰にもいわないでくれるだろうか、ということだった。彼女ひとりが知っているならまだいい。だが玲子が誰かにしゃべってしまったら。そして、それが口から口へと学校中の生徒達に知れ渡ってしまったら。そう考えると山武はいてもたってもいられなくなった。彼女はしゃべらないでくれるだろうか。絶対しゃべらないとさっきは約束してくれた。あの子は誠実な子だから、もしかしたらしゃべらないでくれるかもしれない。だが彼女は友達も多く、友達と愉快におしゃべりするのが三度の食事より好きな子だ。そう考えると山武は気もそぞろになり、血の気の引いた顔を両手で覆った。おれはなんてばかなことをしてしまったのだ。彼女は今日のことは一生忘れないだろう。彼女が一生秘密を守ってくれるなんてまず無理だ。きっといつかなにかのひょうしにいってしまうだろう。
おれは一生彼女のきまぐれにおひえて生きなければならない。気の小さい人間の考えというものはひとたび否定的になるとそれは雪の坂道から雪だるまをころがすようにとめどもなく大きくなっていくものである。もしかすると彼女はもうすでに携帯電話で友達に今日のことを自慢げにはなしてしまっているかもしれない。そんな考えまでも起こってきた。あした学校にいくと玲子に約束したけれどやっぱりやめようか。学校も転任しようか。山武は一瞬本気でそう思った。だがすぐにそれはゆるされなことに気づいた。あした学校にこなければみんなにいいふらすといったからだ。(玲子にしてみればこれは冗談でいったつもりだったが小心な山武にはそれがわからないのである)
「ともかくあした学校へいかなくては…。」
山武はそのため、再び、関係代名詞の説明の仕方を考えようと思って教科書を手にとった。だが混乱した頭には、とてもそんなことを落ち着いて考えるゆとりはなかった。
山武は(もうどうとでもなれ)という捨て鉢な気持ちになって、ポテトチップスとポカリスエットをもってきて、テレビのスイッチを入れた。酒が飲める人ならこういう時、やけ酒を飲むのだろうが山武は酒が飲めない。
テレビではボクシングの日本バンタム級タイトルマッチが始まるところだった。放送席にはゲスト解説者として、元ライト級世界チャンピオンがいた。
「挑戦者はどういった戦術でチャンピオンに対抗したらいいのでしょうか。」とのアナウンサーの質問に対し、ゲストの元世界チャンピオンは、
「チャンピオンは持久戦に強いです。一方、挑戦者のA君はスタミナの点でやや劣りますが、インファイトを得意とする速戦型です。ですから第一ラウンドから一気に攻めるべきでしょうね。それが唯一の勝機をつかむ方法ですよ。」
と自信に満ちた解説をした。それをセコンドが聞いていたのか、実際、試合が始まると挑戦者は第一ラウンドから一気に攻めた。すると第二ラウンドでチャンピオンのカウンターパンチが挑戦者にきれいにきまった。それが起点となって勝敗の趨勢は一気にチャンピオンの側へ傾いた。第二ラウンドの終わりには挑戦者はもう足にきていた。そして第三ラウンドで挑戦者はチャンピオンの連打をうけ、ダウンし、あっけなくK・Oで勝負がついた。
「敗因はいったい何だったのでしょうか。」
とのアナウンサーの質問に対し、ゲストの元世界チャンピオンは、
「いやーA君はスタミナの配分を考えなかったのがまずかったですね。それが最大の敗因とみてまず間違いないでしょう。」
としみじみした口調で語った。山武はこの元世界チャンピオンは現役時代、パンチをくいすぎてパンチドランカーになってしまったのだと確信した。山武はチャンネルをかえた。プロレス中継をしていた。ジュニアヘビー級の試合で、メキシコの空中殺法を得意とする覆面レスラーと蹴りのうまい日本のレスラーとの対戦だった。ヘビー級ではみられない、スピーディーな試合だった。山武は覆面レスラーをみてふと思った。
覆面・・・・正体を知られない・・・・うらやましい・・・・あした・・・・ふくめんをしていこうか・・・・そのためには・・・・今からふくめんを縫わねば・・・・先生が・・・・よなべーをして・・・・ふくめーん編んでくれた・・・・などとばかげたことを考えていた。プロレス中継は三十分ほどでおわった。時計をみるともう一時をまわっていた。あした遅刻してはみっともない。山武はもう寝ようと思って、机をかたずけて、蒲団をしいた。そして歯をみがいてから、10回口をゆすいで、寝間着に着替え、床についた。山武は蒲団の中で、えびのようにちぢこまって、どうか玲子が一生しゃべらないでください、とゲッセマネのキリスト以上の敬虔さをもって心の底からいのった。窓の外では、あいかわらず雨が屋根を叩いている。山武は枕元に置いてある数冊の本の中から「図太い神経になるには」という本をとって、パラパラとめくって読んだ。山武は小心な自分の性格をかえたくて、以前にこれを買って読んだのだが、本をよんだからといって性格はかわるものではない、とつくづく思った。そうこうしているうちにやがて睡魔がおとずれて、山武の意識は徐々にうすれていった。山武の精神は山武にとってもっとも安楽で平和な世界へ入っていった。
☆ ☆ ☆
翌日は雨はやんでいたが、あいかわらず降り出しそうなくもり空だった。降水確率は五十パーセントとテレビの天気予報は言った。彼女はもうきのう、みんなに電話をかけまくって、みんなおれの恥を知っているにちがいない。ペシミストの山武はもう、そう確信していた。だが鏡の前でネクタイをしめながら、山武は心の中で決死の覚悟をした。
しっかりしろ。世の中にはもっとつらい恥に耐えて生きている人間もかぞえきれないほどいるじゃないか。なにも死刑になるわけじゃなし…・。
トーストとコーヒーの軽い朝食をすませたのち、七時半に、意を決し、アパートをでた。学校へは四日ぶりである。精神が高ぶっているため、いつもの景色がはじめてみるように新鮮に感じられる。駅までの道で、山武はこの日、この前まではまったく気がつかなかった、路傍の一輪の青紫色の桔梗の存在に気づいた。通勤電車はあいかわらず、すしづめだった。
駅を降りて、学校に近づくにつれ、生徒達の姿がちらほらみえだした。山武の心に再びためらいの気持ちが起こった。
躊躇する気持ちが山武を立ちどまらせた。
その時、
(キキー!!)
自転車の止まる音が背後に聞こえた。山武はうしろからポンと肩をたたかれた。
山武がふり返ると玲子がいた。
「おっはよ。先生。」
その笑顔は昨日のことなどまるで忘れているかのようだった。
「や、やあ。お、おはよう。」
山武はひきつったような無理につくった笑顔でこたえた。だがその顔は今にもなきそう
なほど弱々しかった。玲子は刹那に山武の今の心をみぬいた。同時に、やさしさがおこってきた。
「きのうのこと、まだ誰にもいってないよ。一生誰にもいわないよ。だから学校やめな
いでね。今度の日曜デートしよ。」
そう言って玲子はペダルを力強くこいでいった。
この一言は山武の悩みを瞬時にして完全に取り去った。
きのう一晩悩んだことは、まったくの取り越し苦労だったのだ。
山武の心に今まで一度も経験したことのないほどのよろこびがわきあがってきた。
この学校でもう一度やろう。やっていける。という自信と、そのよろこびが胸の奥深く
からはちきれんばかりにわきあがってきた。
刹那の手持ちぶさたが山武の顔を空へ向けさせた。
かわりやすい秋の空ではいつしか雲間から日がさしはじめていた。
設定 Situasion
東京郊外のある私立の女子高校で、
一学期の半ば頃、英語担当の女教師が結婚して、他県の高校へ、転任することになったので、今春大学をでて、ある男子校で教鞭をとっていた山武に、彼女から後任のたのみがもちかけられました。彼は彼女と同じ大学で、クラブの後輩でした。山武はこれをひきうけました。山武は女子高の近くのアパートに引っ越して、さっそく女子高で教鞭をとることになりました。山武は英語の担当の他に、二年B組の担当もすることになりました。山武は内気な性格でしたが、熱心なため、生徒達の評判もよかったのですが、でも担任の二年B組の一生徒、根木玲子はなぜか山武が自分にだけはよそよそしい態度のように感じられてなりませんでした。一学期が無事終わり、夏休みも過ぎ、二学期も半ばにさしかかったある秋の日のこと…・。
三日つづけて山武が学校を休んだ日の昼休み、玲子はそのわけを教員室にたずねにいった。すると何でも山武はどこかの男子校に転任するらしいとのことだった。
その日の放課後、玲子は山武のアパートをたずねた。
玲子は山武が自分をさけているような気がしてならなかったのだ。その疑問がわからないまま山武が転任してしまうのはなんともあとくされが悪い。さらに玲子はなんだか山武が転任するのは自分のせいであるような気さえしていた。山武のアパートは学校の最寄の駅から二駅目で、駅から歩いて十分くらいの静かなところにある四階建てのワンルームマンションだった。
周りは一面大根畑だった。このあたりの土壌は、深くてやわらかい黒つちなので、大根、にんじん、ごぼうなどの根菜類に適していた。山武の先任の女教師もそこに住んでいた。以前、玲子は数人の友達と、その女教師のアパートをたずねたことがあったので、場所は知っていたのだ。
先任の女教師が転任して部屋をでるのと入れ替わるように、山武が同じ部屋に入居したのである。玲子は駅前の不二家でマロンケーキとモンブランを買っていった。途中、玲子は通行止めにあった。
小学校低学年くらいのい子供達が四、五人、道にしゃがみ込んで、チョークで絵を書いている。玲子はしゃがみこんで、馬の絵を書いた。
子供達は、
「うまーい。」
と言って拍手した。その中の一人の子は自分達の言ったことばが、しゃれになっていることに気がついて笑った。一人の子が、
「もっとかいて」
と催促した。が、玲子は立ち上がり、
「ちょっと用事があるから、また今度ね。」
と言って手を振って歩き出した。
それから数分もしないうちに山武の住んでいるアパートが見えてきた。
山武の部屋は3階だった。玲子が戸をノックすると鈍い返事がして、足音が聞こえ、戸が開いた。そして中から山武が眠そうな目をこすりながら、ものぐさな様子でぬっと顔を出した。
それをみて玲子はクスッと笑った。山武は予期しない訪問者にたいそう驚いた様子で、へどもどして、さかんに髪をかいて、「やあ。」と返事した、が当惑して
「すまないがちょっとまって。」
と言って戸を閉めた。中でどたばた音がする。5分位して戸はまた開いた。出てきた山武をみて玲子は再びクスッと笑った。山武は、いつも学校へ着てくるスーツを着ている。さすがにネクタイまではしていなかったが。
「よくきてくれたね。まあ、とにかく入って。」
山武は言った。玲子は山武の口調に、かすかに社交辞令ではない真意があるような気がしてうれしくなった。通された部屋は応急手当したあとらしく、多少きれいにかたづいていた。
「あんまりきれじゃなくてすまないけど…・。」
と言って山武は玲子に座布団を差し出した。それはぺしゃんこで生地が光っていた。
玲子はカバンを置いて、座って部屋をみまわした。
さすがに教師の部屋だけあって書物が多い。
まさに汗牛充棟である。山武は英文学が専攻だった。
心理学や哲学の本が多かった。
「先生。ケーキを買ってきました。」
といって玲子はそれを机の上に置いた。
「やあ。それはどうもありがとう。じゃ今、お茶を入れるよ。紅茶でいいかな。」
と山武が聞くと、玲子は「はい。いいです。」と答えた。
山武は台所にポットと紅茶ととティーポットと紅茶茶わんをとりに行った。
紅茶ちゃわんは一つしかなかったのいで、自分は湯のみにすることにした。
幸いポットはいっぱいだった。それをやかんにうつしてあたためなおしたが一分もかからずお湯はわいた。
キッチンからもどって山武は玲子と向かい合わせに座った。
「先生。モンブランとマロンケーキのどっちが好きですか。」
「君はどっちがいい。」
「私はどっちでもいいです。先生のために買ってきたんです。先生が好きなほうをとってください。」
「そう。じゃ、マロンケーキをもらうよ。」
山武はあっさり答えた。もし、モンブランがなかったら、レストランに入るとすくなくても3分はメニューとむきあう、優柔不断度の偏差値が少なくみても65はある山武に、この選択に最低でも一分は費やさせたであろう。山武があっさり答えられたのはモンブランがあったからである。アルコール分解酵素の少ない山武は以前モンブランを食べて、それに含まれている少量のブランデーで顔が赤くなって恥ずかしい思いをした経験があるからである。山武は紅茶を入れた。二人は紅茶が出るのを少しの時間、待った。
「あっ。そうそう。ケーキはいくらした?」
山武はあわてて財布をだした。
「いいです。私のおごりです。」
「いや、そういうわけにもいかないよ。僕が払うよ。」
「先生。」
玲子は少し強い口調で言った。
「人の好意は素直にうけるものですよ。ショートケーキ二つなんて五百円しかしません
。」
「…・わかったよ。ごめん。」
確かにそのとうりだと思って山武は財布を内ポケットに戻した。二人は食べ始めた。山武はなんだか、照れくさくて、うつむき加減に食べた。
玲子はそんな山武がちょっと面白くて、じっと山武をみつめながら食べた。普通こういう時、女同士だったらしゃべられずにはいられない。
だが山武は内気な性格なので、こんな時、何を話したらいいのかわからないのである。
(何か話さなくてはならない。でも何を話したらいいのかわからない。)と山武は困っている。
玲子はそんな山武の心を見ぬいている。
山武は玲子から目をそらすようにして紅茶を飲んだ。重苦しい沈黙を玲子がやぶった。
「先生。どうして転任なさるんですか?」
山武は、たいそう驚いた様子で、口の中に含んでいた紅茶をあわてて飲み込んだ。
「いや、それは、つまり、その…・。」
山武はさかんに髪をかきあげながら、あやふやな返事をした。山武が当惑して口篭もるのを玲子はじっとみつめていた。玲子は何かやさしいことばをかけようかと思った。が、やっぱりそれはやめた。山武の本心をききだすには、こうしてだまってじっとみているのがいちばんいい。玲子は眉を微動だにせず、じっと山武をみつめつづけた。数分その状態が続いた。物理的には短い時間だったっが、精神的には山武にとって長い時間だった。山武はとうとう沈黙に耐えられなくなって、観念して言った。
「僕個人のちょっとした事情のためさ。」
「事情って何です?」
玲子はすぐに聞き返した。
「だからそれはいえない事情だよ。」
山武は湯呑に茶をつぎたした。山武は少しほっとして眉をひらいた。玲子もそれ以上問い詰める気にはならなかった。
「わかりました。それならばもうそのことは聞きません。そのかわり…。」
と言って、玲子は声を少し強めた。
「そのかわり、一つ教えて下さい。」
「ああ、いいよ。」
山武は肩の荷がおりた安堵感でおちついた口調で言った。
「どうして私を無視するんですか?」
(うっ。)
山武は驚きで一瞬のどをつまらせた。
「無視なんかしてないよ。」
山武はあわてて否定した。
「ウソ。先生は授業の時もホームルームの時も一度だって私をみたことがないわ。先生はわざと私から目をそむけるようにしていたわ。」
「そんなことはないよ。もしそうみえたんだとしたらあやまるよ。…ごめん。」
「あやまってもらわくてもいいんです。どうして私を無視するのか、そのわけを教えてください。」
玲子の口調は真剣だった。
山武は大きなため息をついた後、目をつむり、額に手を当てて再び黙ってしまった。重苦しい沈黙が再び起こった。山武は額にしわを寄せ、唇をかんだ。その沈黙を玲子はおちついた口調で破った。
「先生。何か悩んでいらっしゃるんじゃないでしょうか?」
山武の瞼がピクっと動いた。
「なやんでなんかいないよ。」
山武はすぐに否定したが、その声は少しふるえていた。それがはっきりわかったので玲子は少しうれしくなった。
「うそだわ。顔にあらわれてるもん。」
山武は答えない。
「先生。悩み事があるんでしたら教えてください。私でお役に立てることがありましたら何でもします。」
「ありがとう。でもいいよ。これは僕の問題だから…・。」
「ひきょうだわ。先生。」
玲子は間髪を入れずピシャリと強い語調で言った。山武は玲子の発言に驚いた。
「ひきょうってなぜ?」
「だって先生、ホームルームの時おっしゃったじゃないですか。悩み事があったら、どんな事でもいいから一人で悩んでいないで話しにきなさいって…・。」
「それとこれとはわけがちがうよ。」
「どうちがうんですか?」
「それは…・僕は教師で、君達は生徒という立場の違いだよ。」
「そんなのわからないわ。人にいってることを自分はしないなんて、やっぱりずるいわ。それに先生が学校をやめるんなら先生と生徒という関係もなくなるんじゃなくて?」
(うぐっ。)
山武は再びのどをつまらせた。
再び沈黙に入りそうな気配をおそれた玲子は勇気をふるって言った。
「先生。やめないでください。これは私の気持ちであると同時にみんなの気持ちでもあると思います。だって先生はとってもやさしいんですもの。でも私だけは別みたい。私、今日先生が学校をやめると聞いて、それは何だか私のせいのような気がしてしようがないんです。いいえ、きっとそうにちがいないわ。私、先生にやめられたらつらくてしかたがないわ。私のせいで先生がやめるなんて…・。これは私の思い込みでしょうか?」
玲子の目にキラリと一粒涙がひかった。
「教えてください…・。先生。」
玲子は涙にうるんだ瞳をに向けた。
玲子はつかれていた。山武も同じだった。山武はうつむいたまま両手で顔をおおった。再び沈黙がおとづれた。静まり返った部屋の中で置き時計の音だけがだんだん大きくなって聞こえてくる。たまに聞こえるのは夕焼け空をわたる烏の鳴き声くらい…・。
二人はともに悩み、そしてつかれていた。山武はうつむいていたが玲子の気持ちは手にとるように伝わってきた。
(これ以上、彼女を苦しめるのは教師として失格だ。)
山武は決断した。
「じゃ、話すよ。」
その口調にはやや諦念の感があった。
「でもいったらきっとけいべつされるだろうな。」
山武は上目づかいに半ば独り言のように言った。
「そんなことぜったいしません。」
玲子はきっぱり言った。
「いや、するよ。」
「しません。」
山武は大きくため息をついた。
「だれにもいわないでくれる。」
「いいません。」
「ほんとう?」
「私は敬虔なクリスチャンです。神に誓います。」
山武は再び大きくため息をついた。それは以前の悩みのため息とは違う諦念のため息だった。
「実は…・。」
「ええ。」
玲子は少し身をのり出した。
高校生は好奇心のかたまりである。そして教師を説得させたという思いが彼女を少し陽気にさせていた。
玲子は好奇心満々の表情だった。目は、かっと大きくみひらかれ、その照準は寸分たがわず山武の口唇に定められ、そして全神経を耳に集中しているかのごとくだった。まさに満を辞して山武の返答を待っているといった様子である。
そんな玲子をみて山武の言葉はまたとぎれてしまった。玲子の心に少しいらだちが起こった。
「先生。男でしょ。」
この言葉はいかに気の小さい男にでも行動を起こさずにはおかないものである。山武のためらいは完全に消え去った。
「じゃ、言うよ。けいべつされても、もういいよ。実は…・・夜、床につくとなぜか必ず君の顔がうかんでくるんだ。そして…・」
と言って山武一瞬はためらった。が、
「そしてどうなんです。」
と玲子が非常に強い語調で言ったので、山武は(もうどうとでもなれ)という捨て鉢な気持ちになってきっぱり言った。
「そして君がいろんな拷問にかかって、泣き叫んでいる姿が浮かんでくるんだ。」
言って山武は強く目をつむってうつむいた。あと彼女が自分をどう思うか、それはもうすべて彼女に任せてしまったのだ。そう思って山武は恐る恐る顔を上げた。玲子はにこにこしている。山武はおそるおそる聞いた。
「どう。けいべつした。」
「ううん。けいべつなんかしてないわ。ほんとうよ。でもちょっとおどろいたわ。」
玲子の目には確かに軽蔑の念は感じられなかった。山武はほっとした。玲子は無邪気に笑っている。
「でもどんな拷問なの。」
「いえないよ。そんなこと。」
「ずるいわ。たとえ想像でも私を拷問にかけといて…・私知る権利あるわ。」
彼女は子供っぽい口調で言う。山武の心に瞬時に彼女に秘密を話してしまったことに対して後悔の念が起こった。いわなければよかったと思った。玲子の心変わりのあまりもの速さに、さっきの玲子の真剣な表情や、涙の訴えなどは実は多少芝居がかっていたのではないかと、鈍感な山武は今になってはじめて思った。そういえば玲子は演劇部でもある。だがもうおそい。覆水盆に返らず…・である。一度聞かれてしまった言葉は一生忘れられないのである。
「どんな変質的な拷問なんですか。」
玲子はじっと山武を見据えながら聞いた。
「言えないよ。そんなこと。かんべんしてくれ。」
山武は紅潮した顔を下げて哀願した。
「だめです。言ってください。」
玲子は眉を微動だにせず真剣な表情で山武の哀願を却下した。玲子はまるで宇宙人でも見るかのような目つきで黙ったままじっと山武を見つめつづけた。数分そのままの状態が続いた。
山武は何だか自分が刑事の尋問をうけている犯罪者のような気がしてきた。玲子の固定した視線が山武を苦しめた。(もちろんこれは玲子の芝居である。こうすることが山武を最も苦しめるということを玲子は知っている。だが小心な山武にはそれがわからないのである。)いつまでたっても玲子は黙ったまま山武をじっと見つめている。このままでは自分が言わないかぎり玲子はいつまでもこの状態を続けるだろうと山武は思った。また玲子もそのつもりだった。それで、とうとう山武は玲子のこの沈黙ぜめに耐えきれなくなって、尿意は起こっていないが、
「ちょっとトイレにいかせてくれ。」
と言って立ち上がろうとした。だが玲子はすぐさま「だめです。」といって山武の腕をつかんで引きとどめた。この玲子の強引な行為に山武はおそれを感じて、トイレに行くのをあきらめて腰を下ろした。玲子は相変わらず黙然とした表情で炯々と山武をみつめている。ついに山武は玲子の黙視責めに耐えられなくなって
「わかったよ。はなすよ。話すからどうかその宇宙人をみるような目はやめてくれ。」と言った。
「そうです。言ってください。」
「ええと。何についてだったかな。そうそう。今度の文化祭で、何をやるかについてだったね。」
といって山武は手を打った。だがそんな子供だましが通用するはずがない。玲子はあいかわらず真顔で山武をみつめながら即座に、
「ちがいます。想像で私をどんな拷問にかけて楽しんでいたかについてです。」
おそれを感じてすぐさま、
「別にたのしんでなんかいないよ。僕の意思とは無関係におこるんだよ。」あわてて弁明する。山武の頭の中は混乱していた。やっぱりいわなければよかった、とつくづく後悔した。
だがもうおそい。のってしまった船である。山武はうつむいてため息をついた。
しばしの時間がたった。山武の頭は混乱から疲弊状態へと移っていった。
「実家で父親と母親が病気で寝ているんです。」
などとありもしないことを目に涙を浮かべて言いたくなった。
窮鳥もふところにはいれば…・。
それで山武はチラッと玲子をみた。するとそこにはさっきと少しも違わない氷のような無表情の玲子のまなざしがあった。そしてそのきびしい女刑事のような表情は無言のうちにこう語っているように思われた。
「君はもうすでに完全に包囲されてる。いかなる抵抗も無駄である。」
山武はついにこの女刑事に自首する覚悟をきめた。
「わかったよ。いうよ。」
だがそれは彼女に軽蔑の念が全くなかったとしても最悪の羞恥の念なしには言えるものではなかった。言いながら声が震えてきた。
「雪の日に木に縛りつけたり、算盤板の上に正座させて石を膝の上にのせたり、木につるして火あぶりにしたり、体がやっと入るくらいの頑丈なガラスの箱に入れてヘビを入れたり…・。」
「ひどいわ。私ヘビなんていれられたらとてもじやないけど耐えられない。」
言いながら玲子はクスクス笑い出した。
それをみてはじめて、鈍感な山武は玲子の芝居に一杯くわされたことを知って地獄におとされた罪人のようにくやしがった。
「でもどうしてそんなことするの。私がそんなに憎いの。」
「にくくなんかないよ。むしろ…・。」
と言ってあわてて口篭もった。
「じゃ何で私を拷問にかけるの。」
「わからないよ。自分でも自分がいやでたまらないよ。」
「学校やめるのもそのため。」
「ああ。そうさ。こんな性格の教師、失格だよ。」
玲子は今度はさっきとはうってかわったうれしそうな顔である。
「先生。やめないで下さい。私なら別にかまいません。」
「ありがとう。本当なら僕のほうから言うべきなのに。まったくなさけない話しだ。」
「転任するのもそのため。」
「ああ。そうだよ。」
「先生。やめないで下さい。私なら本当にかまわないんです。」
彼女の口調は真剣になった。
「ありがとう。でも君かよくても僕がだめなんだ。こんな性格で女子校の教師をするべきではないよ。」
「そんなこと絶対にありません。先生ほどいい先生めったにいません。授業は誰がきいてもわかるように丁寧に教えてくださるし。とってもやさしいし。」
「ありがとう。僕だってできることならこの学校でつづけたいさ。でもやっぱりやめるべきだ。僕自身苦しいしね。僕のこの変な癖は昔っからだった。たぶん一生なおらないと思う。ここにいれば悩みつづけるだけにきまっている。だから転任すると決めたんだ。」
精神浄化作用が心の重荷を解いた。
玲子はうつむいて考え込んだ。今度は自分が何か言う番だと思った。
窓からさしこむ西日か玲子の頬を照らした。が、しばしの後、行雲によって遮られた。
時計の音は以前のように大きくなってこなかった。むしろ二人の間で時間が止まっているかのようだった。突然、玲子はパッと顔を上げた。
「先生。もしよければ私を拷問してください。そうすればきっと先生の気持ちもはれるわ。でもヘビだけはゆるしてくださいね。」
山武は驚きのあまりしばし呆然と玲子をみつめた。山武が玲子の顔をはっきり見たのはこれがはじめてだった。その目はとても澄んでいた。一瞬山武は我を忘れて玲子の目を見た。だが次の瞬間、頬のあたりから起こってきた羞恥の念が山武の意識を現実に戻した。
「できないよ。そんなこと。絶対に。それに現実に君を拷問にかけたいと言う気持ちはないような気がするんだ。」
「それって空想サディズムね。」
「ああ、そうだね。」
ちょっぴり投げやりな口調で言う。山武が心のすべてを語ってくれたことが玲子に安心感をもたらした。同時に玲子の心にちょっぴり、(いや、かなり)いたずらな気持ちが起こった。
「先生、やめないで。やめたらみんなに先生が変態だって必ずいいふらしますから。」
玲子は子供っぽい口調で言った。山武はおそれで顔が真っ青になった。
「ずるいよ。さっき誰にもいわないっていったじゃないか。」
山武はおおあわてに言った。
「女心は秋の空っていうじゃない。」
そういって玲子は両手で頬杖をついて笑った。
「お願いだからそれだけはやめてくれ。そんなことされたら僕はもう生きてられないよ。」その哀願は真剣そのものだった。玲子はますますうれしくなった。それは生殺与奪の権を手にした人間が感ぜずにはいられない至福の喜びだった。
「そうね…・じゃ考えとくわ。先生が学校をやめないでくれるんなら絶対だれにもいわないわ。」
「そ、そんな…・」
その声は蚊の鳴くほど弱かった。玲子は手を打った。
「そうだわ。私が3年に進級するまではやめないで。だってあと半年じゃない。そうすれば絶対誰にも言わないわ。」
山武はぐったりうなだれていた。自分がばかなことを言ってしまったとつくづく後悔した。しかし心の片隅に、あえて言ってよかったという気持ちもかすかではあるが確かにあった。
山武は大きくため息をついて顔を上げ、玲子をみた。ふたたび雲間からあらわれた西日が玲子の顔を照らした。玲子は無邪気な笑顔で笑っている。その無邪気さに一点のくもりもないのを感じると山武の心の中にあった、あえていってよかったというかすかな気持ちは徐々に大きくなっていった。山武は言った。
「わかったよ。そうするよ。」
そういって山武は大きく一呼吸して窓の外をみた。何度もみなれたつまらない田園の風景がはじめてみた景色ほどに新鮮に感じられた。山武は玲子に再び顔を向けていった。
「なんだかとてもすっきりしたよ。もう一度この学校でやってみようと言う気持ちが起こってきたよ。君のおかげだよ。ははは。変な話だな。教師が生徒に立ち直らされるなんて。」
山武は苦笑した。
「そんなことありませんわ。老いては子に従え、というじゃありませんか。」
「老いては、はひどいな。ぼくはまだ23だよ。」
「それより先生、もう辞表をだしてしまったんでしょ。どうするんですか。」
「それは撤回してもらうようたのんでみるよ。」
やっと一段落した気持ちになった。窓の外には一番星が見える。
秋は日がくれるのがはやい。山武は立ち上がってカーテンをしめ、電気をつけた。
再び玲子と向かい合わせに座った。
「先生、本当にやめないんでくれるんですね。」
「ああ。」
「あしたからまたきてくれるんですね。」
「ああ、いくよ。」
「よかった。これでまた先生のわかりやすい授業がきけるわ。」
と胸に手を当てて半ば独り言のように言う。
「せっかく先生のうちに来たんだから」
と言って玲子は思い出したようにカバンから教科書をとりだした。
「わからないところがあるんです。教えてください。」
と言って玲子は山武の隣にきて教科書のあるページを開いた。
「ああ、いいよ。」
といって山武は玲子のさしだした英語の教科書に少し顔を近づけた。
「ここがわからないんです。」
と言って玲子はあるセンテンスを指した。そこはまだ授業では教えていないところだった。だが勉強熱心な玲子はかなり先まで予習しているらしい。
「えーと、ここのherのとこです。」
「これは前文のa ship(船)のことだよ。英語の名詞はほとんど中性というか無性だ
けど船は例外で女性名詞なんだ。フランス語ではすべての物事に性別があるんだけどね。」
「わかりました。じゃ、ここはどうなんてすか。」
と言って玲子は別のページのセンテンスを指した。
「ああ、これは強調構文だよ。Itとthatの間のin self-sacrificeがthat以下のクロー
ズの副詞句になっているんだよ。」
「わかりました。じゃここはどう訳すんですか。」
と言って玲子は別のページを開いた。そして山武の体にほとんどふれんばかりに近づいた。玲子のストレートの長い黒髪から石鹸のような匂いが伝わってきた。
山武はここにいたってはじめて一つの重大なことに気がついた。それは自分が女性とこれほど近づいて話しをしたことなど一度もないということである。さらに山武はもっと重大なことに気がついた。それは今のこの状況がとてもあぶないということである。閉鎖された密室に男と女か肌がふれんばかりに近づいているのである。山武は心臓の鼓動がだんだん早くなってゆくのに気がついた。顔はだんだん赤くなっていった。同時に山武は自分の下腹部に血流が増加しはじめているのに気がついた。山武はあわててそれを玲子に気づかれないよう腰を少し引いた。山武は必死になってそこへの血流をいかせないようにした。だがそれは意志の力でコントロールできるものではなかった。心拍数の増加も同じであった。それは山武の必死の意志の制止をうらぎり指数関数的に上昇していった。山武が玲子の質問に答えないので玲子は山武の方にふりむいて、
「これはどう訳すんですか。」
と再び聞いた。玲子がもろに山武に顔を向けたことが致命傷を与えた。
「こ、これは…」山武の言葉はひどく震えていた。彼はもうその先を言うことができなかった。これ以上少しでも何かしゃべれば玲子に今の自分の苦境を悟られてしまう。だが答えないわけにはいかない。だが何かしゃべればその震えた口調から今の自分の心境を気づかれてしまう。まさにどうしようもない状況である。頭はますます混乱し、心拍数はますます高まる。
「どうしたんですか。先生。」
答えてくれない山武にしびれをきらした玲子が山武のほうに再び顔を向けて聞いた。だが山武は答えられない。うつむいて真っ赤になっている山武をみて玲子は山武の心を察し、うれしくなった。同時に山武をからかってみようといういたずらな気持ちが起こった。
「先生。何を真っ赤になっているの。」
わざとおちつきはらって丁寧な口調で言う。
山武は答えられない。うつむいたまま頬を紅潮させている。そんな山武をみて玲子のいたずらな気持ちはますます大きくなった。玲子はいきなり山武の手をにぎった。ふるえている。
「な、なにをするんだ。」
山武は声を震わせていった。
「先生、いやらしいこと考えていたでしょ。」
「ば、ばかな。そんなことはないよ。」
「じゃ何で声が震えているの。」
山武は答えられない。玲子の山武をからかいたい欲求は頂点にたっした。
「せえ~んせえ~。」
玲子はめいっぱい、あまい声で言って山武の肩に頭をのせてきた。そして目を閉じた。
山武の心臓は、はちきれんばかりにその拍出量を増した。
「な、なにをするんだ、根木君。」
山武は声を震わせていった。
普通良識のある教師だったら、こういう時、「ばかなまねはやめたまえ。」と言って、彼女をひきはなすであろう。だが小心な山武には、それができないのである。
なぜかというと、一般に女性の方から男に声をかけてきた場合、それをことわることは女性に大変恥をかかせることになる。すぐに彼女をつきはなしてしまっては彼女に恥をかかせることになる。それがこわくて山武は玲子の手をふりほどくことができないのである。
それは山武の本心である。だがそれを大義名分に山武は、確かに、感じてはならないものを、いけないと思いつつ感じていた。
頬にふれる清潔な石鹸のような匂いがする黒髪を…。
肩から伝わってくるふくらみを…。
その谷間から伝わってくる心臓の鼓動を…。
山武の心は、極楽の蓮台の上で身を寄せ合っている佐助と春琴の心境に近かった。
山武の本能は求めていた。
できることならいつまでもこうしていられたら・・・。
だが山武の理性はそれを激しく否定していた。
(こんな状態をみとめることは教師のモラルに反する。)
山武の超自我は山武にそう強く訴えていた。
「や、やめたまえ。根木君。」
山武は声を震わせていった。
玲子に恥をかかせることのできない山武にできる唯一のことは、言葉による制止だけであった。だが玲子は山武の言葉など聞く耳をもたぬかのごとく、うっとりと、柔らかい笑顔で目をつむったまま、手を離そうとしない。
「先生。」
玲子はあまい声で言った。
「好きにしてもいいわよ。」
山武は一瞬、心臓が破裂して死ぬかと思った。全身がカタカタと小刻みに震えてきた。 「な、なにをばかなことをいうんだ。」
すぐさま言うが玲子は聞く耳を持つそぶりもみせない。
「私を拷問にかけたいんでしょ。かけてもいいわよ。」
山武の心臓は破裂するかと思うくらいその拍出量を増した。
「そんなことできるわけがないじゃないか。それにさっきも言ったように現実に君を拷問にかけたいという気持ちなんかないんだよ。ほんとうだよ。」
玲子は何も言わない。うっとりと柔らかい笑顔で目をつむっている。
「とにかくこんなことしててはいけないよ。」
そう言って山武は玲子の手をほどき、彼女をひきはなした。
玲子が体を寄せてきてからかなりの時間がたっていたので、これならもう玲子に恥をかかせないですんだことになると思ったからだ。だが山武の本心を言えば、ちょっぴり(いや、かなり、いや、相当)残念ではあったが…・。
引き離された玲子は笑顔で山武をみている。山武はやっと極度の緊張感から開放されて、ほっとした。山武の心拍数は徐々に平常値にもどっていった。玲子は立ち上がって山武と向かい合わせに座った。玲子はしばし、うれしそうな顔をして山武をみていたが突然、
「先生、恋人いる?」
と聞いた。
「…・。」
「どうなんです?」
「い、いないよ。」
山武はうつむいて答えた。
「イナイ歴何年?」
山武の心に(そんな質問に答えなきゃならない義務はないよ)と言いたい衝動が起こったが、小心な山武は玲子を前にして彼女に何か聞かれると正直に答えなくてはならない義務感のようなものが起こってしまうのだ。それでうつむいて「23年。」と正直に答えた。
「じゃ、いままで一度も恋人をもったことがないんですね。」
玲子はものすごくうれしそうな顔をしている。
「恋をしたことはあるんですか。」
玲子はさらに追い討ちをかける。これにはさすがの山武も少しいらだって、
「そこまで答える義務はないよ。」
と言った。 玲子はうれしそうな顔をして、
「先生。なにかの本で読みましたが、禁欲的な精神状態があまりに嵩じすぎると倒錯し
た感情が起こると書いてありましたよ。」
山武自身そのことは知っていた。そして自分の精神状態がまさにそれであることも…・。
「先生。私のこときらい?」
「な、何を言うんだ。やぶからぼうに。」
「どうなんです。きらいなんですか。」
玲子は即座に追い討ちをかける。
「き、きらいじゃないよ。」
「じゃ、好き?」
(そんな子供じみた質問に、)と、つい思ったが、自分自身に、短気をおこすな、と叱咤して、
「生徒に個人的な感情をもつことは教師のモラルに反することだよ。だが一生徒として
はもちろん好きさ。」
玲子はあいかわらず、うれしそうな顔で山武をみつめていたが突然、
「私が先生の恋人になってあげるわ。どう?私じゃいや?」
と聞いた。狼狽した山武だったが、すぐに、
「だめだよ。そんなこと教師のモラルがゆるさないよ。」
玲子は山武のあまりに融通のきかなさにいささかじれったくなって、
「じゃ今度いつか一回でいいですから、どこかでデートしません?」
「だめだよ。それもモラルに反するよ。」
「もう、モラル、モラルって、かたっくるしいんですね。」
玲子はいらだたしげに言った。
山武はうつむいて「ごめん。」と言った。一瞬の間を置いて、玲子にふと面白い口実がおもいついた。
(これなら山武の律儀さを逆に利用できる)
と思ってうれしくなった。
「一日でいいからデートしましょう。だって今まで私を無視しつづけてきて、私を悩ま
してきたんだもの。その謝罪としてなら先生の心のバランスもたもてるんじゃなくて…。」
山武はしばし考えた後、
「わかったよ。デートするよ。ただし一回だけだよ。こんなことが学校にしれたらたいへんだからね。君も僕も身の破滅だよ。」
「うれしい。じゃ、どこにしようかなー。」
玲子は頬杖をついて天井をみながらしばし考えた。
「そうね。じゃ今度の日曜日。渋谷で。ブティックで洋服買って…。前からほしいと思っていた服があるの。それから他にもほしいものいろいろあるの。そのあとスカイラウンジでフランス料理食べて…・。もちろん費用は全部先生持ちで…。どう?」
「わかったよ。それで謝罪になるならそうするよ。ただし一回だけだよ。こんなことが学校にしれたら身の破滅だからね。」
もう、外は暗くなっていた。
秋の日はつるべ落としである。
もう7時になっていた。
「もう、こんな時間だから帰ったほうがいい。」
玲子は「はい。」と言って、教科書をかばんにしまった。そして、立ち上がって、玄関にむかった。彼女は靴をはいてから、ふりかえり、
「先生。あした必ず学校にきてくださいね。」
「ああ、必ず行くよ。」
「絶対ですよ。こなかったら先生の秘密いいふらしちゃいますからね。」
山武は一瞬、ギョッとして、顔から血の気が引いた。
「いくよ。必ずいくから、それだけはお願いだからいわないで。」
玲子は一瞬、「いまのはジョークですよ。」と言おうかと思ったが、やっぱり、それはやめにした。多少、非常なようでも言わないでいるほうが山武を確実に学校に来させることができると思ったからだ。それで、つつましい口調で、
「先生。今日はどうもありがとうございました。私の勝手な頼みをきいてくださって。
それに勉強もおしえていただいて。」と言って、ペコリと頭をさげた。
山武は内心ほっとして、
「僕の方こそ君にお礼をいわなくっちゃ。またあの学校で教師をつづけようと思うことができたのは君のおかげだよ。」
玲子は再びペコリと頭をさげてから階段を降りていった。
☆ ☆ ☆
玲子を見送ってからドアを閉めると山武は再び机の前に腰をおろした。
山武はしばしの間、我を忘れて、呆然としていた。山武の頭は、まるでるめまぐるしく進行する映画をみたような状態だった。実際、副交感神経優位型の山武にとって、これほど神経の酷使を要求された経験は生まれて一度もなかった。山武の頭はしばしの間、空白状態だった。
だが時間の経過が徐々に山武の意識を現実にもどしはじめていた。山武は無意識のうちに、玲子に対して心のすべてをあかしてしまったことが、はたして本当によかったのかどうか考えだしていた。再び、「やっぱりゆわないほうがよかったのでは。」という考えがあらわれだした。だが、玲子の悩みを解いてやったのだし、再びあの学校で教師をつづけようという決意がもてたのだし、やっばり言ってよかったのだという考えも心の一方にあった。30分ほど、その葛藤が山武を悩ませつづけた。
ポツポツと窓ガラスを打つ音が聞こえ出した。小雨がふりだした。
結局、山武はやっぱり、言ってよかったのだという結論に達した。心のそこからそう思ったのではなく、無理にそう思い込もうとしたのだった。それで気をまぎらわそうと明日の授業の予習をはじめた。山武は書棚から教科書とノートをとり、机に向かった。明日おしえるところは関係代名詞である。わかりにくい授業というのは教師が、わかっている自分を基準にして教えるからわからないのだ。もっと生徒の立場に立ってわかりやすくおしえなければ…・。
「えーと。関係代名詞とはそもそも先行詞とそれを形容する形容詞節をつなぐ代名詞であって、先行詞はその形容詞節の中で、関係代名詞がwhoであれば主格、whomであれば目的格、whoseであれば所有格としてはたらき…。」
(だめだ。だめだ。こんな説明の仕方じゃわかってもらえない。もっとわかりやすく説明しなければ…・。)
それから30分近く、山武は関係代名詞の説明の仕方を考えた。だがどうもうまい説明の仕方が思いつかない。すると再び心の奥にしまいこんた玲子のことが気になりだした。
「やっぱりいわない方がよかったのでは。」という否定論が生まれ出した。そしてそれは加速度的に大きくなり、小心な山武を悩ませ出した。
「よく考えてみれば、ばかなことをいってしまったものだ。何で心のすべてを言ってしまったのだろう。なにも、いわなくてはならない義務などないのだ。」
そう考え出すと山武の心は否定論一辺倒になってしまった。山武は茶を飲みながら、冷静になろうと考え、もう一度何で自分が玲子に心を開いてしまったかを考えてみた。
「彼女に心を開いたのは彼女が真摯な態度で悩みを打ち明けてきたからだ。生徒の深刻な悩みに応じるのは教師の責任だからだと思ったからだ。ましてや自分が生徒を悩ましてるのであればなおさらだ。」
そう思うと山武の心に再びいってよかったという気持ちが起こってきた。そう思うと山武は急にうれしくなって、歌でもうたいだしたい気分になった。外ではあいかわらず小刻みに小雨が窓ガラスをたたいている。山武は再び関係代名詞の説明の仕方にとりくんだ。だがどうもうまい説明の仕方が思いつかない。髪をかきむしり、呻吟して考えた。一時間ほど経った。するとまた一つのことが気になりだした。それは、彼女が誰にもいわないでくれるだろうか、ということだった。彼女ひとりが知っているならまだいい。だが玲子が誰かにしゃべってしまったら。そして、それが口から口へと学校中の生徒達に知れ渡ってしまったら。そう考えると山武はいてもたってもいられなくなった。彼女はしゃべらないでくれるだろうか。絶対しゃべらないとさっきは約束してくれた。あの子は誠実な子だから、もしかしたらしゃべらないでくれるかもしれない。だが彼女は友達も多く、友達と愉快におしゃべりするのが三度の食事より好きな子だ。そう考えると山武は気もそぞろになり、血の気の引いた顔を両手で覆った。おれはなんてばかなことをしてしまったのだ。彼女は今日のことは一生忘れないだろう。彼女が一生秘密を守ってくれるなんてまず無理だ。きっといつかなにかのひょうしにいってしまうだろう。
おれは一生彼女のきまぐれにおひえて生きなければならない。気の小さい人間の考えというものはひとたび否定的になるとそれは雪の坂道から雪だるまをころがすようにとめどもなく大きくなっていくものである。もしかすると彼女はもうすでに携帯電話で友達に今日のことを自慢げにはなしてしまっているかもしれない。そんな考えまでも起こってきた。あした学校にいくと玲子に約束したけれどやっぱりやめようか。学校も転任しようか。山武は一瞬本気でそう思った。だがすぐにそれはゆるされなことに気づいた。あした学校にこなければみんなにいいふらすといったからだ。(玲子にしてみればこれは冗談でいったつもりだったが小心な山武にはそれがわからないのである)
「ともかくあした学校へいかなくては…。」
山武はそのため、再び、関係代名詞の説明の仕方を考えようと思って教科書を手にとった。だが混乱した頭には、とてもそんなことを落ち着いて考えるゆとりはなかった。
山武は(もうどうとでもなれ)という捨て鉢な気持ちになって、ポテトチップスとポカリスエットをもってきて、テレビのスイッチを入れた。酒が飲める人ならこういう時、やけ酒を飲むのだろうが山武は酒が飲めない。
テレビではボクシングの日本バンタム級タイトルマッチが始まるところだった。放送席にはゲスト解説者として、元ライト級世界チャンピオンがいた。
「挑戦者はどういった戦術でチャンピオンに対抗したらいいのでしょうか。」とのアナウンサーの質問に対し、ゲストの元世界チャンピオンは、
「チャンピオンは持久戦に強いです。一方、挑戦者のA君はスタミナの点でやや劣りますが、インファイトを得意とする速戦型です。ですから第一ラウンドから一気に攻めるべきでしょうね。それが唯一の勝機をつかむ方法ですよ。」
と自信に満ちた解説をした。それをセコンドが聞いていたのか、実際、試合が始まると挑戦者は第一ラウンドから一気に攻めた。すると第二ラウンドでチャンピオンのカウンターパンチが挑戦者にきれいにきまった。それが起点となって勝敗の趨勢は一気にチャンピオンの側へ傾いた。第二ラウンドの終わりには挑戦者はもう足にきていた。そして第三ラウンドで挑戦者はチャンピオンの連打をうけ、ダウンし、あっけなくK・Oで勝負がついた。
「敗因はいったい何だったのでしょうか。」
とのアナウンサーの質問に対し、ゲストの元世界チャンピオンは、
「いやーA君はスタミナの配分を考えなかったのがまずかったですね。それが最大の敗因とみてまず間違いないでしょう。」
としみじみした口調で語った。山武はこの元世界チャンピオンは現役時代、パンチをくいすぎてパンチドランカーになってしまったのだと確信した。山武はチャンネルをかえた。プロレス中継をしていた。ジュニアヘビー級の試合で、メキシコの空中殺法を得意とする覆面レスラーと蹴りのうまい日本のレスラーとの対戦だった。ヘビー級ではみられない、スピーディーな試合だった。山武は覆面レスラーをみてふと思った。
覆面・・・・正体を知られない・・・・うらやましい・・・・あした・・・・ふくめんをしていこうか・・・・そのためには・・・・今からふくめんを縫わねば・・・・先生が・・・・よなべーをして・・・・ふくめーん編んでくれた・・・・などとばかげたことを考えていた。プロレス中継は三十分ほどでおわった。時計をみるともう一時をまわっていた。あした遅刻してはみっともない。山武はもう寝ようと思って、机をかたずけて、蒲団をしいた。そして歯をみがいてから、10回口をゆすいで、寝間着に着替え、床についた。山武は蒲団の中で、えびのようにちぢこまって、どうか玲子が一生しゃべらないでください、とゲッセマネのキリスト以上の敬虔さをもって心の底からいのった。窓の外では、あいかわらず雨が屋根を叩いている。山武は枕元に置いてある数冊の本の中から「図太い神経になるには」という本をとって、パラパラとめくって読んだ。山武は小心な自分の性格をかえたくて、以前にこれを買って読んだのだが、本をよんだからといって性格はかわるものではない、とつくづく思った。そうこうしているうちにやがて睡魔がおとずれて、山武の意識は徐々にうすれていった。山武の精神は山武にとってもっとも安楽で平和な世界へ入っていった。
☆ ☆ ☆
翌日は雨はやんでいたが、あいかわらず降り出しそうなくもり空だった。降水確率は五十パーセントとテレビの天気予報は言った。彼女はもうきのう、みんなに電話をかけまくって、みんなおれの恥を知っているにちがいない。ペシミストの山武はもう、そう確信していた。だが鏡の前でネクタイをしめながら、山武は心の中で決死の覚悟をした。
しっかりしろ。世の中にはもっとつらい恥に耐えて生きている人間もかぞえきれないほどいるじゃないか。なにも死刑になるわけじゃなし…・。
トーストとコーヒーの軽い朝食をすませたのち、七時半に、意を決し、アパートをでた。学校へは四日ぶりである。精神が高ぶっているため、いつもの景色がはじめてみるように新鮮に感じられる。駅までの道で、山武はこの日、この前まではまったく気がつかなかった、路傍の一輪の青紫色の桔梗の存在に気づいた。通勤電車はあいかわらず、すしづめだった。
駅を降りて、学校に近づくにつれ、生徒達の姿がちらほらみえだした。山武の心に再びためらいの気持ちが起こった。
躊躇する気持ちが山武を立ちどまらせた。
その時、
(キキー!!)
自転車の止まる音が背後に聞こえた。山武はうしろからポンと肩をたたかれた。
山武がふり返ると玲子がいた。
「おっはよ。先生。」
その笑顔は昨日のことなどまるで忘れているかのようだった。
「や、やあ。お、おはよう。」
山武はひきつったような無理につくった笑顔でこたえた。だがその顔は今にもなきそう
なほど弱々しかった。玲子は刹那に山武の今の心をみぬいた。同時に、やさしさがおこってきた。
「きのうのこと、まだ誰にもいってないよ。一生誰にもいわないよ。だから学校やめな
いでね。今度の日曜デートしよ。」
そう言って玲子はペダルを力強くこいでいった。
この一言は山武の悩みを瞬時にして完全に取り去った。
きのう一晩悩んだことは、まったくの取り越し苦労だったのだ。
山武の心に今まで一度も経験したことのないほどのよろこびがわきあがってきた。
この学校でもう一度やろう。やっていける。という自信と、そのよろこびが胸の奥深く
からはちきれんばかりにわきあがってきた。
刹那の手持ちぶさたが山武の顔を空へ向けさせた。
かわりやすい秋の空ではいつしか雲間から日がさしはじめていた。