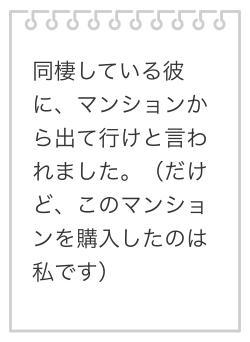今日もだれかのベッドの上で
「悪いな千鶴。こういう事だ。別れてくれ」
悪いなと口にするけれど、悪びれた様子が一切ない彼の謝罪に、千鶴は唖然となった。
それは、長年の彼女に言うセリフだろうか?
別れを切り出すにしても、隣に女を連れてだなんて最低だ。千鶴は怒りか悲しみか分からない感情で、段々と鼻がツンとなるのを感じた。
だが、泣くのはまだ早い。
ここで泣いては女が廃る。
千鶴は唇をギリッと噛み締め、なけなしの意地をここで見せた。
「浮気する男なんて、こっちから願い下げよ。こんな所、二度と来ないわ!!」
千鶴は肩から下げていた鞄から隆弘のアパートの合鍵を出すと、彼目掛けて投げ付けた。
「いってぇ!」
頬を叩いた訳じゃないし、顔に当たった訳じゃない。こんな状況でも、自制心が働きそんな力一杯投げ付けたつもりもない。
だが、隆弘は大袈裟に痛がって見せたのだ。
「やだぁ、隆弘ぉ大丈夫!?」
すかさず、名も知らない浮気女が当たってもいない隆弘の頬を、優しく撫でていた。
「暴力女が!」
「警察呼んじゃう?」
すでに踵を返した千鶴の背に、隆弘達のやり取りが聞こえたが、千鶴は無視して部屋から出て行くのだった。
警察なんて、どうせ呼ばないのは分かっている。たとえ呼んだとしても、事情を話せば事件にはならないだろう。イイとこ痴話喧嘩だ。
もし訴えるなら、浮気した事を逆に訴えてやればいい。千鶴は重い荷物を反対側の肩に持ち直し、帰路に着くのであった。
◇ ◇ ◇
彼と初めて出会ったのはいつだったか、千鶴には遠い記憶のようでハッキリと思い出せない。
ーーそうだ。
高校二年の夏休み。
隆弘の友達が千鶴の友達と付き合っていて、何故かダブルデートするハメになったんだった。
そこから、なんとなく会う回数が増えて、大学生になり一人暮らしを始めた隆弘の家に行き来する仲になって……自然と。
「あ、ハルクのCD置きっぱだった」
先週買ったばかりで、自分はまだ聴いてない事に気付いた。
「貸したお金も返してもらってないじゃん」
月末で金がないからと、五千円貸したままだった。
「まぁ、いいか」
三万貸してと言われた時、渋って良かったと思う。
返せと言って素直に返してくれそうもない。ましてや、借用書なんて書いてもらってない。隆弘の事だから、知らぬ存ぜぬで終わりそうだ。
しかし、連れていた彼女は可愛い系だったなと思った。
ヒラヒラしたワンピースに、ゆるふわに巻いた髪としっかりした化粧。爪はネイルアートをしていて、とても綺麗だった。
自分の爪は二人分の家事でボロボロ。化粧は隆弘の部屋を汚すといけないからと、薄めの化粧だ。
忙しさにかまけて、美容院なんてしばらく行ってないし、このまま何となく結婚するかなと思っていたので、貯蓄に回して服や靴も買ってなかった。
冷静に考えたら、あの子の方が断然可愛いなと思った。
だけど、あの勝ち誇った顔と、隆弘の言動は許せない。
「あぁぁ〜っ。雨まで降って来るなんて最悪」
ポツポツと肩や頬に落ちてくる水は、決して雨だけではなかった。
頬を伝う水は、空から落ちて来る水より温かく、ほんのり塩辛い。
隆弘が浮気女を連れていなかったら、千鶴はきっと泣いていたかもしれない。
(どうしてよ!!)
縋るつもりはなかったが、理由だけは訊きたかった。
食事や洗濯、掃除まで仕事の合間に来てはせっせと、世話をしたつもりだ。だけど、やり過ぎも良くないと聞いた事がある。
甲斐甲斐しくやっていた千鶴は、いつからか隆弘の彼女ではなくなり、家政婦か母みたいな存在になっていたのかもしれない。
「よし、今日はやけ酒だ!」
たまたま見かけたお酒の自販機に、千鶴は足を止めた。
やけ酒だなんて言っても、缶ビール半分でベロベロに酔う千鶴。頭も痛くなるのだから、酒との相性は悪いのだろう。
しかし、今はそんなのは気にしない。
一度はやってみたかった路上歩き飲みをしてやる。雨も降り始めて人もまばら、ひと目なんか気にしないで千鶴は自販機で小さな缶ビールを買った。
「明日に向かってかんぱ〜い!」
元よりウジウジしないように心掛けている千鶴は、空に向かって缶ビールを掲げた。
今日の事は今日で終わらせてやる。明日に持ち越すなんてバカらしい。
「明日は休みだ。ゆっくりしてやるぞ!」
もう面倒な家事を一切やらなくて済むと思えば、少し心が楽になる気がした。今まで無駄に過ごした時間をこれからは、自分に費やせばいい。
可愛い服に靴や鞄。化粧だって思いっきりしてやる。
そうだ、明日は美容院に行こう!
「フラれてバンザーイ!」
ポジティブに考えた千鶴は、あっという間に缶ビールを開けたのだった。
◇ ◇ ◇
「うぅ、頭が痛い」
いつアパートに戻ったかさえ記憶にない千鶴は、布団からモゾモゾと這い上がっていた。
しかし、何故だかいつもよりふわりとした感触の毛布に、いつもより高さのある枕。
思わず鼻をスンとすれば、千鶴の知らない男の香りがした。
「え゛?」
ズキズキと痛んでいたハズの頭が、一気に鎮まると同時にヒュッと冷えた。
知らない柄の枕カバーに、知らない色の毛布が目に入ったのだ。
「え? ぇ?」
最近変えた覚えなどなく、恐る恐るベッドから部屋を見渡せば、そこはまったく見た事がない知らない部屋だった。
「やっと起きたのかよ?」
何事か分からない千鶴の頭上に、聞いた事のない男の人の声が降って来た。
(ど、ど、ど、どういう……)
怖くて顔を上げないでいたら、千鶴の目の前に隆弘が持っていないメーカーの黒いスラックスが見えた。
(というか、ここは私の家でも隆弘の家でもない!!)
酔っていたハズの千鶴の頭は、完全に覚醒した。
酔った勢いでとはよくある話として聞くが、まさか自分が!? と千鶴は思わず身なりをチェックする。
ーードス。
「どアホ」
身なりをチェックしていた千鶴の頭上に、呆れ交じりの失笑と手刀が落ちてきた。
痛みに現実だと悟り、身なりも寝た時以外の乱れはなかった。
襲った訳でも襲われた訳でもない様だ。
だが、ここにいる事情が怖くて聞けない千鶴は、まだ顔を上げられない。
「飯食うか?」
「え?」
どうしようと頭の中はグルグルと、身体はビクビクとしていた千鶴に、男はそう声を掛けてきたのだ。
想定外の言葉に、千鶴は思わず顔を上げた。
「晩飯、まだだろう?」
(まだだけど、何故それを知っているの?)
そんな疑問が頭の隅を過ぎったが、キッチンに立つ男の人に見惚れてしまった。
歳は30代前後の彼は、白い半袖Tシャツに、黒いスラックスというラフな格好だが、半袖から見える腕が隆弘なんかよりも、はるかにガッシリしていた。
太くもなく細くもない鍛えた腕。だらしなく履いているハズのスラックスが、何故かわざと緩く着るモデルの様に見えた。
何より、千鶴が今まで見てきた男の人の中で、断トツで美形だ。ただ立っているだけで、絵になるほどに。
しかも、邪魔な前髪を掻き上げ、振り向いた姿がやけに色っぽい。
「顔を洗いたいなら、洗面所は……って分かるか」
そう言って笑ったその声と表情が、千鶴の心にキュンときた。
さっきフラれたばかりなのに、胸は異様な速さで鼓動を打つ。隆弘にも感じた事のない動機がしてきて、思わず胸を押さえていた。
「聞いてんのかよ?」
再び掛かった声に、千鶴の頬は酔いが振り返した様にボボッと熱くなる。
「き、き、聞いてるとかいないとか!」
「は? いいから、頭も冷やして来い」
よく分からない返答をした千鶴に、男はバスルームを指した。
どうやら、まだパニック状態だと判断した様である。
「はい!!」
とっさに、とりあえずイイ返事を口にし、千鶴はバスルームへと走ったのだった。
(あ……れ?)
洗面所も兼ねているバスルームに立った千鶴は、パシャパシャと顔を洗っていてはたと何かに気付いた。
そういえば、どこか見覚えがある景色な気がするのだ。
ゆっくり音を立てずにバスルームから覗けば、今通って来た場所が廊下を兼ねた細いキッチン。そして奥には、自分がさっきまで寝ていた部屋がある。
よくある1Kの間取りだ。だが、しかしである。
千鶴のよく知る間取りとソックリ……というかそのもの。置いてある家具や配置はまったく違うが、備え付けの冷蔵庫はまったく同じ。
「えっと?」
(ここはどこ?)
と訊こうとしたら、フェイスタオルが顔に飛んで来た。
「ベッドの下に折り畳みのテーブルがあるから、出しとけ」
「あ、はい」
慣れた手つきで料理をする彼をチラッと見つつ、千鶴は奥の部屋に向かった。
本来なら手伝うのが一番だろうが、勝手も知らないし彼の手際が良過ぎて自分が邪魔になりそうだ。
そして、何より、部屋をもう一度確認したかったのである。
奥の部屋は、自分と同じ八畳程。窓が広いので、ベッドは自然と壁際になる。それに合わせた家具の配置になるので、自分と似たような部屋になるのかもしれない。
千鶴は見渡しながらガタガタと、ベッドの下から折り畳みテーブルを出した。
(なるほど、ここにテーブルをしまうのはアリだな)
こんな訳の分からない状態なのに、彼の部屋にある物の置き方に頷いていた。
ベッドの下に服をしまっている千鶴とは、使い方が違って面白いし勉強になっていたのだ。
「あんたの部屋と変わんねぇだろうが」
もはや晩飯を通り越して夜食の様な料理を、まったく知らない男……いや、彼が作って来てくれた。
キョロキョロとしている千鶴にため息を吐いていたけど。
「今さらですけど、ここはどこ?」
テーブルに置かれた料理に目を奪われつつ、千鶴は今一番知りたい事を訊けば、彼は千鶴にクッションを渡しながら答えくれた。
「203」
「え?」
「と な り」
そう言って彼は、何も敷いてない床にドカリと座った。
(となり、となり、となり!?)
「お隣りーーっ!?」
千鶴は思わず叫んでしまった。
道理で見たような部屋なハズだ。隣なら間取りは一緒だし、備え付けの冷蔵庫もあるに決まっている。
「大変申し訳ございません!!」
普段飲まない酒に飲まれた千鶴は、間違って隣の部屋に入っていたらしい。
そう気付いた千鶴は、クッションから降りて土下座した。
「まぁ、鍵を掛けなかった俺も悪……くはねぇが、冷めねぇ内に食え」
自分も悪いと言おうとしてやめた彼。
近くのコンビニだからと、鍵を掛けなかった自分がと思った様だが、確認せず部屋に入った上に、ベッドで寝た千鶴の方が悪いのでは? と考え直したらしい。
「いえ、あの」
「いいから食えよ」
折角作ったのだからと、彼は千鶴に箸を渡した。
テーブルに載っていたのは、炊き立てのご飯にきゅうりの糠漬け。後は卵が入っている温かいコンソメスープだった。
お酒を飲んでいた千鶴には、ちょうどいい量だが……何故コンソメスープ? と首を傾げたくなってしまった。
「悪いな。味噌を買い忘れてないんだよ」
「ふふっ。すごく美味しいです」
だからコンソメスープなのかと、千鶴は小さく笑った。
確かにこのラインナップなら、味噌汁が定番だ。だけど、そんな事が気にならないくらいに、冷え切っていた千鶴の心と身体がゆっくり温まっていった。
「そりゃあ良かったな。だけど、今度からは気をつけろよ? 普通なら襲われて終わりだ」
「はい」
確かにその通りだ。
自分から男の部屋に入り、ベッドで待ち構えた形となっていたのだ。
彼でなければ、今頃ーー
と考え、千鶴は今さらながらブルッと身体が震えた。
「食ったらさっさと帰れよ?」
「え?」
そっけない言葉とは裏腹に、彼の口調は実に優しかった。
「腹が適当に満たされて、目の前に美味しそうなデザートがあれば……食いたくなるのが男の性さがってな?」
要は襲うぞ? と注意してくれているのだ。いや、揶揄っている気もするが。
それを言うなら、その言葉に身の危険を感じ、衝動的に立ち上がりたくなるのが、女の性さがだろう。
だが、そう言った彼の表情がいやらしくなく、誘うような色っぽい姿で千鶴の頬が、酔ったように赤くなっていた。
ーーピン!
「いったぁ!」
「ばぁか。そこで顔を赤らめるんじゃねぇ」
呆れた様な声と共に、向かいに座っている彼は、千鶴のおでこをピンと弾いたのである。
「すみません」
(だって、何だか彼ならイイか……いやいや、何を考えているのかな!?)
千鶴はさらに赤く染まっていく顔を、ブンブンと横に振っていた。
「ご、ご、ごちそうさまでした」
もはや、夜食の味なんか分からなかった。
千鶴の頭は色んな煩悩から逃れるために、必死で戦っていたのである。こんな事は初めてだった。
「お粗末さん」
食器を片付けるついでに、千鶴の頭をクシャリとして行くから、千鶴の頭は先程排除した煩悩がお呼びですかと、カムバックする。
(何、この感じた事のないモヤッとした変な感情は!)
「お皿を洗わせて下さい!!」
(この煩悩ごと!!)
千鶴は彼の後を慌てて追った。
何かしないと気持ちが落ち着かない。とにかく身体を動かしたいと千鶴は立ち上がった。
「皿洗ったら帰れよ?」
(デザートを食べたくなるからですか?)
なんて、恥ずかしくて冗談でも言えない。
「はい」
もはや、千鶴の頭に隆弘の面影などないに等しかった。
慌てて洗うのも変な気がするし、ゆっくり洗うのもおかしい。
でも、洗い終わったら帰らなきゃいけない。頭は帰らなきゃと分かっているが、心はまだここにいたいとざわついていた。
千鶴はさらなる苦行に立たされていたのであった。
「お騒がせ致しました」
結果として、千鶴は理性が勝った。
そもそもフラれたばかりだ。そんな女が、見ず知らずの男の部屋に乱入して、何故かご飯をご馳走になり、身まで任せる訳にはいかない。
そんな軽い女でいたくないと、千鶴の理性が勝利の雄叫びを上げていた。
(そういえば、名前を訊いてなかったな)
そうチラッと思いつつ、自分の荷物を持ってドアから出れば、千鶴の背後から耳にそっと息が掛かった。
「今度来たら、抱くからな?」と。
「な、な、なっ!」
息を吹きかけられた耳を慌てて押さえて振り返れば、彼はドア枠に寄りかかり、手をヒラヒラさせて笑っていた。
「来ませんよ!!」
揶揄われたのだと分かり、千鶴はそう反射的に言ったが……きっと行くような気がする。
そんな予感しかなかった。
悪いなと口にするけれど、悪びれた様子が一切ない彼の謝罪に、千鶴は唖然となった。
それは、長年の彼女に言うセリフだろうか?
別れを切り出すにしても、隣に女を連れてだなんて最低だ。千鶴は怒りか悲しみか分からない感情で、段々と鼻がツンとなるのを感じた。
だが、泣くのはまだ早い。
ここで泣いては女が廃る。
千鶴は唇をギリッと噛み締め、なけなしの意地をここで見せた。
「浮気する男なんて、こっちから願い下げよ。こんな所、二度と来ないわ!!」
千鶴は肩から下げていた鞄から隆弘のアパートの合鍵を出すと、彼目掛けて投げ付けた。
「いってぇ!」
頬を叩いた訳じゃないし、顔に当たった訳じゃない。こんな状況でも、自制心が働きそんな力一杯投げ付けたつもりもない。
だが、隆弘は大袈裟に痛がって見せたのだ。
「やだぁ、隆弘ぉ大丈夫!?」
すかさず、名も知らない浮気女が当たってもいない隆弘の頬を、優しく撫でていた。
「暴力女が!」
「警察呼んじゃう?」
すでに踵を返した千鶴の背に、隆弘達のやり取りが聞こえたが、千鶴は無視して部屋から出て行くのだった。
警察なんて、どうせ呼ばないのは分かっている。たとえ呼んだとしても、事情を話せば事件にはならないだろう。イイとこ痴話喧嘩だ。
もし訴えるなら、浮気した事を逆に訴えてやればいい。千鶴は重い荷物を反対側の肩に持ち直し、帰路に着くのであった。
◇ ◇ ◇
彼と初めて出会ったのはいつだったか、千鶴には遠い記憶のようでハッキリと思い出せない。
ーーそうだ。
高校二年の夏休み。
隆弘の友達が千鶴の友達と付き合っていて、何故かダブルデートするハメになったんだった。
そこから、なんとなく会う回数が増えて、大学生になり一人暮らしを始めた隆弘の家に行き来する仲になって……自然と。
「あ、ハルクのCD置きっぱだった」
先週買ったばかりで、自分はまだ聴いてない事に気付いた。
「貸したお金も返してもらってないじゃん」
月末で金がないからと、五千円貸したままだった。
「まぁ、いいか」
三万貸してと言われた時、渋って良かったと思う。
返せと言って素直に返してくれそうもない。ましてや、借用書なんて書いてもらってない。隆弘の事だから、知らぬ存ぜぬで終わりそうだ。
しかし、連れていた彼女は可愛い系だったなと思った。
ヒラヒラしたワンピースに、ゆるふわに巻いた髪としっかりした化粧。爪はネイルアートをしていて、とても綺麗だった。
自分の爪は二人分の家事でボロボロ。化粧は隆弘の部屋を汚すといけないからと、薄めの化粧だ。
忙しさにかまけて、美容院なんてしばらく行ってないし、このまま何となく結婚するかなと思っていたので、貯蓄に回して服や靴も買ってなかった。
冷静に考えたら、あの子の方が断然可愛いなと思った。
だけど、あの勝ち誇った顔と、隆弘の言動は許せない。
「あぁぁ〜っ。雨まで降って来るなんて最悪」
ポツポツと肩や頬に落ちてくる水は、決して雨だけではなかった。
頬を伝う水は、空から落ちて来る水より温かく、ほんのり塩辛い。
隆弘が浮気女を連れていなかったら、千鶴はきっと泣いていたかもしれない。
(どうしてよ!!)
縋るつもりはなかったが、理由だけは訊きたかった。
食事や洗濯、掃除まで仕事の合間に来てはせっせと、世話をしたつもりだ。だけど、やり過ぎも良くないと聞いた事がある。
甲斐甲斐しくやっていた千鶴は、いつからか隆弘の彼女ではなくなり、家政婦か母みたいな存在になっていたのかもしれない。
「よし、今日はやけ酒だ!」
たまたま見かけたお酒の自販機に、千鶴は足を止めた。
やけ酒だなんて言っても、缶ビール半分でベロベロに酔う千鶴。頭も痛くなるのだから、酒との相性は悪いのだろう。
しかし、今はそんなのは気にしない。
一度はやってみたかった路上歩き飲みをしてやる。雨も降り始めて人もまばら、ひと目なんか気にしないで千鶴は自販機で小さな缶ビールを買った。
「明日に向かってかんぱ〜い!」
元よりウジウジしないように心掛けている千鶴は、空に向かって缶ビールを掲げた。
今日の事は今日で終わらせてやる。明日に持ち越すなんてバカらしい。
「明日は休みだ。ゆっくりしてやるぞ!」
もう面倒な家事を一切やらなくて済むと思えば、少し心が楽になる気がした。今まで無駄に過ごした時間をこれからは、自分に費やせばいい。
可愛い服に靴や鞄。化粧だって思いっきりしてやる。
そうだ、明日は美容院に行こう!
「フラれてバンザーイ!」
ポジティブに考えた千鶴は、あっという間に缶ビールを開けたのだった。
◇ ◇ ◇
「うぅ、頭が痛い」
いつアパートに戻ったかさえ記憶にない千鶴は、布団からモゾモゾと這い上がっていた。
しかし、何故だかいつもよりふわりとした感触の毛布に、いつもより高さのある枕。
思わず鼻をスンとすれば、千鶴の知らない男の香りがした。
「え゛?」
ズキズキと痛んでいたハズの頭が、一気に鎮まると同時にヒュッと冷えた。
知らない柄の枕カバーに、知らない色の毛布が目に入ったのだ。
「え? ぇ?」
最近変えた覚えなどなく、恐る恐るベッドから部屋を見渡せば、そこはまったく見た事がない知らない部屋だった。
「やっと起きたのかよ?」
何事か分からない千鶴の頭上に、聞いた事のない男の人の声が降って来た。
(ど、ど、ど、どういう……)
怖くて顔を上げないでいたら、千鶴の目の前に隆弘が持っていないメーカーの黒いスラックスが見えた。
(というか、ここは私の家でも隆弘の家でもない!!)
酔っていたハズの千鶴の頭は、完全に覚醒した。
酔った勢いでとはよくある話として聞くが、まさか自分が!? と千鶴は思わず身なりをチェックする。
ーードス。
「どアホ」
身なりをチェックしていた千鶴の頭上に、呆れ交じりの失笑と手刀が落ちてきた。
痛みに現実だと悟り、身なりも寝た時以外の乱れはなかった。
襲った訳でも襲われた訳でもない様だ。
だが、ここにいる事情が怖くて聞けない千鶴は、まだ顔を上げられない。
「飯食うか?」
「え?」
どうしようと頭の中はグルグルと、身体はビクビクとしていた千鶴に、男はそう声を掛けてきたのだ。
想定外の言葉に、千鶴は思わず顔を上げた。
「晩飯、まだだろう?」
(まだだけど、何故それを知っているの?)
そんな疑問が頭の隅を過ぎったが、キッチンに立つ男の人に見惚れてしまった。
歳は30代前後の彼は、白い半袖Tシャツに、黒いスラックスというラフな格好だが、半袖から見える腕が隆弘なんかよりも、はるかにガッシリしていた。
太くもなく細くもない鍛えた腕。だらしなく履いているハズのスラックスが、何故かわざと緩く着るモデルの様に見えた。
何より、千鶴が今まで見てきた男の人の中で、断トツで美形だ。ただ立っているだけで、絵になるほどに。
しかも、邪魔な前髪を掻き上げ、振り向いた姿がやけに色っぽい。
「顔を洗いたいなら、洗面所は……って分かるか」
そう言って笑ったその声と表情が、千鶴の心にキュンときた。
さっきフラれたばかりなのに、胸は異様な速さで鼓動を打つ。隆弘にも感じた事のない動機がしてきて、思わず胸を押さえていた。
「聞いてんのかよ?」
再び掛かった声に、千鶴の頬は酔いが振り返した様にボボッと熱くなる。
「き、き、聞いてるとかいないとか!」
「は? いいから、頭も冷やして来い」
よく分からない返答をした千鶴に、男はバスルームを指した。
どうやら、まだパニック状態だと判断した様である。
「はい!!」
とっさに、とりあえずイイ返事を口にし、千鶴はバスルームへと走ったのだった。
(あ……れ?)
洗面所も兼ねているバスルームに立った千鶴は、パシャパシャと顔を洗っていてはたと何かに気付いた。
そういえば、どこか見覚えがある景色な気がするのだ。
ゆっくり音を立てずにバスルームから覗けば、今通って来た場所が廊下を兼ねた細いキッチン。そして奥には、自分がさっきまで寝ていた部屋がある。
よくある1Kの間取りだ。だが、しかしである。
千鶴のよく知る間取りとソックリ……というかそのもの。置いてある家具や配置はまったく違うが、備え付けの冷蔵庫はまったく同じ。
「えっと?」
(ここはどこ?)
と訊こうとしたら、フェイスタオルが顔に飛んで来た。
「ベッドの下に折り畳みのテーブルがあるから、出しとけ」
「あ、はい」
慣れた手つきで料理をする彼をチラッと見つつ、千鶴は奥の部屋に向かった。
本来なら手伝うのが一番だろうが、勝手も知らないし彼の手際が良過ぎて自分が邪魔になりそうだ。
そして、何より、部屋をもう一度確認したかったのである。
奥の部屋は、自分と同じ八畳程。窓が広いので、ベッドは自然と壁際になる。それに合わせた家具の配置になるので、自分と似たような部屋になるのかもしれない。
千鶴は見渡しながらガタガタと、ベッドの下から折り畳みテーブルを出した。
(なるほど、ここにテーブルをしまうのはアリだな)
こんな訳の分からない状態なのに、彼の部屋にある物の置き方に頷いていた。
ベッドの下に服をしまっている千鶴とは、使い方が違って面白いし勉強になっていたのだ。
「あんたの部屋と変わんねぇだろうが」
もはや晩飯を通り越して夜食の様な料理を、まったく知らない男……いや、彼が作って来てくれた。
キョロキョロとしている千鶴にため息を吐いていたけど。
「今さらですけど、ここはどこ?」
テーブルに置かれた料理に目を奪われつつ、千鶴は今一番知りたい事を訊けば、彼は千鶴にクッションを渡しながら答えくれた。
「203」
「え?」
「と な り」
そう言って彼は、何も敷いてない床にドカリと座った。
(となり、となり、となり!?)
「お隣りーーっ!?」
千鶴は思わず叫んでしまった。
道理で見たような部屋なハズだ。隣なら間取りは一緒だし、備え付けの冷蔵庫もあるに決まっている。
「大変申し訳ございません!!」
普段飲まない酒に飲まれた千鶴は、間違って隣の部屋に入っていたらしい。
そう気付いた千鶴は、クッションから降りて土下座した。
「まぁ、鍵を掛けなかった俺も悪……くはねぇが、冷めねぇ内に食え」
自分も悪いと言おうとしてやめた彼。
近くのコンビニだからと、鍵を掛けなかった自分がと思った様だが、確認せず部屋に入った上に、ベッドで寝た千鶴の方が悪いのでは? と考え直したらしい。
「いえ、あの」
「いいから食えよ」
折角作ったのだからと、彼は千鶴に箸を渡した。
テーブルに載っていたのは、炊き立てのご飯にきゅうりの糠漬け。後は卵が入っている温かいコンソメスープだった。
お酒を飲んでいた千鶴には、ちょうどいい量だが……何故コンソメスープ? と首を傾げたくなってしまった。
「悪いな。味噌を買い忘れてないんだよ」
「ふふっ。すごく美味しいです」
だからコンソメスープなのかと、千鶴は小さく笑った。
確かにこのラインナップなら、味噌汁が定番だ。だけど、そんな事が気にならないくらいに、冷え切っていた千鶴の心と身体がゆっくり温まっていった。
「そりゃあ良かったな。だけど、今度からは気をつけろよ? 普通なら襲われて終わりだ」
「はい」
確かにその通りだ。
自分から男の部屋に入り、ベッドで待ち構えた形となっていたのだ。
彼でなければ、今頃ーー
と考え、千鶴は今さらながらブルッと身体が震えた。
「食ったらさっさと帰れよ?」
「え?」
そっけない言葉とは裏腹に、彼の口調は実に優しかった。
「腹が適当に満たされて、目の前に美味しそうなデザートがあれば……食いたくなるのが男の性さがってな?」
要は襲うぞ? と注意してくれているのだ。いや、揶揄っている気もするが。
それを言うなら、その言葉に身の危険を感じ、衝動的に立ち上がりたくなるのが、女の性さがだろう。
だが、そう言った彼の表情がいやらしくなく、誘うような色っぽい姿で千鶴の頬が、酔ったように赤くなっていた。
ーーピン!
「いったぁ!」
「ばぁか。そこで顔を赤らめるんじゃねぇ」
呆れた様な声と共に、向かいに座っている彼は、千鶴のおでこをピンと弾いたのである。
「すみません」
(だって、何だか彼ならイイか……いやいや、何を考えているのかな!?)
千鶴はさらに赤く染まっていく顔を、ブンブンと横に振っていた。
「ご、ご、ごちそうさまでした」
もはや、夜食の味なんか分からなかった。
千鶴の頭は色んな煩悩から逃れるために、必死で戦っていたのである。こんな事は初めてだった。
「お粗末さん」
食器を片付けるついでに、千鶴の頭をクシャリとして行くから、千鶴の頭は先程排除した煩悩がお呼びですかと、カムバックする。
(何、この感じた事のないモヤッとした変な感情は!)
「お皿を洗わせて下さい!!」
(この煩悩ごと!!)
千鶴は彼の後を慌てて追った。
何かしないと気持ちが落ち着かない。とにかく身体を動かしたいと千鶴は立ち上がった。
「皿洗ったら帰れよ?」
(デザートを食べたくなるからですか?)
なんて、恥ずかしくて冗談でも言えない。
「はい」
もはや、千鶴の頭に隆弘の面影などないに等しかった。
慌てて洗うのも変な気がするし、ゆっくり洗うのもおかしい。
でも、洗い終わったら帰らなきゃいけない。頭は帰らなきゃと分かっているが、心はまだここにいたいとざわついていた。
千鶴はさらなる苦行に立たされていたのであった。
「お騒がせ致しました」
結果として、千鶴は理性が勝った。
そもそもフラれたばかりだ。そんな女が、見ず知らずの男の部屋に乱入して、何故かご飯をご馳走になり、身まで任せる訳にはいかない。
そんな軽い女でいたくないと、千鶴の理性が勝利の雄叫びを上げていた。
(そういえば、名前を訊いてなかったな)
そうチラッと思いつつ、自分の荷物を持ってドアから出れば、千鶴の背後から耳にそっと息が掛かった。
「今度来たら、抱くからな?」と。
「な、な、なっ!」
息を吹きかけられた耳を慌てて押さえて振り返れば、彼はドア枠に寄りかかり、手をヒラヒラさせて笑っていた。
「来ませんよ!!」
揶揄われたのだと分かり、千鶴はそう反射的に言ったが……きっと行くような気がする。
そんな予感しかなかった。