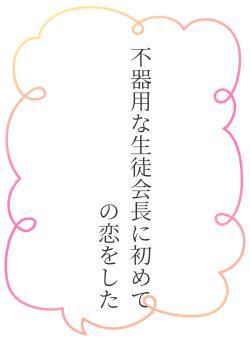線香花火が落ちたそのとき
「俺さ……好きな人いるんだよね」
突然、幼馴染の優太がそう言った。
幼馴染の恋愛話なんて聞きたくない。何となく暑いからという理由で線香花火をしているけれど、私にとって線香花火は大好きだし。
「へぇー、そっか」
「何だよ、興味なし? 恋バナなんてしたことなかったのに」
「恋バナとか言わないで。優太の好きな人とか興味ない」
「相変わらず花は辛辣だなぁ」
私はわざとらしくはぁ、とため息を吐く。
優太は明るくて人気者。小学校、中学校と確かに女子からモテていたと思う。告白される度に断っていたらしいけれど。
幼馴染の恋なんて聞きたくない。私には関係ないことだし、恋愛なんてさっぱり分からないから。
「花は好きな奴とかいないの?」
「いるわけないでしょ」
そう答えると、優太の線香花火がぱたっ、と地面に落ちた。
その線香花火を見ると何だか胸がぎゅーっと強く締め付けられる。
「優太の線香花火落ちるの早いね」
「……あぁ、そうだな。花のはまだ?」
「うん、何か全然落ちない。珍しいね」
何だかぎこちない会話になってしまう。
私はまた線香花火に視線を戻した。
「もう中学終わっちゃうね」
「な、早かったなー」
「受験とかどうしよ。全く考えてないよ」
「俺も」
もしこのまま中学校が終わって、優太と高校が別々になったら、もう話せなくなってしまうのだろうか。
恋人なんかじゃない、ただの幼馴染だから会う機会もだんだん減るのだろう。
そう考えると、少しさみしい気もした。
「……この線香花火見ると、小さい頃思い出すな」
「え? いつの話?」
「俺と花で、どっちが線香花火長く続くかっていうゲームしたとき。先に落ちちゃったほうが負け」
「あー、そんなのあったね」
優太と小さい頃からずっと、こうやって線香花火をやっていた。
華やかな打ち上げ花火よりも、私たちはこういう小さい花火が好きだから。
「あのときは俺が勝ったんだよな」
「確かに私負けたかも。五歳くらいのときだから、悔しくて大泣きしたの覚えてる」
「はは、花は負けず嫌いだったもんなぁ」
――優太ともっとこうやって、線香花火をしていたい。
このまま夏が終わるなんて嫌だ。この気持ちはなんていうのだろう。
「……なぁ、花」
「ん? どうしたの?」
「――俺、花のことが好き」
その瞬間、私が持っていた線香花火がぱたっと地面に落ちた。
その花火は決して小さいけれど、何よりも華やかで美しかった。
胸が高鳴って、頭の中まで鼓動が伝わってくる。
こんなにもドキドキしたことない気がする。
「……昔から好きだった。明るくていつも笑顔の花のこと。高校に行っても離れたくない」
――あぁ、そっか。この気持ちはきっと……。
恋、というものだろう。
「だから、俺と付き合ってください」
差し出された優太の手を、強く握る。
それから私は、優太のことをぎゅーっと抱きしめた。
「私も好きです」
――たとえ小さい線香花火でも、好きな人に対するこの「好き」という気持ちは、打ち上げ花火くらい胸いっぱいに広がっている。
突然、幼馴染の優太がそう言った。
幼馴染の恋愛話なんて聞きたくない。何となく暑いからという理由で線香花火をしているけれど、私にとって線香花火は大好きだし。
「へぇー、そっか」
「何だよ、興味なし? 恋バナなんてしたことなかったのに」
「恋バナとか言わないで。優太の好きな人とか興味ない」
「相変わらず花は辛辣だなぁ」
私はわざとらしくはぁ、とため息を吐く。
優太は明るくて人気者。小学校、中学校と確かに女子からモテていたと思う。告白される度に断っていたらしいけれど。
幼馴染の恋なんて聞きたくない。私には関係ないことだし、恋愛なんてさっぱり分からないから。
「花は好きな奴とかいないの?」
「いるわけないでしょ」
そう答えると、優太の線香花火がぱたっ、と地面に落ちた。
その線香花火を見ると何だか胸がぎゅーっと強く締め付けられる。
「優太の線香花火落ちるの早いね」
「……あぁ、そうだな。花のはまだ?」
「うん、何か全然落ちない。珍しいね」
何だかぎこちない会話になってしまう。
私はまた線香花火に視線を戻した。
「もう中学終わっちゃうね」
「な、早かったなー」
「受験とかどうしよ。全く考えてないよ」
「俺も」
もしこのまま中学校が終わって、優太と高校が別々になったら、もう話せなくなってしまうのだろうか。
恋人なんかじゃない、ただの幼馴染だから会う機会もだんだん減るのだろう。
そう考えると、少しさみしい気もした。
「……この線香花火見ると、小さい頃思い出すな」
「え? いつの話?」
「俺と花で、どっちが線香花火長く続くかっていうゲームしたとき。先に落ちちゃったほうが負け」
「あー、そんなのあったね」
優太と小さい頃からずっと、こうやって線香花火をやっていた。
華やかな打ち上げ花火よりも、私たちはこういう小さい花火が好きだから。
「あのときは俺が勝ったんだよな」
「確かに私負けたかも。五歳くらいのときだから、悔しくて大泣きしたの覚えてる」
「はは、花は負けず嫌いだったもんなぁ」
――優太ともっとこうやって、線香花火をしていたい。
このまま夏が終わるなんて嫌だ。この気持ちはなんていうのだろう。
「……なぁ、花」
「ん? どうしたの?」
「――俺、花のことが好き」
その瞬間、私が持っていた線香花火がぱたっと地面に落ちた。
その花火は決して小さいけれど、何よりも華やかで美しかった。
胸が高鳴って、頭の中まで鼓動が伝わってくる。
こんなにもドキドキしたことない気がする。
「……昔から好きだった。明るくていつも笑顔の花のこと。高校に行っても離れたくない」
――あぁ、そっか。この気持ちはきっと……。
恋、というものだろう。
「だから、俺と付き合ってください」
差し出された優太の手を、強く握る。
それから私は、優太のことをぎゅーっと抱きしめた。
「私も好きです」
――たとえ小さい線香花火でも、好きな人に対するこの「好き」という気持ちは、打ち上げ花火くらい胸いっぱいに広がっている。