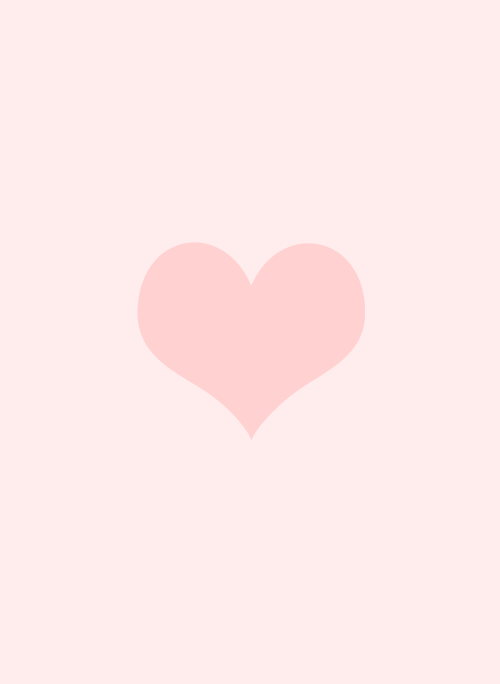流星群の落下地点で〜集団転移で私だけ魔力なし判定だったから一般人として生活しようと思っているんですが、もしかして下剋上担当でしたか?〜
エンディング【シド】思い出
ハロルドを倒したあと、ノインにとっ捕まってリグに「一緒にいたい」とお願いされたシドは自由騎士団に所属することを了承した。
涼もそのまま自由騎士団に保護されるというリグについて、自由騎士団の本部に行くことを選んだ。
自由騎士団で召喚魔法師の部門を作るということなので、涼とリグも協力することにした。
試行錯誤の結果、涼とリグは流入召喚魔たちを送還する方法を編み出す。
まずは近隣の村にいた流入召喚魔の中で、帰還を希望した者に仮契約を行い、送還してみる。
その後再び召喚し、無事に帰還できたかを確認してみた。
すると、泣いて喜び「帰れた」と報告を聞いて涼とリグは手を叩く。
成功したのだ。
そこからは多くの流入召喚魔がいるところへ立ち寄り、希望者を募る。
ノインは剣聖として認められ、シドも瞬く間に一等級になり剣聖として認めるか否かを働きを見て決めるという。
しかし、ノインとともにリグと涼が送還魔法のために各地を巡ることになったあと、二人を常に完璧に守り抜いている。
剣聖として認められるのは時間の問題だろう。
「あいつ、ハロルド・エルセイドの息子だろう?」
「でも王都ダンジョン化の時、ハロルド・エルセイドと敵対したらしいじゃないか」
「剣聖の称号を本当に与える気なのか? 元広域指名手配犯が剣聖だなんてあり得ないだろう」
そんな声はもちろん聞こえる。
ウォレスティー王国とエレスラ帝国国境付近の小さな村に来た時には、特にそんな声がわかりやすく聞こえてきた。
「ここは変わらないな」
「リグ、この村に来たことがあるの?」
「ああ。ハロルドの研究施設が近くにあったんだ。僕もシドもそこで生まれて、ダロアログに連れ出されるまでそこで育った。【機雷国シドレス】のアンドロイドが教育係で、彼らに囲まれて最低限の常識を学んだのだが――なにぶん【機雷国シドレス】の常識も多くて、ダロアログには『死なない程度に生き延びろ』とあの頃は自由に出歩けていた」
え、とドン引きする。
シドとリグはその頃この辺りに滞在して、外の常識を学んだらしい。
しかし、親のない幼い子どもを放り出すとは。
食事も寝る場所も自分でなんとかしろ、と丸投げにされて、シドはお金を稼ごうとしたが五歳の子どもを雇うところなどあるわけもなく結局盗みに手を染めた。
あるいは、最初からそれがダロアログの目的だったのかもしれない。
「あそこのパン屋……」
「うん」
「よくシドが盗みに入ったパン屋だな」
「えっ」
と、言われてみると、今まさにシドがそのパン屋の店主に話しかけているところだ。
普通にお金を手渡して、パンをそれなりの量買い込んでいる。
パンがいっぱい詰まった紙袋二つも抱えて店から出てくるシドに、リグが目を細めた。
「お客さん! お金が多いよ!」
その時、パン屋の店主が慌てたように出てきて叫ぶ。
シドはそれに対して「ツケてた分だよ」と言ってリグと涼の方に近づいてきた。
リグの顔を見るなり、店主は目を丸くして「あっ」と声を漏らす。
黒髪紫眼と金髪碧眼の双子なんて、そうそういるものではない。
この辺りで何度も悪さをしていたのなら、覚えていても不思議ではないだろう。
「わあ、なになに差し入れ? シドにしては気が利くじゃん」
「ああ、好きなの食え。大して美味くないけどな、あそこのパン屋」
「なんで突然失礼なこと言うの? そんなに買い込んでおいて。一個もらうねぇ」
「じゃあ僕も」
「わ、私も」
駆け寄ってきたノインがぱくり、とシドの抱える紙袋からパンを一つ取って口に入れる。
もぐもぐと咀嚼してから「まあ、さすがにリータさんとリョウちゃんに比べたら、だけど。普通に美味しいよ」と絶妙に反応に困る感想を言う。
涼も食べてみる。
こう言ってはなんだが、確かに可もなく不可もない味。
「……ああ、懐かしいな」
「マジでなんの改良もなく変化もないの笑うよな」
くっくっ、と笑うシドと、懐かしがるリグを見て、店主の表情がじわじわと赤くなって歪んでいく。
なにも店の側で、店主の目の前で言わなくてもいいだろうに。
「ツケ分いくら置いてきたの?」
「細かく覚えてねぇし、八百万ラーム置いてきた」
「そりゃ店主も顔色変えて追いかけてくるよ……ビビるよそんな大金ポンと置いていかれたら……怖いよ、逆に……引くよ……」
「屋根の修繕費でも窯の新調にでも好きに使えばいいだろう」
「うん、そのうちまた食べにきたい」
「リグとシドには思い出の味なんだね」
と、涼が言うとリグが嬉しそうに頷く。
それを見ていた店主が、ついにブチギレたように「次来る時はもっと美味いパン食わせてやるわ! クソガキが!」と叫んで店の中に戻っていった。
クスクスと笑うノイン。
「ほら」
「あ、モンブランクリームパン」
「変わり映えがないと思っていたが、栗はお前が食べ方を教えて広まったんだろう? これは悪くない」
「――ふふふ、よかった」
彼の思い出の味に、自分が伝えた栗が少しだけ手を加えた。
それを受け入れてもらえた。
肩が寄り添う。
今はまだ、この距離感が心地いい。
シド 自由騎士団エンディング