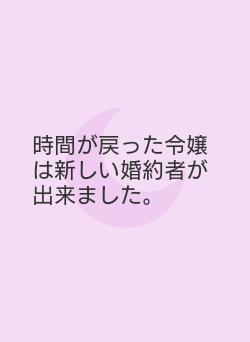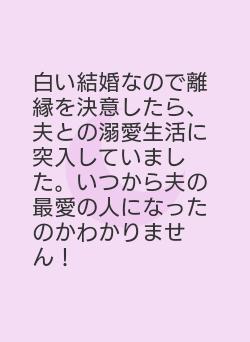光の聖女は闇属性の王弟殿下と逃亡しました。
第五十五話 ブラックローズ
__シュタルベルグ国の離宮の夜。
光の祝祭から一ヶ月以上も経ち、今はシュタルベルグ国でヴェイグ様と暮らしている。
カレディア国もシュタルベルグ国の属国になり、ヘルムート陛下はヴェイグ様に褒美もくれたが、ヴェイグ様は気にもしてなかった。
離宮の庭園には、毎日シード(魔法の核)を育てており、それが収穫(?)と言っていいのか、とにかく収穫できる頃になっており、土の中から取り出せば、煌めくようなシード(魔法の核)が出来上がっていた。
「セレスティア。リリノアを連れて来たぞ」
「まぁ、お待ちしてましたわ」
リリノア様にシード(魔法の核)を埋め込むために、ヴェイグ様に連れて来てもらったが……思わず眉根が上がる。
リリノア様がヴェイグ様と腕を組んで来ていたのだ。
「別にくっついて来てくださいとは言ってないのですけど……」
「呼んで来いと言ったのは、セレスティアだぞ」
まぁ、ヴェイグ様からすれば、妹のような存在なのだろうけど。
「セレスティア様。私に御用とは何でしょうか?」
少なからず不機嫌さを現わした表情に、ヴェイグ様との結婚がまったく無くなり、私に恨みもあるらしい。でも、リリノア様の性格では、何も私を落とす策略など考えもできないようで、何もできずにいたのだ。
「リリノア様。ちょっとだけヴェイグ様から離れて、こちらへいらしてください」
「ここでは、ダメなのですか?」
「良いものを差し上げます。ですから、これで元気を出してください」
むすっとした表情で、ヴェイグ様に背中を押されて私の前に立ったリリノア様に、腕を出すように言った。
「いいですか。少し身体に違和感があるかもしれませんが、すぐになじむと思いますので……馴染めなかったら、言ってくださいね」
馴染めなかったら、それは、シード(魔法の核)の適正がないと言うことで、身体からはじき出されるだろう。
でも、リリノア様は生まれつきシード(魔法の核)持ちだと言う。そう考えたら、馴染めないことはないと確信に似たものを感じる。
「それは?」
「私が造ったシード(魔法の核)です。癒しの魔法の紋を刻んでいるので、それをどう育てて極めるかはリリノア様次第です」
シード(魔法の核)を埋め込む魔法で、リリノア様の身体にシード(魔法の核)を埋め込むと、自然と吸い込まれるように入っていく。
シード(魔法の核)を埋め込む魔法の光に茫然としたリリノア様と違って、私は安堵した。
吸い込まれるような状況は、そのシード(魔法の核)が身体にあっているということだから。
だから、探索のシードが私ではなく、側にいたヴェイグ様に吸い込まれたのだ。
「……魔法……」
「はい。癒しの魔法がこれで使えます。癒しの魔法なら、失敗しても誰にも迷惑をかけないと思いますので……遠慮なく使って、精進してください」
「魔法が使える……私にも……?」
「上級魔法がすぐに使えるわけではありませんが、それはリリノア様次第です」
これで、自信に繋がればいい。何かに夢中になれば、きっと誇りに思えることが出てくるはずだ。
私ができるのは、ここまでだ。
リリノア様の人生は背負えないし、ヴェイグ様を譲ることもできない。
でも、自信がなく、父親や王妃様に結婚などで振り回される彼女の悩みが少しでも解消されればいいと思うし、手助けはしたいと思う。
「……セ、セレスティアお姉さま!!」
感無量で泣きながら、前触れもなく抱き着いてくるリリノア様に驚いた。
「私、これで魔法が使えるのですねっ……失敗しても誰にも迷惑をかけずにっ……」
「そうですけど……私はお姉さまではありませんよ」
「意地悪でふしだらなな聖女様かと思って、酷い態度を取って申し訳ないですわ!」
「そんなことを思ってましたか……」
「お茶に下剤も盛ったのに、騒ぎが起きて二人ですぐにどこかへ行ってしまい……飲まなくて良かったですわ!!」
「それは知りませんでした!」
いきなり言葉も選ばずに暴露するリリノア様。
何もできないでいただろうと思えば、そんな可愛い意地悪をしていたとは!?
しかも、華麗に空振りしている状況になっていた。
そう思われていたのだと思うけど、口に出されると複雑だ。
でも、聖女機関での嘲笑や侮蔑のほうが酷かった。
そう思えば、リリノア様のは可愛いものなのだろう。
「あんまり構うと、懐かれて大変なことになるぞ」
「そのようです……」
抱き着くリリノア様から、私を引き離すヴェイグ様も少し呆れ気味だ。
「リリノア。少し落ち着きなさい」
「はい……セレスティアお姉さまに嫌われないようにします」
「そうしなさい。それと、王妃もセレスティアとの結婚にもう反対はできないから、心配するな」
「私は、頑張らなくていいのですね……」
「お前のは、俺に対してあったのは愛じゃない」
「意地悪です」
「だが、間違いないだろう」
図星を刺されたみたいで、リリノア様が目を伏せた。
「頑張るのは他のことにしなさい」
「……はい。ごめんなさい。ヴェイグ様」
「いい子だ」
優しくヴェイグ様が頭を撫でると、リリノア様が頬を染める。
リリノア様の初恋はヴェイグ様なのだろう。子供が年上に憧れるものに似ている。
「私、魔法を頑張ります」
「きっと上手くいきますよ。シード(魔法の核)が吸い込まれたということは、リリノア様にその魔法と相性がいいからです」
「セレスティアお姉さま……嬉しいです」
また、涙をながすリリノア様に、シード(魔法の核)を造って良かったと思えた。
一生懸命にハンカチで涙を拭きながら、何度もお礼を言って去っていくリリノア様を見送り、姿が見えなくなった。
「あんなに喜んでくれるなんて……」
「ずいぶん悩んでいたからな。落ちこぼれだと言われるのは、気持ちのいいものではない」
「そうですね……リリノア様なら、良い癒し手になると思います」
無垢な彼女なら、慈しむように癒しの魔法を使える気がする。
「ヴェイグ様にも、見せたいものがあるのです」
「俺に?」
「はい。一緒に庭園へ来てください」
ヴェイグ様の手をとり庭園へと向かうと、以前ヴェイグ様から贈られたブラックローズの花が咲いており、それを美しく幻想的に照らすように周りに埋めたシード(魔法の核)が光を放っていた。
腰を下ろしてブラックローズをよく見ると、ヴェイグ様も腰を下ろして愛おしそうに見ていた。
「蕾から咲いたのです」
「ああ、綺麗なものだな。シード(魔法の核)もまた造っていたのか?」
「周りで光っているのは、光の祝祭で割ったシード(魔法の核)です。光の魔力を入れただけのものですので、光らせるのにちょうどいいかと……」
「珍しいシード(魔法の核)だぞ」
ククッとヴェイグ様が笑みを零し、つられて私もふふっと笑ってしまう。
「でも、光の祝祭のシード(魔法の核)は魔除けなどの意味も込めて玄関先や部屋に飾る人も多いのですよ。旅人は、光を放つシード(魔法の核)をお守りとして持って行くのです」
「効果抜群だな。では、ブラックローズが散れば、このシード(魔法の核)はお守りとして、アクセサリーに変えるか? 二つに割れば二人で持っていられるし、また野営する時は役に立ちそうだ」
「それは良いですね。でも、また野営する時が来ますか?」
「カレディア国にあった闇のシード(魔法の核)は、欠片だと聞かなかったのか? 言った気もするが?」
「欠片……?」
そう言えば、そんなことを言っていた気がする。
「ということは……」
「また、どこかで闇のシード(魔法の核)が見つかれば探しに行く。どうせ、あれに馴染む奴はいないかなら」
それは、ヴェイグ様にしかできないことだ。
いずれ、また闇のシード(魔法の核)を探しに行くのだと予想される。そして、逃亡しそうな気がする。
自由気ままなヴェイグ様は、誰にも止められない。
「でも、しばらくはここにいる。結婚して、新婚生活というものを味わってみたい」
「お手柔らかにお願いしますね」
無言で見つめるヴェイグ様の顔が近づくと、頭を添えられるように支えられて口付けをされていた。
光の祝祭から一ヶ月以上も経ち、今はシュタルベルグ国でヴェイグ様と暮らしている。
カレディア国もシュタルベルグ国の属国になり、ヘルムート陛下はヴェイグ様に褒美もくれたが、ヴェイグ様は気にもしてなかった。
離宮の庭園には、毎日シード(魔法の核)を育てており、それが収穫(?)と言っていいのか、とにかく収穫できる頃になっており、土の中から取り出せば、煌めくようなシード(魔法の核)が出来上がっていた。
「セレスティア。リリノアを連れて来たぞ」
「まぁ、お待ちしてましたわ」
リリノア様にシード(魔法の核)を埋め込むために、ヴェイグ様に連れて来てもらったが……思わず眉根が上がる。
リリノア様がヴェイグ様と腕を組んで来ていたのだ。
「別にくっついて来てくださいとは言ってないのですけど……」
「呼んで来いと言ったのは、セレスティアだぞ」
まぁ、ヴェイグ様からすれば、妹のような存在なのだろうけど。
「セレスティア様。私に御用とは何でしょうか?」
少なからず不機嫌さを現わした表情に、ヴェイグ様との結婚がまったく無くなり、私に恨みもあるらしい。でも、リリノア様の性格では、何も私を落とす策略など考えもできないようで、何もできずにいたのだ。
「リリノア様。ちょっとだけヴェイグ様から離れて、こちらへいらしてください」
「ここでは、ダメなのですか?」
「良いものを差し上げます。ですから、これで元気を出してください」
むすっとした表情で、ヴェイグ様に背中を押されて私の前に立ったリリノア様に、腕を出すように言った。
「いいですか。少し身体に違和感があるかもしれませんが、すぐになじむと思いますので……馴染めなかったら、言ってくださいね」
馴染めなかったら、それは、シード(魔法の核)の適正がないと言うことで、身体からはじき出されるだろう。
でも、リリノア様は生まれつきシード(魔法の核)持ちだと言う。そう考えたら、馴染めないことはないと確信に似たものを感じる。
「それは?」
「私が造ったシード(魔法の核)です。癒しの魔法の紋を刻んでいるので、それをどう育てて極めるかはリリノア様次第です」
シード(魔法の核)を埋め込む魔法で、リリノア様の身体にシード(魔法の核)を埋め込むと、自然と吸い込まれるように入っていく。
シード(魔法の核)を埋め込む魔法の光に茫然としたリリノア様と違って、私は安堵した。
吸い込まれるような状況は、そのシード(魔法の核)が身体にあっているということだから。
だから、探索のシードが私ではなく、側にいたヴェイグ様に吸い込まれたのだ。
「……魔法……」
「はい。癒しの魔法がこれで使えます。癒しの魔法なら、失敗しても誰にも迷惑をかけないと思いますので……遠慮なく使って、精進してください」
「魔法が使える……私にも……?」
「上級魔法がすぐに使えるわけではありませんが、それはリリノア様次第です」
これで、自信に繋がればいい。何かに夢中になれば、きっと誇りに思えることが出てくるはずだ。
私ができるのは、ここまでだ。
リリノア様の人生は背負えないし、ヴェイグ様を譲ることもできない。
でも、自信がなく、父親や王妃様に結婚などで振り回される彼女の悩みが少しでも解消されればいいと思うし、手助けはしたいと思う。
「……セ、セレスティアお姉さま!!」
感無量で泣きながら、前触れもなく抱き着いてくるリリノア様に驚いた。
「私、これで魔法が使えるのですねっ……失敗しても誰にも迷惑をかけずにっ……」
「そうですけど……私はお姉さまではありませんよ」
「意地悪でふしだらなな聖女様かと思って、酷い態度を取って申し訳ないですわ!」
「そんなことを思ってましたか……」
「お茶に下剤も盛ったのに、騒ぎが起きて二人ですぐにどこかへ行ってしまい……飲まなくて良かったですわ!!」
「それは知りませんでした!」
いきなり言葉も選ばずに暴露するリリノア様。
何もできないでいただろうと思えば、そんな可愛い意地悪をしていたとは!?
しかも、華麗に空振りしている状況になっていた。
そう思われていたのだと思うけど、口に出されると複雑だ。
でも、聖女機関での嘲笑や侮蔑のほうが酷かった。
そう思えば、リリノア様のは可愛いものなのだろう。
「あんまり構うと、懐かれて大変なことになるぞ」
「そのようです……」
抱き着くリリノア様から、私を引き離すヴェイグ様も少し呆れ気味だ。
「リリノア。少し落ち着きなさい」
「はい……セレスティアお姉さまに嫌われないようにします」
「そうしなさい。それと、王妃もセレスティアとの結婚にもう反対はできないから、心配するな」
「私は、頑張らなくていいのですね……」
「お前のは、俺に対してあったのは愛じゃない」
「意地悪です」
「だが、間違いないだろう」
図星を刺されたみたいで、リリノア様が目を伏せた。
「頑張るのは他のことにしなさい」
「……はい。ごめんなさい。ヴェイグ様」
「いい子だ」
優しくヴェイグ様が頭を撫でると、リリノア様が頬を染める。
リリノア様の初恋はヴェイグ様なのだろう。子供が年上に憧れるものに似ている。
「私、魔法を頑張ります」
「きっと上手くいきますよ。シード(魔法の核)が吸い込まれたということは、リリノア様にその魔法と相性がいいからです」
「セレスティアお姉さま……嬉しいです」
また、涙をながすリリノア様に、シード(魔法の核)を造って良かったと思えた。
一生懸命にハンカチで涙を拭きながら、何度もお礼を言って去っていくリリノア様を見送り、姿が見えなくなった。
「あんなに喜んでくれるなんて……」
「ずいぶん悩んでいたからな。落ちこぼれだと言われるのは、気持ちのいいものではない」
「そうですね……リリノア様なら、良い癒し手になると思います」
無垢な彼女なら、慈しむように癒しの魔法を使える気がする。
「ヴェイグ様にも、見せたいものがあるのです」
「俺に?」
「はい。一緒に庭園へ来てください」
ヴェイグ様の手をとり庭園へと向かうと、以前ヴェイグ様から贈られたブラックローズの花が咲いており、それを美しく幻想的に照らすように周りに埋めたシード(魔法の核)が光を放っていた。
腰を下ろしてブラックローズをよく見ると、ヴェイグ様も腰を下ろして愛おしそうに見ていた。
「蕾から咲いたのです」
「ああ、綺麗なものだな。シード(魔法の核)もまた造っていたのか?」
「周りで光っているのは、光の祝祭で割ったシード(魔法の核)です。光の魔力を入れただけのものですので、光らせるのにちょうどいいかと……」
「珍しいシード(魔法の核)だぞ」
ククッとヴェイグ様が笑みを零し、つられて私もふふっと笑ってしまう。
「でも、光の祝祭のシード(魔法の核)は魔除けなどの意味も込めて玄関先や部屋に飾る人も多いのですよ。旅人は、光を放つシード(魔法の核)をお守りとして持って行くのです」
「効果抜群だな。では、ブラックローズが散れば、このシード(魔法の核)はお守りとして、アクセサリーに変えるか? 二つに割れば二人で持っていられるし、また野営する時は役に立ちそうだ」
「それは良いですね。でも、また野営する時が来ますか?」
「カレディア国にあった闇のシード(魔法の核)は、欠片だと聞かなかったのか? 言った気もするが?」
「欠片……?」
そう言えば、そんなことを言っていた気がする。
「ということは……」
「また、どこかで闇のシード(魔法の核)が見つかれば探しに行く。どうせ、あれに馴染む奴はいないかなら」
それは、ヴェイグ様にしかできないことだ。
いずれ、また闇のシード(魔法の核)を探しに行くのだと予想される。そして、逃亡しそうな気がする。
自由気ままなヴェイグ様は、誰にも止められない。
「でも、しばらくはここにいる。結婚して、新婚生活というものを味わってみたい」
「お手柔らかにお願いしますね」
無言で見つめるヴェイグ様の顔が近づくと、頭を添えられるように支えられて口付けをされていた。