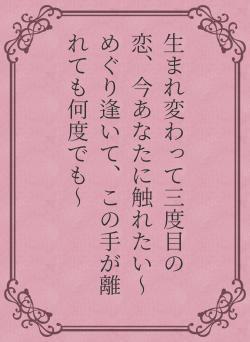アフタヌーンティーはFlavor of Love
お気に入りの古民家カフェで本を読みながらホットティーを飲むのが好きだ。
店長さんは物静かで、私が来店するとクラシックのレコードで店内を癒し空間に変えてくれる。
西洋文化が入り交じるレトロな雰囲気は少しだけ異世界転生した気分を味わえた。
注文するのは決まってお気に入りのホットティー。
ナチュラルな甘みの「ホット・シナモン・スパイスティー」は仕事終わりの疲れを解くように優しい味だ。
コールセンター並の電話をとってはクレーム対応をし、上司と板挟みにされストレスは大きい。
そのため、毎日喉がカラカラになっている。
疲れきった身体にスパイシーさと甘味がマッチしていた。
突然のクレームにより休日出勤した日のことだった。
いつもは夜に前を通る古民家カフェであったが、今日は珍しくアフタヌーンティーの時間にお店の前を通ることが出来た。
癒されたい気持ちがつのり、私は吸い込まれるようにお店へと入っていく。
「いらっしゃいませ」
いつもの店長さんではない。
茶色のエプロンをつけた爽やかで甘いマスクの青年だ。
グレーの色は珍しく、やや長めの前髪を邪魔そうに耳にかける。
それでもうっとうしいところはヘアピンでおさえ、店長さんがいつもレコードを蓄音機にかけてまわすように曲を選んでいた。
パチッと目が合えば蒼い瞳が印象的で、まつ毛さえもグレーと色素がうすい。
彼はおだやかに微笑み、スッと私を定位置に案内した。
「店長さんは?」
「店長はぎっくり腰でお休みなんです。代わりに僕が店番をしてます」
淡い微笑みを浮かべる彼はハチミツのように甘い。
店長さんは年齢の割に若く見える人だったが、詳しく思い出せば定年間近だったとつい苦笑いをしてしまう。
ぎっくり腰とは大変だと思いつつ、この店がなくなったら嫌だと居心地のよい場所に思いを馳せた。
それだけ世の中は後継者に悩まされ、素敵な場所でも泣く泣く店じまいをするしかない。
店長さんのいない空白はレトロでかわいらしい店内を空虚にみせてきた。
(ヴァイオリン……。アベマリアだ)
店長さんはジャズ好きだが私が来店するといつもクラシックレコードに変えてくれる。
居心地よく過ごせる環境を提供してくれる気づかいが好きだった。
だからこそなおさら終わりの時が迫っているのかもしれないと想像して胸が傷んだ。
私は決まって窓際の一人席に座り、水を一口飲む。
代理であろう彼に私はいつも通り注文をする。
「ホット・シナモン・スパイスティーとプレーンのスコーンを一つ」
「かしこまりました」
笑顔でオーダーを受けるとカウンター裏へ入っていき、準備をはじめる。
嗅ぎなれた甘酸っぱい香りが店内に充満した。
(さて、至福の時間ね)
私の趣味は乙女系のライトノベルでも読むことである。
家だとバタバタして読めないのであえて喫茶店で読むのが好きであった。
だが人に表紙を見られるのは恥ずかしい。
その点でこの古民家カフェはちょうど良い場所だった。
鞄から本を出してしばらく読んでいると店内の変化に気付く。
アベマリアが流れていたはずなのに、いまは優雅なメロディーを奏でる曲に切り替わっていた。
「愛の挨拶……」
イギリスの作曲家エドワード・エルガーが作曲した楽曲で、エルガーの結婚相手となるアリスに送ったプロポーズの曲である。
まるで甘ったるいロマンス小説に流れてきそうなメロディーに、私は本を捲りながら気分を良くしていた。
シナモンとスパイシーな香りが鼻をくすぐる。
「おまたせしました。ホット・シナモン・スパイスティー……とプレーンスコーンです」
一口飲めば、店長さんの入れたものと全く変わらない優しい味。
アルバイトにしては入れ方が上手だ。
今までこんな人は見たことがないと不審に思い、じとっと彼のきらびやかな顔を凝視した。
耳を赤く染める彼に気づき、私はカップを置いて口元をペーパーナプキンで拭いた。
「あの、何か?」
「えっと……。ーーさんですよね?」
「そうだけど……?」
先ほどの丁寧な対応と比べるとずいぶんとぎこちない口調になる。
あんなにスムーズな接客だったのに、今はまるではじめて接客をする人のようだ。
それでもホットティーの入れ方はパーフェクト。
ホットティーをいれる様は真摯で人懐っこさが薄れる。
本当に紅茶や珈琲を愛しているだろうと気持ちのこもったカップに口をつける。
疲れた休日出勤の後にはスパイシーで身体があたたまり、リラックスして肩の力を緩めることが出来た。
「お会い出来てうれしいです」
よくわからないと首を傾げる。
「父から話をよく聞いていたので。本を読みながらホットティーを飲んで時間と空間を楽しんでくれる方だと」
「なにそれー。店長さんそんなこと言ってたんだ」
店長の息子さんだったのか。
そういえば目元の穏やかさがよく似ており、目尻のホクロは色っぽい。
たしかにこの甘いマスクならこの先もモテ続けるだろう。
スラリとした高身長で、妖艶さは女性をまやかしの世界へ連れていってしまいそうだ。
さっそく幻想世界に引きづられて、私はハッとしてホットティーを一口飲んで好奇心を押し流した。
それを見て彼は目を細めて柔く微笑み、カウンターへ下がっていく。
「ホットティー、好きなんですか?」
「えっ……と、好きかな。でもこれは特別好きなの」
心癒されるのは味なのか、それとも彼の心づかいなのか。
「やっぱりうれしいものなんでしょうね。父が熱く語るのは珍しいんです」
「あっ……熱く語るって……」
「プライベートなことは語りませんよ? ただ他ではなくうちだから選んでもらえてると実感出来てうれしいみたいです」
「……そっか」
それならば私もうれしいことだと安堵の息をつく。
彼の言葉は直球なのかカーブなのかあいまいで受け取り方に悩んでしまう。
そのまま受け取れば勢いに押され、カーブが取れたところで捻れたまま回転してしまうだろう。
何を考えているのやら……と澄まし顔をしながらも脳内では会議が行われていた。
整った顔立ちに色っぽいチェロのような声色。
艶やかな好青年はハチミツのように甘いかと思えば、深く入ろうとすると苦みがある。
出会う以前から私の憩いを理解して、やさしさを添える姿勢に平常心でいられるほど、私は無欲ではなかった。
「癒しになってたらそれが一番だと。疲れててもほんの少し、元気になれば。そんな話を聞いてると……気になっちゃいますよね」
こんな口説き文句、天然で出てくるの?
それともわざと?
考えると恥ずかしくなって誤魔化すように目の前にあるスコーンを口にした。
(やっぱりおいしい)
ホットティーも好きだが、私にとって何よりなのはスコーンとの組み合わせだ。
静かに過ごせる懐かしの古民家、時代が移り変わる蓄音機からのムーディなクラシック。
本を読みながら幸せのスコーンに、じんわりと身体をあたためてくれるホット・シナモン・スパイスティー。
「ずっと会ってみたかったんです。いつもこのホットティーと一緒にスコーンを頼んでくれる人に」
「あ……」
「もてなすのは楽しいんですよ」
まるで忠実な執事に大事にされている気分で。
距離感を伺いながらも縮めてくるのは本当に接客?
かわいい子犬と思って撫でたら狼だった、と定番に振り回される。
こんな期待なんてしていい大人が恥ずかしいと思いながらもチラチラとみてしまう。
甘い微笑みが返されると勘違いでもいいや、と自惚れに走った。
……それでもいい。
それ以上に心づかいややさしい味に幸せをもらっていると気持ちがほっこりしていた。
プレーンスコーンはイギリスの定番スイーツで、この喫茶では忠実に丸く作られている。
そこに日替わりでついてくる手作りジャムをつけて食べるのが好きだった。
「ここのスコーンは甘さがちょうどよくて好きなの。ジャムは……」
「今日は無花果のジャムなんです。つぶつぶ感がスコーンの食感をさらに楽しませてくれて、甘みが落ち着いてて、僕のイチオシです!」
声がワントーン上がっている。
彼は心から癒しの空間を大事にしているのだと見ていて微笑ましい気分だ。
いつもは周りの機嫌をうかがい、笑顔を貼り付けていた私も自然と素直になっていた。
「……うん。私、これ好きだな」
仕事終わりの夕食代わりに訪れているようなものだが、このホットティーとスコーンだけは毎日食しても飽きがこなかった。
目を輝かせて語る姿は愛らしさを増す。
色っぽいと思えば幼さが見て取れて、コロコロ変わるかわいい青年だと胸がくすぐられた。
「とってもおいしい。ここのお店は本当に大好きなの。これからも通いたいなって思ってて……」
「はい。……よかった」
やさしい微笑みを見て興味が引かれる
どう考えても私の方が年上なのに彼への好奇心は捨てられないとホットティーを一口飲んで上目に見つめた。
仕事に明け暮れていた私のプライベート。
ささいな会話からはじまるアフタヌーンティー。
また会えたらうれしいと期待する反面、一歩引いて自制する気持ち。
不安定さにホット・シナモン・スパイスティーを口にすればまた来たいと思ってしまう。
あぁ、どうしようかな。
失望するのが怖くて一歩踏み出せない私がいる。
「……あなた名前は?」
その勇気は刺激的。
彼は花開くように明るい表情を浮かべた。
甘さと艶が混ざったシナモンスパイス。
「ーーです」
その響きが私の内側を熱くした。
火照った顔を誤魔化すようにホット・シナモン・スパイスティーを口にふくむ。
またいつものように本を読み、癒される。
リラックスのあいまに目が合うとじんじん火照ってしまう。
愛の挨拶でロマンスに浸りながら、私の休日はアフタヌーンティーだと手帳に記載した。
店長さんは物静かで、私が来店するとクラシックのレコードで店内を癒し空間に変えてくれる。
西洋文化が入り交じるレトロな雰囲気は少しだけ異世界転生した気分を味わえた。
注文するのは決まってお気に入りのホットティー。
ナチュラルな甘みの「ホット・シナモン・スパイスティー」は仕事終わりの疲れを解くように優しい味だ。
コールセンター並の電話をとってはクレーム対応をし、上司と板挟みにされストレスは大きい。
そのため、毎日喉がカラカラになっている。
疲れきった身体にスパイシーさと甘味がマッチしていた。
突然のクレームにより休日出勤した日のことだった。
いつもは夜に前を通る古民家カフェであったが、今日は珍しくアフタヌーンティーの時間にお店の前を通ることが出来た。
癒されたい気持ちがつのり、私は吸い込まれるようにお店へと入っていく。
「いらっしゃいませ」
いつもの店長さんではない。
茶色のエプロンをつけた爽やかで甘いマスクの青年だ。
グレーの色は珍しく、やや長めの前髪を邪魔そうに耳にかける。
それでもうっとうしいところはヘアピンでおさえ、店長さんがいつもレコードを蓄音機にかけてまわすように曲を選んでいた。
パチッと目が合えば蒼い瞳が印象的で、まつ毛さえもグレーと色素がうすい。
彼はおだやかに微笑み、スッと私を定位置に案内した。
「店長さんは?」
「店長はぎっくり腰でお休みなんです。代わりに僕が店番をしてます」
淡い微笑みを浮かべる彼はハチミツのように甘い。
店長さんは年齢の割に若く見える人だったが、詳しく思い出せば定年間近だったとつい苦笑いをしてしまう。
ぎっくり腰とは大変だと思いつつ、この店がなくなったら嫌だと居心地のよい場所に思いを馳せた。
それだけ世の中は後継者に悩まされ、素敵な場所でも泣く泣く店じまいをするしかない。
店長さんのいない空白はレトロでかわいらしい店内を空虚にみせてきた。
(ヴァイオリン……。アベマリアだ)
店長さんはジャズ好きだが私が来店するといつもクラシックレコードに変えてくれる。
居心地よく過ごせる環境を提供してくれる気づかいが好きだった。
だからこそなおさら終わりの時が迫っているのかもしれないと想像して胸が傷んだ。
私は決まって窓際の一人席に座り、水を一口飲む。
代理であろう彼に私はいつも通り注文をする。
「ホット・シナモン・スパイスティーとプレーンのスコーンを一つ」
「かしこまりました」
笑顔でオーダーを受けるとカウンター裏へ入っていき、準備をはじめる。
嗅ぎなれた甘酸っぱい香りが店内に充満した。
(さて、至福の時間ね)
私の趣味は乙女系のライトノベルでも読むことである。
家だとバタバタして読めないのであえて喫茶店で読むのが好きであった。
だが人に表紙を見られるのは恥ずかしい。
その点でこの古民家カフェはちょうど良い場所だった。
鞄から本を出してしばらく読んでいると店内の変化に気付く。
アベマリアが流れていたはずなのに、いまは優雅なメロディーを奏でる曲に切り替わっていた。
「愛の挨拶……」
イギリスの作曲家エドワード・エルガーが作曲した楽曲で、エルガーの結婚相手となるアリスに送ったプロポーズの曲である。
まるで甘ったるいロマンス小説に流れてきそうなメロディーに、私は本を捲りながら気分を良くしていた。
シナモンとスパイシーな香りが鼻をくすぐる。
「おまたせしました。ホット・シナモン・スパイスティー……とプレーンスコーンです」
一口飲めば、店長さんの入れたものと全く変わらない優しい味。
アルバイトにしては入れ方が上手だ。
今までこんな人は見たことがないと不審に思い、じとっと彼のきらびやかな顔を凝視した。
耳を赤く染める彼に気づき、私はカップを置いて口元をペーパーナプキンで拭いた。
「あの、何か?」
「えっと……。ーーさんですよね?」
「そうだけど……?」
先ほどの丁寧な対応と比べるとずいぶんとぎこちない口調になる。
あんなにスムーズな接客だったのに、今はまるではじめて接客をする人のようだ。
それでもホットティーの入れ方はパーフェクト。
ホットティーをいれる様は真摯で人懐っこさが薄れる。
本当に紅茶や珈琲を愛しているだろうと気持ちのこもったカップに口をつける。
疲れた休日出勤の後にはスパイシーで身体があたたまり、リラックスして肩の力を緩めることが出来た。
「お会い出来てうれしいです」
よくわからないと首を傾げる。
「父から話をよく聞いていたので。本を読みながらホットティーを飲んで時間と空間を楽しんでくれる方だと」
「なにそれー。店長さんそんなこと言ってたんだ」
店長の息子さんだったのか。
そういえば目元の穏やかさがよく似ており、目尻のホクロは色っぽい。
たしかにこの甘いマスクならこの先もモテ続けるだろう。
スラリとした高身長で、妖艶さは女性をまやかしの世界へ連れていってしまいそうだ。
さっそく幻想世界に引きづられて、私はハッとしてホットティーを一口飲んで好奇心を押し流した。
それを見て彼は目を細めて柔く微笑み、カウンターへ下がっていく。
「ホットティー、好きなんですか?」
「えっ……と、好きかな。でもこれは特別好きなの」
心癒されるのは味なのか、それとも彼の心づかいなのか。
「やっぱりうれしいものなんでしょうね。父が熱く語るのは珍しいんです」
「あっ……熱く語るって……」
「プライベートなことは語りませんよ? ただ他ではなくうちだから選んでもらえてると実感出来てうれしいみたいです」
「……そっか」
それならば私もうれしいことだと安堵の息をつく。
彼の言葉は直球なのかカーブなのかあいまいで受け取り方に悩んでしまう。
そのまま受け取れば勢いに押され、カーブが取れたところで捻れたまま回転してしまうだろう。
何を考えているのやら……と澄まし顔をしながらも脳内では会議が行われていた。
整った顔立ちに色っぽいチェロのような声色。
艶やかな好青年はハチミツのように甘いかと思えば、深く入ろうとすると苦みがある。
出会う以前から私の憩いを理解して、やさしさを添える姿勢に平常心でいられるほど、私は無欲ではなかった。
「癒しになってたらそれが一番だと。疲れててもほんの少し、元気になれば。そんな話を聞いてると……気になっちゃいますよね」
こんな口説き文句、天然で出てくるの?
それともわざと?
考えると恥ずかしくなって誤魔化すように目の前にあるスコーンを口にした。
(やっぱりおいしい)
ホットティーも好きだが、私にとって何よりなのはスコーンとの組み合わせだ。
静かに過ごせる懐かしの古民家、時代が移り変わる蓄音機からのムーディなクラシック。
本を読みながら幸せのスコーンに、じんわりと身体をあたためてくれるホット・シナモン・スパイスティー。
「ずっと会ってみたかったんです。いつもこのホットティーと一緒にスコーンを頼んでくれる人に」
「あ……」
「もてなすのは楽しいんですよ」
まるで忠実な執事に大事にされている気分で。
距離感を伺いながらも縮めてくるのは本当に接客?
かわいい子犬と思って撫でたら狼だった、と定番に振り回される。
こんな期待なんてしていい大人が恥ずかしいと思いながらもチラチラとみてしまう。
甘い微笑みが返されると勘違いでもいいや、と自惚れに走った。
……それでもいい。
それ以上に心づかいややさしい味に幸せをもらっていると気持ちがほっこりしていた。
プレーンスコーンはイギリスの定番スイーツで、この喫茶では忠実に丸く作られている。
そこに日替わりでついてくる手作りジャムをつけて食べるのが好きだった。
「ここのスコーンは甘さがちょうどよくて好きなの。ジャムは……」
「今日は無花果のジャムなんです。つぶつぶ感がスコーンの食感をさらに楽しませてくれて、甘みが落ち着いてて、僕のイチオシです!」
声がワントーン上がっている。
彼は心から癒しの空間を大事にしているのだと見ていて微笑ましい気分だ。
いつもは周りの機嫌をうかがい、笑顔を貼り付けていた私も自然と素直になっていた。
「……うん。私、これ好きだな」
仕事終わりの夕食代わりに訪れているようなものだが、このホットティーとスコーンだけは毎日食しても飽きがこなかった。
目を輝かせて語る姿は愛らしさを増す。
色っぽいと思えば幼さが見て取れて、コロコロ変わるかわいい青年だと胸がくすぐられた。
「とってもおいしい。ここのお店は本当に大好きなの。これからも通いたいなって思ってて……」
「はい。……よかった」
やさしい微笑みを見て興味が引かれる
どう考えても私の方が年上なのに彼への好奇心は捨てられないとホットティーを一口飲んで上目に見つめた。
仕事に明け暮れていた私のプライベート。
ささいな会話からはじまるアフタヌーンティー。
また会えたらうれしいと期待する反面、一歩引いて自制する気持ち。
不安定さにホット・シナモン・スパイスティーを口にすればまた来たいと思ってしまう。
あぁ、どうしようかな。
失望するのが怖くて一歩踏み出せない私がいる。
「……あなた名前は?」
その勇気は刺激的。
彼は花開くように明るい表情を浮かべた。
甘さと艶が混ざったシナモンスパイス。
「ーーです」
その響きが私の内側を熱くした。
火照った顔を誤魔化すようにホット・シナモン・スパイスティーを口にふくむ。
またいつものように本を読み、癒される。
リラックスのあいまに目が合うとじんじん火照ってしまう。
愛の挨拶でロマンスに浸りながら、私の休日はアフタヌーンティーだと手帳に記載した。