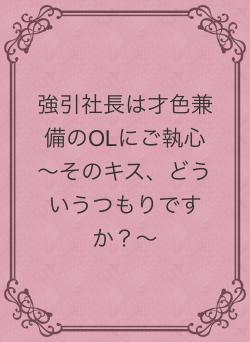運命の相手が幼馴染だなんて、今さら言い寄られても困ります!
とある日曜日の昼下がり。
週末最後、漫画でも読みながらのんびり過ごそうと思っていたら、父に呼ばれた。
だだっ広いリビングダイニングの中央に鎮座する革張りのソファに腰を沈めれば、父が信じられないことを言う。
世界屈指のホテル企業、雨宮グループが、父が経営する和泉不動産との共同事業として今度新しく大きなプロジェクトを興すらしい。
そこで私に、幼馴染でもある雨宮グループの御曹司と結婚しろ、と。
政略結婚ということだ。相手があの男じゃなければ、私もこんなに難色を示したりしない。
「絶ッ対に嫌。なんで私がお父さんの都合で、あの男と結婚しなきゃいけないの!?」
「志乃(しの)、あのなぁ…。 彼のどこが気に入らないっていうんだ。おまえが小さい頃からよく遊んでくれて、優しくしてくれたじゃないか」
優しくしてくれた?
そんなわけない。同い年で近所に住んでいた雨宮蓮(あまみや れん)は、出会ったその瞬間から意地悪なやつだった。
忘れもしない。近所の公園で遊んでいた時のこと。物怖じしない性格の私は見慣れない子を見かけたので声をかけた。新しい友達ができるかもしれないという純粋な気持ちからだった。
しかし……
『いやだ。ひとりでいたいんだよ、あっちへ行け』
まさか断られるとは思っていなかった当時の能天気な私はかなりショックを受けて帰宅。
ところがびっくり、もう関わることはないだろうと思っていた矢先、雨宮蓮が両親に連れられて引越しの挨拶に来たのだから。
それからも、私は嫌いだって言ってるのに、かえるやだんごむしをご丁寧に虫かごにいれて贈呈してきた幼稚舎時代に、私が男子にからかわれていたら、『こいつのどこがそんなにいいんだよ。もっと面白いやついんじゃん、他に』って意地悪な顔で言ってきた小学校。
ひとりでいたいとかほざいていたのはどこの誰だって話よ。
中学に上がると、話しかけてもほとんど無視。高校生になるころには口数は戻りつつあったものの、気まずいことこの上ない関係のまま家が近いせいでたまに会ったら『お前、変わんねーな』とか仏頂面でバカにするように言われ続けて迎えた二十五歳の今春。
その最悪な幼馴染と、まさか結婚だなんて。誰が予想できたというの?
運命とはなんて非情なのだろう。
「……っ、で、なんで私はあんたと食事をしているのよ!夜景の綺麗なホテルのレストランで!」
「普通に誘っても来ないと思って。お前、俺の事嫌いだろ?」
ええ、まあ大嫌いですとも。
『うちの犬が寂しがってるから会いに来てやってくれ』って言うからこいつの家に行けば、ドックフードを買いに行くとか言って車に乗せられて。
着いた先はペットショップじゃなくてホテル。
詐欺だ。拉致誘拐だ。解せん。
これこそが雨宮蓮。この男、完全に私をおちょくっているのだ。
仏頂面を決め込む私に、蓮がふっと笑う。
「お前ほんと、変わんねーな」
その言葉にムッとして、つっけんどんに言い返す。
「蓮もね。昔からずっと、私をバカにしてからかって」
「愛情の裏返しだって。志乃は鈍いからな、気づかないだろうけど」
「キモチワルイこと言わないで。今どきの小学生だってもっとマシな愛情表現するでしょう」
あからさまに嫌な顔をすれば、蓮は肩を竦めて笑った。
「おお、辛辣。刺さるわ〜」
口では言うけど、顔は笑っているんだもの。
これっぽっちも傷ついてなどいないのは分かっている。
ムカつく。その端正な顔と完璧で隙のない態度がそそけるところを見てみたいものだ。
蓮の魂胆に気づけていればのこのこと付いてなんてこなかったのに。
難なく私を騙して連れてきた隣のこの男はムカつくけど、料理とお酒は美味しいから帰らない。
食事と睡眠は私にとって何より大事なのだ。
それもこれも分かっててこの男……!
「美味いだろ?ここ。 フランス帰りの有名なシェフがやってるんだけど、その人愛犬家で有名なんだよ。CoCoっていう名前も、ワンコの名前だって噂。親近感湧くよな」
黙々と味を楽しむ私を横目に、楽しそうにそう話す蓮。
犬好きなのは、嫌いなこいつの唯一諒とできる点だ。愛犬家に悪い人はいないって謎の自信がある私は、犬に弱い。
母が犬アレルギーで家では飼えないから、私たちが中学生の頃に蓮のお父さんが拾ってきたゴールデンレトリバーのだいふくを我が子のように愛でてきたのだ。
態度が素っ気なくなりつつあった蓮にとっては、暇さえあれば蓮の家に入り浸っていた私をさぞ鬱陶しく思っただろう。
それにしても…なるほど、愛犬家か。目の前にあるビーフシチューの旨みが更に増した気がする。
「優しい味がする。絶対良い人よ、ここのシェフ。それに、イケメンなんでしょう?この間見た雑誌に、料理特集にしては随分顔写真多めのページが載ってたの、思い出した」
「スペック的には俺も負けてないと思うけど?」
なぜかドヤ顔をきめてくる蓮に、私は思いっきり顔を顰めてみせる。
「何1人で競ってるの?くだらない」
「志乃ってば、ほんと冷たい」
誰のせいよ。思春期だかなんだか知らないけど、急に口効いてくれなくなってから今まで、どれだけ気まずい思いをしたと。
大人になった今こうして調子よくからかってくるのだって、慣れてなくて居心地悪い。
いっそ一生思春期のままでいてくれればよかった。
すると、蓮が階下に広がる街の方に視線を向けたまま口を開いた。
グラスの氷がカランと音を立てて溶ける。
「志乃さー、俺と結婚したい?」
つい反射的に蓮の横顔を見つめてしまう。
一瞬、際どいワードにドキッとしたが、すぐにあの婚約の話だろうと思い直して彼から目を逸らす。どこか気の抜けた口調に、私は正直に答えてやる。
「したいわけないじゃない。誰があんたなんかと一生添い遂げるってのよ」
「だよな。そりゃそう言われても仕方ない。今までの俺は、ちょっとお前を妹扱いしすぎてた。幼馴染っていう切っても切れない出会い方をした運命に、甘えてたんだ」
妹扱い…されてたのね。意地悪もからかいも、いいリアクションする遊びがいのある妹だと思われてたわけね。
なんたる屈辱。たった数ヶ月早く生まれただけのくせに、年上気取ってないでよ。
しかも、切っても切れない出会い方…なんて、嫌な言い方をしてくれる。
蓮が私の方に向き直る。
「だからこれからは、お前をレディとして完璧にエスコートしようと思う」
唐突に言うから、パイの生地が喉に引っかかってむせた。
慌ててグラスを仰ぎ、息を整える。
ばっと蓮を見れば、馬鹿みたいに真剣な顔をしているじゃないか。
熱でも出たのだろうか。本気でそう思うくらいには、意味のわからない発言だった。
「もう今の関係に縋って逃げるのはやめる。志乃の婚約者として認めてもらえるように、お前を全力で落としにかかる」
「は、いや、何言って…」
「よろしく頼む」
「わ、私たちって、婚約…してないよね?」
目をぱちくりさせて動揺する私に対して、蓮は相変わらず涼しい顔を崩さない。
「親父さんから聞かなかったか?」
「…え、まさか、和泉と雨宮の会社が新規プロジェクトを立ち上げるとかで、これを機に私たちを使って両家を結びつけようっていう、あの悪しき計画……?」
「言い方最悪だけど、まあそういうこと。俺とお前は結婚することになったわけだ。本気にしてなかったのか?」
サーっと血の気が引く感じがした。
この男と、結婚…? 本当に…?
そんなの、幸せな未来が全く想像できないんですけど。
「…断固拒否したから、断ったつもりでいた」
「どこまでも寂しいこと言ってくれるな」
また、ちっとも寂しくなさそうな顔で飄々と言う。
「とりあえず、今はもうお前は俺の婚約者だから。あとは結婚までに、志乃の心も俺のものにするために精進するよ。 最終的には、他の男が石ころに見えるくらい俺にメロメロにさせてやる」
にっと口角を上げて楽しそうな笑みを浮かべる蓮の顔面に一発拳を入れても良かったのではないかと思う。
大企業と言われるようになってもなおこれからの成長を期待されているホテル王の御曹司であり、その手腕は既に発揮済み。将来有望と持て囃され、顔面は国宝級に整っている。高身長で、愛想はいいから外面は王子様さながら。
玉の輿を狙う女性も多かろう。引く手数多に違いない。
だけど、家のしがらみに巻き込まれて、大嫌いなこいつと夫婦にならなきゃいけないなんて、私にとっては至極不本意な展開だった。
*
「志乃ちゃん。夕飯食べてく?」
夕方、日が完全に落ち始める頃、潔子さんがキッチンから顔をのぞかせて言った。
そうしたいのはやまやまだけど、私はだいふくの大きな背中を撫でながら首を振る。
「んー、今日は帰ろうかな。お父さんが帰ってくるから、お母さんにご馳走作るの手伝えって言われてて」
「そっか。じゃあまた今度。志乃ちゃんの好きなもの、なんでも作っちゃうわよ」
「ありがとう。久しぶりにおばさんの唐揚げ食べたいな〜」
「いいわね。仕込んでおくわ」
蓮の、細身でスラリと長い手足はおばさん譲りだと思う。
おばさんは笑いジワを刻んで朗らかに笑う。
仕事帰りに、癒しを求めて向かいの蓮の家に寄っていたのだ。
共働きで両親不在のため、夕飯は私1人で簡単なもので済ませるだけなので、潔子さんに甘えていつもはそのまま夕飯をご馳走になって帰ることが多い。
蓮は実家を出ていて、会社近くのマンションに一人暮らしのためいない。
かわいいかわいいだいふくと、優しくて料理上手なおばさんと、帰宅して私を見ると笑って歓迎してくれるおじさんに囲まれて、多分私は蓮よりこの家を満喫している。
もういい大人だけど、ひとりであの大きな家に帰るのは好きじゃなくて、小さい頃からよく遊びに来ていたこの家の居心地の良さはもう手放せない。
『蓮もあまり帰ってこないし、志乃ちゃんが来てくれると娘ができたみたいで嬉しいよ』
なんて言ってくれるから、社交辞令だとは思わないで素直にありがたく受け取っておくのだ。
今日はリビングにカレーのいい香りが広がっていたからお腹がすいて仕方ないけれど、出張に行っていた父が戻るからと母が張り切っていたのを無下にもできず、家に帰ることにする。
「じゃあね、だいふく。いっぱい食べてよく寝て、長生きするんだよ〜」
私が立ち上がると、傍にくっついていただいふくものそのそと体を起こしてこちらを見上げる。
『もう帰っちゃうの?』って瞳で見つめてくるから、帰りたくなくなって困る。完全に私の都合のいい想像だけれど。
だいふくももうすぐ10歳の老犬。人間で言うと70歳くらいのおじいちゃんだ。
ひとつひとつの動作がおっとりしているのは昔からだけど、最近はそれに拍車がかかった気がする。
私は少しだけだいふくの頭を撫でてから、おばさんに挨拶をして玄関に向かった。
廊下に出て、電気が勝手についたタイミングで玄関が開く音がした。
おじさんが帰ってきたのだろうか。今日はいつもより早いな。
なんて思っていたら、顔をのぞかせたのは蓮だ。
私はびっくりして固まって、蓮と目が合った。
彼は表情を変えることなく言う。
「来てたのか」
「うん。でももう帰るから」
蓮に会うのは、一週間ぶりだった。彼に騙されて連れていかれたホテルでの食事以来のことだ。
口説かれ宣言を受けてから、どんな顔をしていいのかわからない。
私は言いようのない気恥しさに目をそらすように彼の横を通り過ぎようとする。
「待て。今日は飯、食ってかないのか?」
咄嗟に腕をやんわりと掴まれて反射的に振り向く。先程よりも近い距離に蓮がいて、体に力が入った。
「お父さんが出張から帰ってくるの。夕飯作らないといけないから」
「そうか。なら、一瞬待って」
言うなり、蓮は持っていたカバンを漁り出す。
なに?私は一刻も早くこの男の前から立ち去りたいのに。
「これ。取引先の人にもらった。今週末、空いてるか?」
蓮の手元には、スイーツ食べ放題の文字がポップに刻印されたチケットのようなものが2枚。
私は怪訝な顔をして、蓮の目を見る。
「どうして私に聞くの?」
「お前と行きたいから。デートに誘ってんの」
「お断りします。どうぞ他の人を当たって」
私が行くと言うとでも思ったのだろうか。
上から目線な物言いをばっさりと切り捨て、さっさと玄関から出ていこうとする。
けれど、蓮の長い腕がドアの鍵に伸びてきて、そのままカチャリと施錠するのに拒まれた。
「ちょっと。帰りたいんだけど」
「行くって言うまで帰さない」
実家の玄関で何を言っているのか。少し動くだけで蓮の体のどこかしらに触れてしまう距離感に、心臓がいい加減うるさい。
こんなの、今まではなかった。
「…~っ、わかった。行く、行くから離れて!」
デートの誘いに乗るよりも、今この状況のほうが耐えられなくて、私は振り向きざまに言いながら彼の体を押した。
「あれ、意外とあっさりOK出た」
あんたが行くって言うまで帰さないって言ったんでしょう!?
頑固で1度決めたら覆さない蓮のめんどくさい性格を知っていたから、今回はこっちが折れざるを得なかっただけだ。
「うるさい。私はもう帰るんだから!」
思わぬ足止めを食らったが、もういいだろう。
蓮を玄関から遠ざけて、ドアノブに手をかけたところで「あ、志乃、」と声がして、単純な私はまたもや振り返ってしまう。
すると、その手が今度は私の頭の上に伸ばされるから、驚きのあまり目を見開いて動きを止めた。
「な、ななななに!?」
「じっとしてろ」
さっき離れたのに、また蓮が近い!
スーツに包まれた身体が私に覆い被さるように迫ってきて、私は申し訳程度に両手を相手の胸に押し当てる。
そこで、廊下の奥の扉が開いた。
「お父さん?帰ってきたの…って、あら、蓮?」
話し声と物音に、おばさんが出てきてしまったようだ。
どう考えてもこの格好、向こうからは玄関先で抱き合ってるようにしか見えない。
「あら、あらあらあら、ごめんなさい、邪魔しちゃったわね。蓮、帰ってくるなら連絡くらいしてちょうだい。それと、志乃ちゃんが可愛いのはわかるけど、場所は考えなさいよ」
おばさんの明らかに機嫌のいい声の途中で、いつの間にか私の視界は開けていた。
蓮は靴を脱いで、何事も無かったかのように上がり框を上がっていく。
「部屋に探し物しに来たんだ。すぐ帰る」
おばさんの最後の言葉にはノータッチだ。
立ち尽くす私をよそに、親子の会話を一言二言交わして、おばさんはリビングに戻っていった。
蓮は振り返り、ふっと笑う。
「だいふくの毛、髪についてたからとっただけだよ」
「そ、そんなの、むしろこっちからつけられにいってるの!」
私は半ば叫ぶように言って、蓮の家を飛び出した。
蓮はこれからずっとあの調子で、私を惑わせてくるのだろうか。
蓮が蓮じゃないみたいで、落ち着かない。
どうしたらいいのかわからない。今までからかってばかりだったのに、急に近づいたり優しさを見せたり。
それで、その先に待っているのは結婚…?
忘れたはずの淡い感情が胸の奥で静かに疼く。
口を聞かなくなるまでは冷たいだけじゃなかった。大企業の後継者として幼い頃から苦労してきた蓮をずっとそばで見てきたのだ。誰よりも努力家で、自分に厳しく勇ましい彼を知っている。時折見せる、あいつなりの優しさだって……
そんな蓮のことが、私はずっと好きだった。
だけど、今は違う。
どういう風の吹き回しか知らないけど、急に優しくしたって無駄よ。
好きな人に無視されるようになったあの頃の私の切ない恋心を、今更掘り返そうったってそうはいかないんだから。
燻ってもう動くことは無いと思っていた運命がいま、確実に動き出したのに気づかないふりをした。
私は自宅の玄関で深く呼吸をしてから、母の待つキッチンへ向かった。