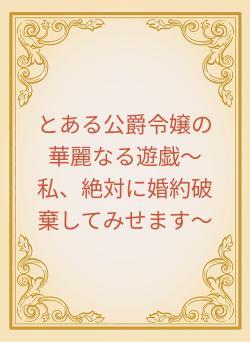戦場姫と呼ばれた伯爵令嬢は、隣国の王太子から寵愛を受ける
第1話 戦場姫と呼ばれた伯爵令嬢
「…デイジー頼む。どうか、君がアイリスの代わりに戦場姫になってくれないか?この通りだ」
焦燥しきった様子で頭を垂れ、私にそんなことを言う彼の名前は、レオ・エヴァンズ。
現在、17歳。エヴァンズ公爵家の長兄であり、私、デイジー・アッシャー伯爵令嬢の幼なじみ。そして、婚約者でもある青年だ。
(私が戦場姫に…?)
その瞬間、私はまるで、鈍器でガツンと頭を殴られたような衝撃に襲われた。そして、頭の中では理解しつつも、彼の言葉の真意を受け止められずにいる。
『戦場姫』
我が国、クリスティア公国にその制度ができたのは100年ほど前のことらしい。
戦争が行われる等、国の有事の際に、公国内から選ばれた18歳未満の少女が1人、士気を高めるために戦場へと送り出される。
戦場姫に選ばれることは我が国内では、たいへん名誉なこととされており、選ばれた家の少女は『英雄』としてその名はクリスティア公国内で語り継がれる。
そういう理由で、選ばれたからには戦場姫になることを断るなど言語道断。それはもちろん貴族令嬢も例外ではなかった。
しかし、その実情は体のいい「生贄」のようなもの。
非力な少女が命をかけて闘う戦地に送り出されれば、どうなるか…。それは火を見るより明らかであった。
「戦場姫に選ばれれば命はない」
我が国では誰しもが知る事実。
しかし今、私の婚約者であるはずの彼は、私にその『生贄』になれと言っているのだ。
しかも私の双子の妹であるアイリスの代わりに…。
アイリス・アッシャー。15歳。
私の双子の妹であり、アッシャー伯爵家の次女である。
アイリスは、クリスティア公国の「花姫(はなひめ)」と呼ばれるくらい愛らしい少女だ。プラチナブロンドの髪に綺麗なグリーンの瞳に白い肌。彼女が笑えば、その場がパッと明るくなると、ついた異名が「花姫」だった。
そして、私の名前はデイジー・アッシャー。
アイリスの双子の姉であり、同じく15歳。アッシャー伯爵家の長女になる。
私とアイリスは、一卵性の双子であり、容姿はお互いよく似ていた。グリーンの瞳や白い肌は同じ。
ただ、私の髪色は、父似の赤毛で、母方の血を色濃く受け継いだアイリスの透き通ったプラチナブロンドと比べれればかなり見劣りする。
性格も外向的な彼女と比べれば内向的で物静かな方であることは自覚していた。
『デイジーお姉様、レオお義兄様、早く行きましょう〜』
『アイリス、走ったら危ないわよ』
『ハハッ。全くアイリスは相変わらずお転婆だなぁ』
『……』
夜会が行われる際、私をエスコートしながも、彼の綺麗なブルーの瞳がアイリスの姿を追っていることは知っていた。
そう。彼が本当に好きなのは、私じゃなくてアイリスなのだ。
けれど、親同士の取り決めとは言え、彼の婚約者は長女である私。それが唯一の自分の取り柄のようにも感じていた。
レオは、私のこともとても大事にしてくれていたし、いつかは、アイリスではなく私自身のことを見てくれるはず。そう心の底では信じていた。
しかし、アイリスが「戦場姫」に選ばれてから、私の平凡な日常は終わりを告げる。
彼女が戦場姫として通達を受けたのは、数ヶ月前のこと。敵国フォルティスとの戦争が決まった日だった。
我が家にその知らせが届いた時、父も母も顔面蒼白となり、泣き崩れたのを覚えている。
知らせを聞いたレオも、青い顔をして飛んできた。必死にアイリスを救うため、「戦場姫」制度をどうにかできないか奮闘しているその姿にチラッと浮かんだのは「私が選ばれたても今みたいに心配してくれたかしら」というものだった。
自分でも性格が悪いのはわかっている。
でも、婚約者を差し置いてでもアイリスを救おうとするレオの姿は明らかに常軌を逸していた。
もちろん私だってアイリスのことは、妹として大切に思っている。レオとは違う方面から、アイリスを救う方法はないかと、個人的に調べたりしたが、結局良い方法は見つからず…。
刻一刻と、彼女が戦場に赴く日が近づいてくるのを待つことしかできなかった。
『アイリス…。なんで私の可愛い娘が…』
『かわいそうな、アイリス。あの子じゃなく、選ばれたのがデイジーだったら…』
数日前、父と母の部屋の前を通りかかった時、偶然聞こえてきたそんな会話。
昔から母は私よりもアイリスのことがお気に入りだったから、私の前では本音は言わずともなんとなく、察していた。
父は何も言わなかったが、きっと母と同じことを思っているのだろう。
(私がアイリスの代わりに戦場へ…)
戦場姫は、基本的にランダムで選ばれるが、立候補することも可能であった。その場合、元々決められていた戦場姫が辞退をすれば、立候補者が代わりの戦場姫となる。
だが、言わずもがな戦場姫の制度が始まってから100年と少し。その間、ただの一度も立候補者がでたことはなかった――。
そして、アイリスが戦場姫として戦地に赴く前日。レオが唐突に私を訪ねてきた。
久しぶりに"私に"会いに来てくれたのだと、淡い期待を胸に秘め、彼が待つ屋敷のバルコニーやって来た私。
そんな私に対して、彼から告げられたのは愛の言葉でも、労いの言葉でもなく、アイリスの代わりに「戦場姫」になってほしいと言うもの。
(そう…。貴方も結局は、婚約者の私ではなく、アイリスを選ぶのね)
何かがガラガラと音を立てて崩れ落ちていくのを感じた。
「……」
シンと静まり返ったバルコニーで、私は泣きそうになるのを必死に堪えるように拳をギュッと握りしめる。
父も母も、そして、婚約者のレオですら、生きるのを望むのは私ではなく妹のアイリス。
「私も君にこんなことを頼むのは心苦しいのだが…。他に方法がないんだ。戦争に行けばか弱いアイリスでは確実に命を落としてしまうだろう。しかし、デイジー…。君は彼女より足も速いし運動神経もよかっただろう?だから…」
言いにくそうに口ごもるレオを見つめ、私はフッと自嘲的な笑みを浮かべた。
「たしかにそうですね。…わかりました」
(もうどうでもいいわ…)
私の言葉に一瞬、驚いたような表情を浮かべたレオだったが、次の瞬間には、ホッと安堵したように優しく微笑んでいる。
私が好きだった穏やかな彼の笑顔。今はもう何とも思わないけれど。
「…デイジー。君の勇気に感謝する。君は本当に妹思いの素晴らしい…」
「レオ様、もうよろしいでしょうか?それでは私、このことを報告して参りますから、これで失礼しますわね」
「あ、あぁ…そうだな」
私を褒め称えるレオの言葉を遮り、私はくるりと踵を返す。そして、バルコニーを後にした瞬間、一筋の涙が私の頬をツーッとつたった。
こうして、私は妹、アイリスの代わりに…。クリスティア公国史上初の立候補者として「戦場姫」となったのだ――。
**
「おい、聞いたか…。戦場姫様の話…!」
「あぁ。まさかあの戦争で生き残るなんてなぁ。たしかアッシャー伯爵家のご令嬢だったろう?妹の代わりに戦場姫に立候補したっていう」
「美談だよなぁ。しかも戦場姫で、生き残られた方は初らしいぞ。それに今日王城で帰還のパーティーが開かれるそうだ」
「それはぜひともこの目で戦場姫様を見なければ…!」
興奮したように話す市民たちの話題は、今やこの話で持ちきりだ。
そう。妹を救うために戦場姫に自ら名乗りを上げたというデイジー・アッシャーの帰還を知らせる話題。
デイジーが戦場姫として戦地に赴いてから、2年の月日が経とうとしていた――。