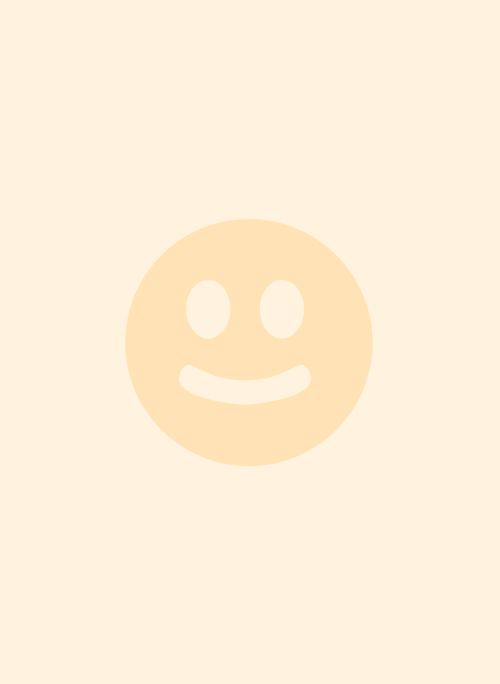古い館
古い館
大野健はいつの間にか、どこかで見たことのある古い館にいた。
少年時代、お化け屋敷といって遊んでいた西洋風の大きな家と酷似している。階段を上るごとに「ミシッキュキュッ」という気味の悪い音を立てるのであった。
上りきると大きな踊り場があって、そこにはありし日の親友の姿があった。
それは紛れもなく翔であった。翔はその名に相応しく天馬の如く翔るのが、得意だった。
運動会の徒競走ではいつもダントツの一位であったのを覚えている。
サッカー少年だった翔と野球少年だった健はいつも放課後になると、近くの公園で違う大きさのボールを持っていった。そこにある大きな壁に向かってボールを投げ、あるいは蹴って遊んでいた。
それぞれがそれぞれの球技を何も違和感を感じず、同じ場所でやっていたのである。
二人はお互いを尊重し合っていた。
将来もプロの野球選手、サッカー選手をお互い目指していた。だが、その夢は翔の命とともに潰えたのである。
忘れもしない、あれは小学六年の時の放課後。翔が交通事故にあった日だ。
いつも同じ公園で二人が自主練をした帰りだった。
その日は金曜日で、次の日はお互いクラブの練習があった。
それもあって、早めに自主練を切り上げたのだった。そして、いつものように自転車で童心に戻り、競輪ごっこをして帰宅の途に入るのだった。
それが、まさか翔の命を奪うとはその瞬間まで思ってもいなかったのである。
今、目の前にはその時と同じジャージ姿の翔が立っているのである。
プロ入団五年目のたくましい体つきをした健を彼は羨望の眼差しで見つめている。
その眼差しに堪えられなくなって、健は翔に声をかけた。
「なぁ、翔。許してくれ。そもそも俺があんな遊びを提案しなければ、翔の命を……」
「いや、あれは健のせいじゃないよ。あの日は俺の足の調子が悪かったんだ。というより、俺は不治の病に侵されてもう治る見込みはなかったんだ。本当はあの時、すでに医者から止められていたんだ。運動はもうするなって。自分でも思うように体を動かせなくなっていることに気づいてたんだ。もう、俺は一生サッカーができない。そう思うと悔しくてさ。あの時、車が突っ込んでくる音も耳に入って来なかったんだ。」
悔しさと悲しさが入り雑じった表情を隠すように翔は十数年前の真実を告白したのである。
「そっか、そうだったのか。翔は苦しんでたんだな。何で、俺は気づいてやれなかったんだろう。俺は友達として失格だ。」
健は自分の頭をかきむしった。
「ううん、もういいんだ。俺は健のことを今でも最高の親友だと思っているし。それから、俺は天国で楽しくやっている。ほら、この通り」
翔はあの頃よく学校の階段でやっていたのと同じように見事な跳躍をやってみせた。
そして、いつの間にか途切れた階段の上の方までいき、健の視界から消えていった。
「翔……」
翔が去ったあと足元を見ると、小さな紙片のようなものが落ちていた。紙片には翔らしい丁寧な字で「ありがとう」とだけ記されていた。
少年時代、お化け屋敷といって遊んでいた西洋風の大きな家と酷似している。階段を上るごとに「ミシッキュキュッ」という気味の悪い音を立てるのであった。
上りきると大きな踊り場があって、そこにはありし日の親友の姿があった。
それは紛れもなく翔であった。翔はその名に相応しく天馬の如く翔るのが、得意だった。
運動会の徒競走ではいつもダントツの一位であったのを覚えている。
サッカー少年だった翔と野球少年だった健はいつも放課後になると、近くの公園で違う大きさのボールを持っていった。そこにある大きな壁に向かってボールを投げ、あるいは蹴って遊んでいた。
それぞれがそれぞれの球技を何も違和感を感じず、同じ場所でやっていたのである。
二人はお互いを尊重し合っていた。
将来もプロの野球選手、サッカー選手をお互い目指していた。だが、その夢は翔の命とともに潰えたのである。
忘れもしない、あれは小学六年の時の放課後。翔が交通事故にあった日だ。
いつも同じ公園で二人が自主練をした帰りだった。
その日は金曜日で、次の日はお互いクラブの練習があった。
それもあって、早めに自主練を切り上げたのだった。そして、いつものように自転車で童心に戻り、競輪ごっこをして帰宅の途に入るのだった。
それが、まさか翔の命を奪うとはその瞬間まで思ってもいなかったのである。
今、目の前にはその時と同じジャージ姿の翔が立っているのである。
プロ入団五年目のたくましい体つきをした健を彼は羨望の眼差しで見つめている。
その眼差しに堪えられなくなって、健は翔に声をかけた。
「なぁ、翔。許してくれ。そもそも俺があんな遊びを提案しなければ、翔の命を……」
「いや、あれは健のせいじゃないよ。あの日は俺の足の調子が悪かったんだ。というより、俺は不治の病に侵されてもう治る見込みはなかったんだ。本当はあの時、すでに医者から止められていたんだ。運動はもうするなって。自分でも思うように体を動かせなくなっていることに気づいてたんだ。もう、俺は一生サッカーができない。そう思うと悔しくてさ。あの時、車が突っ込んでくる音も耳に入って来なかったんだ。」
悔しさと悲しさが入り雑じった表情を隠すように翔は十数年前の真実を告白したのである。
「そっか、そうだったのか。翔は苦しんでたんだな。何で、俺は気づいてやれなかったんだろう。俺は友達として失格だ。」
健は自分の頭をかきむしった。
「ううん、もういいんだ。俺は健のことを今でも最高の親友だと思っているし。それから、俺は天国で楽しくやっている。ほら、この通り」
翔はあの頃よく学校の階段でやっていたのと同じように見事な跳躍をやってみせた。
そして、いつの間にか途切れた階段の上の方までいき、健の視界から消えていった。
「翔……」
翔が去ったあと足元を見ると、小さな紙片のようなものが落ちていた。紙片には翔らしい丁寧な字で「ありがとう」とだけ記されていた。