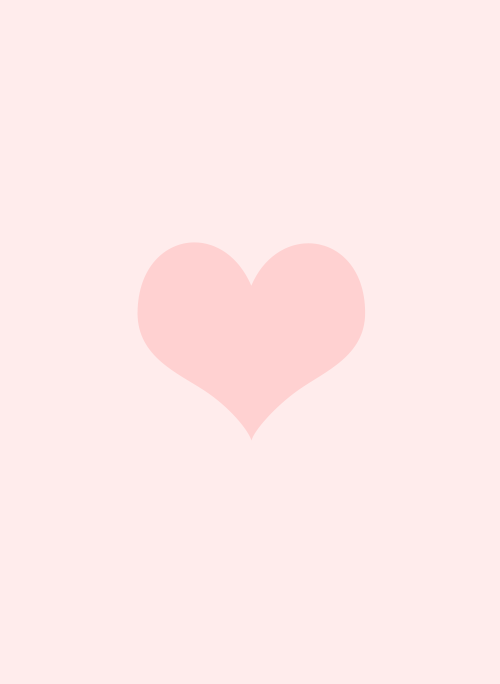ファントム・アクター
後編
後編
***
あのとき喜壱は階段から足を滑らせた女の子を庇って、階段を転げ落ちたそうだ。
信也の素早く適切な処置もあって大事には至らなかったものの、全治3ヵ月という診断が下され次の舞台への出演は絶望的となった。
しかし、事件はこれだけに留まらなかった。喜壱の抜けた穴を誰が埋めるかということについて、なんと僕に白羽の矢が立ったのだ。僕は当然信也がやるものと思っていたのに……。どうやら喜壱の推薦らしかった。なんで僕なんだ……?
「もう2ヵ月切ってるけど大丈夫か?太陽」
ミーティングの帰り道、信也が心配そうに僕に聞いた。
「セリフは……全部読みこんでたからどの役のセリフも入ってる」
「ん。いらん心配だったな」
「でも信也、僕に主役なんて務まりっこない。やっぱり今から先生に言って信也に……」
「何言ってんだ、あの喜壱の推薦だ。誰も文句ねぇよ。それに喜壱が推薦しなくても俺がしてたと思うぞ。お前がどれだけ努力したかはよく知ってる。喜壱もそれをわかってるからお前に託した。そんなお前が怖気づいててどうする」
「信也……」
「凍える太陽もそろそろ輝いていいんじゃないか?」
「え?」
「えって……え?」
「その呼び名どこで聞いたんだよ?小学校の時のあだ名だぞ」
「え……嘘だろ?えー……お前、俺と小学校一緒だったの覚えてないの?」
「え……えー?!」
ここ数日で一番驚いたかもしれない。まさか信也が小学校の同級生だったなんて。じゃあ中学校も一緒だったのか?全く覚えていないぞ……。冗談かとも思ったが、『凍える太陽』という僕の昔のあだ名を知っているのだから間違いないだろう。小学校のとき僕はたしかに同級生からそう呼ばれていた。
真面目で規則に厳しく、自分にも他人にも厳しく接していた僕はそう呼ばれてみんなから疎まれていたのだ。陰湿ないじめのようなものも受けていた気がする。その時につけられたあだ名だ。自分でも僕は太陽のような人間ではないことはわかっていたが、このあだ名は決定的だった。何故こんな名前負けするような名にしたのかと親を恨んだりもした。
そんな自分を変えたくて僕は演劇を始めたのではなかったか?確かに人付き合いは良くなったし、性格も大分丸くなった(信也のおかげというのが大きいのだが)。それでも僕は自分の名前が好きになることはなかったんだ。
そして僕は喜壱に出会ったのだ。
初めて喜壱と会ったとき、まるで太陽みたいな男だと……僕は思ったんだ。
「まぁ、喜壱にとってはお前はずっと太陽だったみたいだけどな」
「は?」
「……お前ってやつは……わかってはいたが、自分が助けた奴の名前くらい覚えとけ」
「助けた?」
「あいつは虐められてたんだ小学校のとき。その時お前が助けてくれたんだと。見舞いに行ったときに言ってたよ。詳しくは聞かなかったけどな」
本日2回目の衝撃だった。
まさか喜壱も同じ小学校だったなんて……世間は狭い……ってそこじゃない。あの喜壱が虐められていた?それだけでもにわかには信じられないのに、それを助けたのが僕だって?
全く記憶にない話だ。信也は誰か別の人間の話をしているんじゃないかと思った。
「とにかく太陽!今回の舞台はお前にかかってんだ!期待してるっ……ぞ!!」
バチンと激励の平手が僕の背中に思いっきり打ち込まれる。
僕にはそれを痛がる余裕もなく、息をのむをブルっと身震いをした。
***
子どもの頃の夢。
僕の目の前で男の子が泣いていて、僕はその子を叱りつけてるんだ。
と思ったらいつの間にか叱られてるのは僕だ。
「いいか、自分を信じるんだ。何を言われても関係ない。どんな自分も自分なんだ。自分自身なんだ」
僕はそこで目を覚ました。
思い出した。喜壱に言った言葉。
あれは僕が僕自身に言っていたのか?
***
それから舞台までの時間はあっという間に過ぎていった。
満員の体育館を舞台袖から覗き見て、僕は顔を青くしていた。そこに後ろからポンポンと肩を叩かれる。クリスティーン役衣装に着替えた姫野さんが立っていた。
煌びやかな衣装に身を包んだ彼女に目が奪われる。
「おーおー、緊張してるかと思えば、なに紅くなっちゃってんの?」
「えー、先輩本番前になに考えちゃってるんですかぁ~、や~らし~」
横からにやついた顔でちゃちゃを入れるのは信也と喜壱。喜壱は舞台には出られないものの音響などの裏方の手伝いならばやっていいとの許可が下りていた。
「う……うるさい黙れ!!」
僕はマントの下から小道具のナイフを取り出すと、ブンブン振り回して信也と喜壱を追い払った。
「芹澤君、いよいよ本番だね。緊張……してる?」
「うん……してる。でもあんだけ練習したんだ……きっと大丈夫」
「私もそう思う!」
そう言った姫野さんの手は、ギュッと握りしめられていた。僕は緊張をほぐしてあげたくて言葉を探す。
「姫野さん喜壱と付き合ってんの?」
「ええ?!」
自分でも思わぬ言葉が出てしまった。目の前のクリスティーンは顔を真っ赤にして固まっている。予想外の反応だったが、照れた顔がまた可愛い。
「そ、そんな、付き合ってなんてないよ!そう見える?」
慌てて否定する姫野さんを見て僕はポカーンとしてしまった。思わず笑いが込み上げてくる。姫野さんも僕がなんで笑っているのかわからないという顔で困惑していたが、すぐに笑顔になる。どうやら緊張はほぐれたようだ。お互い。
僕らはステージへと立つ。
孤独な怪人ファントムをステージで演じながら、考えていたことがあった。
僕と喜壱は実のところ似たもの同士なのかもしれないと。依然喜壱のことは何も知らないから、これはあくまでも僕が勝手に想像した根拠のない仮説ではあるが。
僕が何故喜壱を意識してしまうのかと言えば、例えば思ったことをサラッと口に出したり、恥ずかしいことを平気でやってみせたり、人の言うことにすぐ流されたり、遅刻したことをヘラヘラ謝ったり……。どれも僕が嫌いな喜壱の一面だが、それは言いかえれば素直であり、ユーモアであり、協調性があり、愛嬌があるということだ。それらは僕に欠けているものばかりだった。光の当たらない心の影の部分で無意識に抑圧している感情。
それを前面に持っている喜壱が羨ましかったのかもしれない。
まるで光に憧れるファントムのように。
僕は信也に出会ってから少し自分が変わったと思っていた。でも心の奥底では大して変っていなかったのかもしれない。それは自分と向き合うことでしか変えられない。
もっと向き合おう。自分と。
このステージが無事成功に終わったら、僕は自分の名前に誇りを持って前に進める気がする。
『私はオペラ座の怪人 思いのほかに醜いだろう?この禍々しき怪物は 地獄の業火に焼かれながらそれでも天国に憧れる!』
***
大勢の拍手が体育館中を埋め尽くしていた。
この喝采が自分に向けられているだなんて、まったく信じられない。
「なにボケっとしてんだ!カーテンコールだぞ」
そう言って信也が僕の背中を押し、すぐさまマントを引っ張って後ろに引きずり戻す。
「主役は最後だった」
「おい、僕で遊ぶな!」
それを見て喜壱と姫野さんがケタケタと笑っている。僕が睨みつけるとサッと姿勢を正す喜壱。
「あ、すんません芹澤先輩!」
「……た……太陽で……いい……ぞ」
その場の全員がキョトンとする。僕はステージにいた時よりも顔が熱くなっているのがわかった。恥ずかしくて死にそうだ。
「なに?!太陽先輩良く聞こえなかった!!もう一回」
「う……うるさい!!おま、聞こえてんじゃねぇか!!」
鳴り止まない拍手の音と、みんなの笑い声がいつまでも耳に残っていて、初めて感じたこの気持ちに僕はまんざらでもないと笑顔がこぼれてしまった。
その日から悪夢にうなされることはなくなった。
***
あのとき喜壱は階段から足を滑らせた女の子を庇って、階段を転げ落ちたそうだ。
信也の素早く適切な処置もあって大事には至らなかったものの、全治3ヵ月という診断が下され次の舞台への出演は絶望的となった。
しかし、事件はこれだけに留まらなかった。喜壱の抜けた穴を誰が埋めるかということについて、なんと僕に白羽の矢が立ったのだ。僕は当然信也がやるものと思っていたのに……。どうやら喜壱の推薦らしかった。なんで僕なんだ……?
「もう2ヵ月切ってるけど大丈夫か?太陽」
ミーティングの帰り道、信也が心配そうに僕に聞いた。
「セリフは……全部読みこんでたからどの役のセリフも入ってる」
「ん。いらん心配だったな」
「でも信也、僕に主役なんて務まりっこない。やっぱり今から先生に言って信也に……」
「何言ってんだ、あの喜壱の推薦だ。誰も文句ねぇよ。それに喜壱が推薦しなくても俺がしてたと思うぞ。お前がどれだけ努力したかはよく知ってる。喜壱もそれをわかってるからお前に託した。そんなお前が怖気づいててどうする」
「信也……」
「凍える太陽もそろそろ輝いていいんじゃないか?」
「え?」
「えって……え?」
「その呼び名どこで聞いたんだよ?小学校の時のあだ名だぞ」
「え……嘘だろ?えー……お前、俺と小学校一緒だったの覚えてないの?」
「え……えー?!」
ここ数日で一番驚いたかもしれない。まさか信也が小学校の同級生だったなんて。じゃあ中学校も一緒だったのか?全く覚えていないぞ……。冗談かとも思ったが、『凍える太陽』という僕の昔のあだ名を知っているのだから間違いないだろう。小学校のとき僕はたしかに同級生からそう呼ばれていた。
真面目で規則に厳しく、自分にも他人にも厳しく接していた僕はそう呼ばれてみんなから疎まれていたのだ。陰湿ないじめのようなものも受けていた気がする。その時につけられたあだ名だ。自分でも僕は太陽のような人間ではないことはわかっていたが、このあだ名は決定的だった。何故こんな名前負けするような名にしたのかと親を恨んだりもした。
そんな自分を変えたくて僕は演劇を始めたのではなかったか?確かに人付き合いは良くなったし、性格も大分丸くなった(信也のおかげというのが大きいのだが)。それでも僕は自分の名前が好きになることはなかったんだ。
そして僕は喜壱に出会ったのだ。
初めて喜壱と会ったとき、まるで太陽みたいな男だと……僕は思ったんだ。
「まぁ、喜壱にとってはお前はずっと太陽だったみたいだけどな」
「は?」
「……お前ってやつは……わかってはいたが、自分が助けた奴の名前くらい覚えとけ」
「助けた?」
「あいつは虐められてたんだ小学校のとき。その時お前が助けてくれたんだと。見舞いに行ったときに言ってたよ。詳しくは聞かなかったけどな」
本日2回目の衝撃だった。
まさか喜壱も同じ小学校だったなんて……世間は狭い……ってそこじゃない。あの喜壱が虐められていた?それだけでもにわかには信じられないのに、それを助けたのが僕だって?
全く記憶にない話だ。信也は誰か別の人間の話をしているんじゃないかと思った。
「とにかく太陽!今回の舞台はお前にかかってんだ!期待してるっ……ぞ!!」
バチンと激励の平手が僕の背中に思いっきり打ち込まれる。
僕にはそれを痛がる余裕もなく、息をのむをブルっと身震いをした。
***
子どもの頃の夢。
僕の目の前で男の子が泣いていて、僕はその子を叱りつけてるんだ。
と思ったらいつの間にか叱られてるのは僕だ。
「いいか、自分を信じるんだ。何を言われても関係ない。どんな自分も自分なんだ。自分自身なんだ」
僕はそこで目を覚ました。
思い出した。喜壱に言った言葉。
あれは僕が僕自身に言っていたのか?
***
それから舞台までの時間はあっという間に過ぎていった。
満員の体育館を舞台袖から覗き見て、僕は顔を青くしていた。そこに後ろからポンポンと肩を叩かれる。クリスティーン役衣装に着替えた姫野さんが立っていた。
煌びやかな衣装に身を包んだ彼女に目が奪われる。
「おーおー、緊張してるかと思えば、なに紅くなっちゃってんの?」
「えー、先輩本番前になに考えちゃってるんですかぁ~、や~らし~」
横からにやついた顔でちゃちゃを入れるのは信也と喜壱。喜壱は舞台には出られないものの音響などの裏方の手伝いならばやっていいとの許可が下りていた。
「う……うるさい黙れ!!」
僕はマントの下から小道具のナイフを取り出すと、ブンブン振り回して信也と喜壱を追い払った。
「芹澤君、いよいよ本番だね。緊張……してる?」
「うん……してる。でもあんだけ練習したんだ……きっと大丈夫」
「私もそう思う!」
そう言った姫野さんの手は、ギュッと握りしめられていた。僕は緊張をほぐしてあげたくて言葉を探す。
「姫野さん喜壱と付き合ってんの?」
「ええ?!」
自分でも思わぬ言葉が出てしまった。目の前のクリスティーンは顔を真っ赤にして固まっている。予想外の反応だったが、照れた顔がまた可愛い。
「そ、そんな、付き合ってなんてないよ!そう見える?」
慌てて否定する姫野さんを見て僕はポカーンとしてしまった。思わず笑いが込み上げてくる。姫野さんも僕がなんで笑っているのかわからないという顔で困惑していたが、すぐに笑顔になる。どうやら緊張はほぐれたようだ。お互い。
僕らはステージへと立つ。
孤独な怪人ファントムをステージで演じながら、考えていたことがあった。
僕と喜壱は実のところ似たもの同士なのかもしれないと。依然喜壱のことは何も知らないから、これはあくまでも僕が勝手に想像した根拠のない仮説ではあるが。
僕が何故喜壱を意識してしまうのかと言えば、例えば思ったことをサラッと口に出したり、恥ずかしいことを平気でやってみせたり、人の言うことにすぐ流されたり、遅刻したことをヘラヘラ謝ったり……。どれも僕が嫌いな喜壱の一面だが、それは言いかえれば素直であり、ユーモアであり、協調性があり、愛嬌があるということだ。それらは僕に欠けているものばかりだった。光の当たらない心の影の部分で無意識に抑圧している感情。
それを前面に持っている喜壱が羨ましかったのかもしれない。
まるで光に憧れるファントムのように。
僕は信也に出会ってから少し自分が変わったと思っていた。でも心の奥底では大して変っていなかったのかもしれない。それは自分と向き合うことでしか変えられない。
もっと向き合おう。自分と。
このステージが無事成功に終わったら、僕は自分の名前に誇りを持って前に進める気がする。
『私はオペラ座の怪人 思いのほかに醜いだろう?この禍々しき怪物は 地獄の業火に焼かれながらそれでも天国に憧れる!』
***
大勢の拍手が体育館中を埋め尽くしていた。
この喝采が自分に向けられているだなんて、まったく信じられない。
「なにボケっとしてんだ!カーテンコールだぞ」
そう言って信也が僕の背中を押し、すぐさまマントを引っ張って後ろに引きずり戻す。
「主役は最後だった」
「おい、僕で遊ぶな!」
それを見て喜壱と姫野さんがケタケタと笑っている。僕が睨みつけるとサッと姿勢を正す喜壱。
「あ、すんません芹澤先輩!」
「……た……太陽で……いい……ぞ」
その場の全員がキョトンとする。僕はステージにいた時よりも顔が熱くなっているのがわかった。恥ずかしくて死にそうだ。
「なに?!太陽先輩良く聞こえなかった!!もう一回」
「う……うるさい!!おま、聞こえてんじゃねぇか!!」
鳴り止まない拍手の音と、みんなの笑い声がいつまでも耳に残っていて、初めて感じたこの気持ちに僕はまんざらでもないと笑顔がこぼれてしまった。
その日から悪夢にうなされることはなくなった。