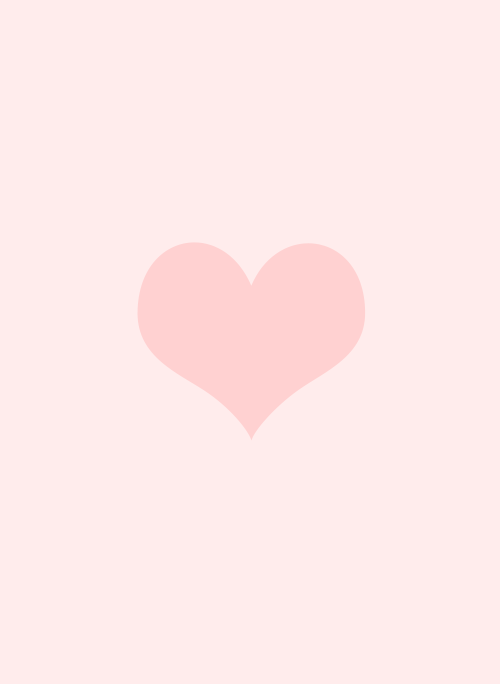心、欠片、深ク遠く。
上司のアドバイスは、きっと的確だったのだろう。
常に明るく、笑顔で。
時折、軽薄な冗談を飛ばす。
そんな「誰か」を演じながら年月を経るうち、子供たちに囲まれて、毎日を過ごすようになっていった。
「98歳で先生だなんて、すごいでしょう?」
いたい・・・
鼓膜をふるわす自らの声が、白々しい。
いたい、
わたしは、うまく笑えている?
痛イイタイ!
きしきしと、まだ残っている「わたし」のかけらが、軋む。
だからわたしは、感覚を閉ざす。
子供たちを、騙し続けなければならない。
子供たちに、愛される「誰か」で居続けなれば、ならない。
痛みを振り切るように、生徒たちと一緒に大声をあげて笑う。
ふと目線を感じて、振り返る。
まだ顔に幼さの残る女の子たち数名が、こちらを凝視していた。
その瞳には、何の感情も浮かんではいない。
それは、底さえ見えない、深い湖の水面(みなも)の色にも似て・・・
ゾクリとした。
瞬間、少女たちが唐突に笑いだす。
歯茎まで剥き出しにして。
演技しなければ・・・
騙し続けなければ・・・
教室に響きわたり続ける笑い声が、ふっと遠のいて聞こえた。
演技シテイタノハ、
騙サレテイタノハ。
ワタ し?
ソれトモ・・・
2008/4/20