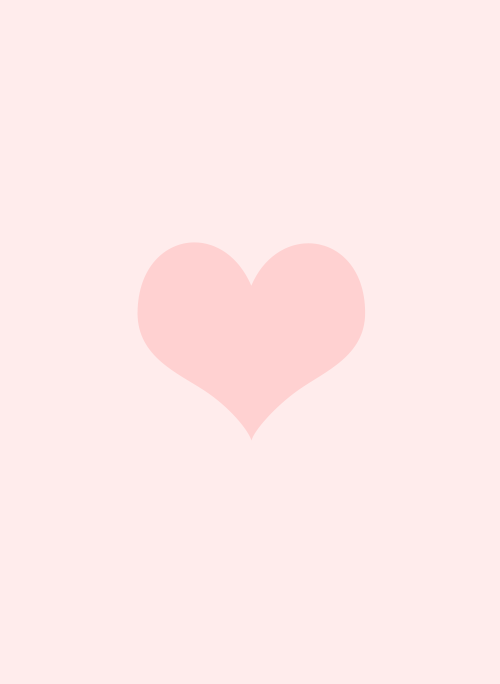君のように
*
そうして、僕は一人、もう誰も来ることのない丘のベンチに座っている。
彼女が去ってから、そう時間は経ってない。いや、正直なところ、自分でも時間の経過なんてわからない。あれからもう一時間は経ったのかもしれない。一分かもしれない。もしかしたら、一秒すら経ってないのかもしれない。
その証拠に、彼女の涙が染みた服の胸元は、まだ乾いてはいない。服の皺もそのままで。
どれだけ懸命に、彼女が僕にしがみついていたのか。その証明になるものが、目に見える形でまだ存在していた。
花火が上がらなくなった世界は、ただ静かだった。風が凪ぐ音さえしない。そして当然、木の葉が風に揺られる音すらしない。町の生活音も、虫の鳴き声も。何も聞こえない空間の中、僕はただベンチに座り続ける。
これでよかったのだろうか。そう、何度も自問し続けた。これが正解だったのか。これで正しかったのか。間違いはなかったのか。そんな、答えが出ようもないことを永遠と。
気が狂いそうだった。これから彼女と離れて生きていくことが、彼女に触れられないことが。これからの未来にありえないことなんだと思うと。今すぐにでも走り出し、まだどこかにいるかもしれない彼女の背中を追いたくてしょうがなかった。
……さっさと立ち上がればいいんだ。彼女を追うためではなく、家に帰り、部屋に篭り、それこそ狂ったように絵を描きばいい。
手放した彼女への想いを、その渇望を描き出せばいい。きっと素晴らしいものが出来る。僕らしい色合いで、僕らしい構図で、僕らしい作品が生まれるだろう。
きっと、彼女もそれを望んでいる。
「……帰ろう」
口にすることで、決意を促しているみたいだった。それでも僕の足は、僕自身の宣言なんて無視して、立ち上がることを拒否する。この場から離れたくないと、彼女との思い出の場所から帰りたくないと駄々をこねる。
どうして、絵を描いてきたんだろう。絵を描いていなければ、こんな気持ちになることはなかった。ただ普通に彼女と出会い、彼女の描く絵に見入られるだけの一般人でいられた。そうすれば、今の悲しみなんてなかったのに。
どうして僕は、絵など描いてきたのだろうか。
その時。
光が、上がった。
甲高い、笛のような音を立てて。
夜空に、一筋の光を走らせ。
暗く沈んだ、黒いキャンバスを、光で染め上げた。
「……そっか。今年から、二部制なんだっけ」
人口増加と人気急増による範囲拡大。さっきまでの花火よりもずっと、華やかで煌びやかな光が夜空を舞う。
次々と打ち上げられる火薬。幾筋もの軌道を残し、夜空を彩る。爆音を響かせ、一瞬の閃光を走らせ続ける。目に焼きついてしまうほどの強い光。いくつも、いくつもいくつも。その一瞬は続いていく。
「……綺麗、だな」
この輝きを、煌きを。今どれだけの人が眺めているんだろう。何百、何千、何万という人間が、この夜空のキャンバスに描かれた一瞬の名画に心を奪われているんだろう。
ふと立ち止まり、空を見上げ、その美しい光景を瞳に映しているんだろう。
夜空に浮かぶ美しさの中の儚さを、どれだけの人が……。
「……綺麗だ」
気づけば僕は、また涙を流していた。もう枯れるほど泣いたと思ったのに。夜空に浮かぶ光の軌跡を眺めていると、自然に涙が零れて、止まらなくなる。
美しいと思った。綺麗だと思った。一瞬の光が、消えてなくなる輝きが、儚く散っていく煌きが美しく見えてしょうがなかった。涙で滲んだ視界でさえ、その光の軌跡は華やかに美しく映る。
「描きたいな……」
そう思えた。この一瞬の奇跡を。夜空のキャンバスじゃない、紙のキャンバスに描き上げ、一生残しておきたいと。
誰もが目を、心を奪われる。
手が疼く。筆を振るいたくなる。その光の芸術を、僕の手で、魅力を余すことなく、増量して、この世界に残したい。
もう届かない希望を。目にした美しいものを、もう二度と同じものはない輝きを、自らの技術を駆使して形に残せる。
……ああ、だから僕は、絵を描いていたんだよな。
だから僕は、絵が好きなんだよな。
光の芸術祭はフィナーレへと差し掛かる。次々と放たれる輝き。夜なのに、眩しいぐらいの光を放って。
君なら、この光景をどう描くだろう。華やかに、明るく、けれど底抜けに美しく描くのだろうか。
なら僕は、この美しくも儚い光景をどう描こうか。
最後に放たれた大輪を、僕は両の眼で捉える。忘れないように、消えないように。なくなさいように、失わないように。
君が好きだと言った、僕なりの描き方を持って。
この、儚く美しい光景を描こう。
そうして僕は立ち上がる。ズボンについた砂や埃を払って。もう何も描かれない夜空のキャンバスを見て。けれど、頭の中ではさっきまでの輝きを思い浮かべて。
遠く離れた君に負けないぐらい、胸を張って、自信を持って描き出そう。
この、瞼の裏に焼きついた消えない残光を。
*
……それから僕は、絵を描き続けた。
秋は赤く染まる山々を描いた。冬は白く染まる町並みを。春は淡く染まる桜の花々を。
僕に出来る表現を、構図を、技術を用いて、僕らしく描き続けた。
彼女も同じだった。海外の絵画コンクールにて、突然現れた彗星のごとき彼女は見事銀賞を掴んだ。彼女らしい、華々しいデビューとなった。
その時彼女が描いた絵も、彼女らしい、暖かく、底抜けに明るい色合いで描かれた名作だった。
「やっぱり、覚悟が違うのかな……」
僕も僕で、日本国内で何度か受賞を果たしている。高校を卒業し、美大に入った。そこでも黙々と、淡々と絵を描き続けた。
それでもやっぱり、彼女の方が一歩先を進んでいる。僕から離れ、単身海外に留学した彼女とは、どうしても覚悟が足りない気がしてならない。
「……腐っててもしょうがないか」
僕は立ち上がり、沙恵のことを特集に組んでいた雑誌を机に置く。若い美人画家、海外でデビューとストレートに書かれた見出しが目に入り、知らずのうちにため息を吐く。
君は立ち止まらず、先を行っているというのに。僕はいったい何をしているんだろう。
遠く外国にいる君の目に触れられるぐらいの、僕らしい絵を、僕はまだ描けてないのに。
「あっ」
そんなことを考えてもいたからか、持ち上げたイーゼルの足が机にぶつかる。そのせいで、さっき机に置いた雑誌がバサリと音を立てて落ちた。
「……はぁ、ほんと、何やってんだろ」
気が滅入っている時は、やること成すこと全部に失敗が目立つようになってしまう。何度目かわからないため息を吐きながら、落ちた雑誌を拾おうとして。
「……これ」
涙が、零れそうになった。
開かれたページにはこれまでの、海外に渡ってからの彼女が描いた作品が細かく紹介されていた。僕の滲んだ瞳には、その中の一作が映される。
それは、確かに、あの日二人で見た花火。
そして、彼女らしくない、涼しげな色合いと、どこか寂しくも思える雰囲気を醸し出した。僕らしい、絵だった。
「なん、で……」
震える声のまま、雑誌を手に取る。
黒い夜空に咲く花。けれど、そこに華やかさはない。一瞬だけ輝き、すぐに散り逝く儚い光を、淡くて清廉さを感じる色合いで表現している。煌く光の、散り際を切り取ったような……。
そんな、僕らしい意図を汲み取ったような、僕らしい作品。
タイトルは、「あなたのように」。
「どうして……これを沙恵が」
彼女の作品の一覧に目を通す。ほとんどは、彼女らしい暖かさを持って描かれた作品だ。けれどその中に、いくつか彼女らしくない、静かで冷たい色合いで描かれた絵画がある。
そのどれも、評価はあまり良くない。彼女の持ち味を活かせてないからだ。彼女は明るく、鮮麗なまでの希望を描くことが出来る。だからこそ、僕のようなただ綺麗な絵では彼女の個性は活きない。
それでも、彼女は描き続けた。描きたかったから。自分の希望通りに、好きなように。好きな絵を描き続けた。
自分の希望を、自分なりの表現の仕方で、自分なりに描き続けた。
もう涙を堪えることは出来なかった。頬を伝った涙が雑誌にポタポタと落ちる。嗚咽を噛み締めるように抑えて、どこか呻きにも似た声が漏れる。
僕らしいって、いったいなんだ。彼女らしいってなんだ。
僕は、彼女の絵が好きだった。明るく鮮麗な色合いが好きだった。それを印象付ける計算された構図が好きだった。彼女の描く希望の形が美しくて大好きだった。
彼女が描く絵が、大好きだった。
けど、決して、彼女が僕を目指して描いた絵が、嫌いだったわけじゃない。
彼女が描いた絵に関して、僕は嘘をついたことなんて一度もない。
「何でも良かったんだ……君が描いた絵なら、何でも良かったんだよ……」
美しくなくても、綺麗でなくても。明るくなくても、鮮麗でなくても。
ただ、大好きな君が描いた絵なら、何でも構わなかったんだ。
芸術は、見る人の心に左右される。美しさも、鮮麗さも。全てが、見る人の心の裁量で如何様にも変わる。音楽は、ただの音の震えに過ぎないし。絵画も、色や形の明確化でしかない。
それなのに、どうして心を打つ、魂が揺さぶられるような衝撃を、芸術は生むのか。そんなの、見る人の心に答えを求めるしかない。その美しさを見た人が、決めていく。
なら、僕が今感じている、この胸の高鳴りはいったいなんだ。そんなもの、考えるまでもない。
僕は、僕の意志で、僕の感情で、僕の心で、彼女の絵を……。
涙を拭う。画材をカバンに詰める。イーゼルを解体し、持ち運びやすくする。
描きたい。そう思った。今日は何日だ。あれから何日経った。一年……そう、一年だ。
今日はまたあの花火が咲く。黒いキャンバスを鮮やかな光が清廉に、鮮麗に染め上げる。爆音を響かせ、目に焼きついて消えない残光を僕にくれるだろう。
それを描こう。精一杯描こう。君らしい絵を、僕らしく。君が僕らしい絵を、君らしく描いたように。
自分が好きだと思えた、綺麗だと思えた希望を、自らの手で描き出そう。
「沙恵は知らないだろうな。二部からの花火はもっとずっと派手なんだ。きっと、沙恵にぴったりなのに」
家を飛び出す。まだ日は暮れてない。なら時間はまだたっぷりある。けれど逸る気持ちは抑え切れない。描きたい気持ちはなくならない。
無理があるってわかっていても。夜空に咲き誇る花々を、一つ残らず描いてみせたくなる。
描き終わったら、君に会いに行こう。僕は君みたいに、雑誌に掲載してそれを僕が見てくれたら……なんて考えられる奥ゆかしさを持ってないんだよ。
大好きな君らしい絵を描く。それだって、十分僕らしい。
そんな僕らしい絵を、描きに行こう。そして、それを君に見せてやる。持って行って、目の前で。
これが僕が描きたい絵なんだって、胸を張って言おう。
荷物をガタガタと揺らしながら、肩に食い込むカバンの紐の痛みなど気にならずに。僕は息を切らせて走り続ける。
立ち止まるのは、あの丘に着いてからで構わない。それからゆっくりと、準備をしよう。そうして、描き始めようか。
君が知らない、君と見た花火よりもずっと派手で、豪快な花火を。
君らしく、僕らしく描き上げよう。
タイトルはもう、決まっている。
そうして、僕は一人、もう誰も来ることのない丘のベンチに座っている。
彼女が去ってから、そう時間は経ってない。いや、正直なところ、自分でも時間の経過なんてわからない。あれからもう一時間は経ったのかもしれない。一分かもしれない。もしかしたら、一秒すら経ってないのかもしれない。
その証拠に、彼女の涙が染みた服の胸元は、まだ乾いてはいない。服の皺もそのままで。
どれだけ懸命に、彼女が僕にしがみついていたのか。その証明になるものが、目に見える形でまだ存在していた。
花火が上がらなくなった世界は、ただ静かだった。風が凪ぐ音さえしない。そして当然、木の葉が風に揺られる音すらしない。町の生活音も、虫の鳴き声も。何も聞こえない空間の中、僕はただベンチに座り続ける。
これでよかったのだろうか。そう、何度も自問し続けた。これが正解だったのか。これで正しかったのか。間違いはなかったのか。そんな、答えが出ようもないことを永遠と。
気が狂いそうだった。これから彼女と離れて生きていくことが、彼女に触れられないことが。これからの未来にありえないことなんだと思うと。今すぐにでも走り出し、まだどこかにいるかもしれない彼女の背中を追いたくてしょうがなかった。
……さっさと立ち上がればいいんだ。彼女を追うためではなく、家に帰り、部屋に篭り、それこそ狂ったように絵を描きばいい。
手放した彼女への想いを、その渇望を描き出せばいい。きっと素晴らしいものが出来る。僕らしい色合いで、僕らしい構図で、僕らしい作品が生まれるだろう。
きっと、彼女もそれを望んでいる。
「……帰ろう」
口にすることで、決意を促しているみたいだった。それでも僕の足は、僕自身の宣言なんて無視して、立ち上がることを拒否する。この場から離れたくないと、彼女との思い出の場所から帰りたくないと駄々をこねる。
どうして、絵を描いてきたんだろう。絵を描いていなければ、こんな気持ちになることはなかった。ただ普通に彼女と出会い、彼女の描く絵に見入られるだけの一般人でいられた。そうすれば、今の悲しみなんてなかったのに。
どうして僕は、絵など描いてきたのだろうか。
その時。
光が、上がった。
甲高い、笛のような音を立てて。
夜空に、一筋の光を走らせ。
暗く沈んだ、黒いキャンバスを、光で染め上げた。
「……そっか。今年から、二部制なんだっけ」
人口増加と人気急増による範囲拡大。さっきまでの花火よりもずっと、華やかで煌びやかな光が夜空を舞う。
次々と打ち上げられる火薬。幾筋もの軌道を残し、夜空を彩る。爆音を響かせ、一瞬の閃光を走らせ続ける。目に焼きついてしまうほどの強い光。いくつも、いくつもいくつも。その一瞬は続いていく。
「……綺麗、だな」
この輝きを、煌きを。今どれだけの人が眺めているんだろう。何百、何千、何万という人間が、この夜空のキャンバスに描かれた一瞬の名画に心を奪われているんだろう。
ふと立ち止まり、空を見上げ、その美しい光景を瞳に映しているんだろう。
夜空に浮かぶ美しさの中の儚さを、どれだけの人が……。
「……綺麗だ」
気づけば僕は、また涙を流していた。もう枯れるほど泣いたと思ったのに。夜空に浮かぶ光の軌跡を眺めていると、自然に涙が零れて、止まらなくなる。
美しいと思った。綺麗だと思った。一瞬の光が、消えてなくなる輝きが、儚く散っていく煌きが美しく見えてしょうがなかった。涙で滲んだ視界でさえ、その光の軌跡は華やかに美しく映る。
「描きたいな……」
そう思えた。この一瞬の奇跡を。夜空のキャンバスじゃない、紙のキャンバスに描き上げ、一生残しておきたいと。
誰もが目を、心を奪われる。
手が疼く。筆を振るいたくなる。その光の芸術を、僕の手で、魅力を余すことなく、増量して、この世界に残したい。
もう届かない希望を。目にした美しいものを、もう二度と同じものはない輝きを、自らの技術を駆使して形に残せる。
……ああ、だから僕は、絵を描いていたんだよな。
だから僕は、絵が好きなんだよな。
光の芸術祭はフィナーレへと差し掛かる。次々と放たれる輝き。夜なのに、眩しいぐらいの光を放って。
君なら、この光景をどう描くだろう。華やかに、明るく、けれど底抜けに美しく描くのだろうか。
なら僕は、この美しくも儚い光景をどう描こうか。
最後に放たれた大輪を、僕は両の眼で捉える。忘れないように、消えないように。なくなさいように、失わないように。
君が好きだと言った、僕なりの描き方を持って。
この、儚く美しい光景を描こう。
そうして僕は立ち上がる。ズボンについた砂や埃を払って。もう何も描かれない夜空のキャンバスを見て。けれど、頭の中ではさっきまでの輝きを思い浮かべて。
遠く離れた君に負けないぐらい、胸を張って、自信を持って描き出そう。
この、瞼の裏に焼きついた消えない残光を。
*
……それから僕は、絵を描き続けた。
秋は赤く染まる山々を描いた。冬は白く染まる町並みを。春は淡く染まる桜の花々を。
僕に出来る表現を、構図を、技術を用いて、僕らしく描き続けた。
彼女も同じだった。海外の絵画コンクールにて、突然現れた彗星のごとき彼女は見事銀賞を掴んだ。彼女らしい、華々しいデビューとなった。
その時彼女が描いた絵も、彼女らしい、暖かく、底抜けに明るい色合いで描かれた名作だった。
「やっぱり、覚悟が違うのかな……」
僕も僕で、日本国内で何度か受賞を果たしている。高校を卒業し、美大に入った。そこでも黙々と、淡々と絵を描き続けた。
それでもやっぱり、彼女の方が一歩先を進んでいる。僕から離れ、単身海外に留学した彼女とは、どうしても覚悟が足りない気がしてならない。
「……腐っててもしょうがないか」
僕は立ち上がり、沙恵のことを特集に組んでいた雑誌を机に置く。若い美人画家、海外でデビューとストレートに書かれた見出しが目に入り、知らずのうちにため息を吐く。
君は立ち止まらず、先を行っているというのに。僕はいったい何をしているんだろう。
遠く外国にいる君の目に触れられるぐらいの、僕らしい絵を、僕はまだ描けてないのに。
「あっ」
そんなことを考えてもいたからか、持ち上げたイーゼルの足が机にぶつかる。そのせいで、さっき机に置いた雑誌がバサリと音を立てて落ちた。
「……はぁ、ほんと、何やってんだろ」
気が滅入っている時は、やること成すこと全部に失敗が目立つようになってしまう。何度目かわからないため息を吐きながら、落ちた雑誌を拾おうとして。
「……これ」
涙が、零れそうになった。
開かれたページにはこれまでの、海外に渡ってからの彼女が描いた作品が細かく紹介されていた。僕の滲んだ瞳には、その中の一作が映される。
それは、確かに、あの日二人で見た花火。
そして、彼女らしくない、涼しげな色合いと、どこか寂しくも思える雰囲気を醸し出した。僕らしい、絵だった。
「なん、で……」
震える声のまま、雑誌を手に取る。
黒い夜空に咲く花。けれど、そこに華やかさはない。一瞬だけ輝き、すぐに散り逝く儚い光を、淡くて清廉さを感じる色合いで表現している。煌く光の、散り際を切り取ったような……。
そんな、僕らしい意図を汲み取ったような、僕らしい作品。
タイトルは、「あなたのように」。
「どうして……これを沙恵が」
彼女の作品の一覧に目を通す。ほとんどは、彼女らしい暖かさを持って描かれた作品だ。けれどその中に、いくつか彼女らしくない、静かで冷たい色合いで描かれた絵画がある。
そのどれも、評価はあまり良くない。彼女の持ち味を活かせてないからだ。彼女は明るく、鮮麗なまでの希望を描くことが出来る。だからこそ、僕のようなただ綺麗な絵では彼女の個性は活きない。
それでも、彼女は描き続けた。描きたかったから。自分の希望通りに、好きなように。好きな絵を描き続けた。
自分の希望を、自分なりの表現の仕方で、自分なりに描き続けた。
もう涙を堪えることは出来なかった。頬を伝った涙が雑誌にポタポタと落ちる。嗚咽を噛み締めるように抑えて、どこか呻きにも似た声が漏れる。
僕らしいって、いったいなんだ。彼女らしいってなんだ。
僕は、彼女の絵が好きだった。明るく鮮麗な色合いが好きだった。それを印象付ける計算された構図が好きだった。彼女の描く希望の形が美しくて大好きだった。
彼女が描く絵が、大好きだった。
けど、決して、彼女が僕を目指して描いた絵が、嫌いだったわけじゃない。
彼女が描いた絵に関して、僕は嘘をついたことなんて一度もない。
「何でも良かったんだ……君が描いた絵なら、何でも良かったんだよ……」
美しくなくても、綺麗でなくても。明るくなくても、鮮麗でなくても。
ただ、大好きな君が描いた絵なら、何でも構わなかったんだ。
芸術は、見る人の心に左右される。美しさも、鮮麗さも。全てが、見る人の心の裁量で如何様にも変わる。音楽は、ただの音の震えに過ぎないし。絵画も、色や形の明確化でしかない。
それなのに、どうして心を打つ、魂が揺さぶられるような衝撃を、芸術は生むのか。そんなの、見る人の心に答えを求めるしかない。その美しさを見た人が、決めていく。
なら、僕が今感じている、この胸の高鳴りはいったいなんだ。そんなもの、考えるまでもない。
僕は、僕の意志で、僕の感情で、僕の心で、彼女の絵を……。
涙を拭う。画材をカバンに詰める。イーゼルを解体し、持ち運びやすくする。
描きたい。そう思った。今日は何日だ。あれから何日経った。一年……そう、一年だ。
今日はまたあの花火が咲く。黒いキャンバスを鮮やかな光が清廉に、鮮麗に染め上げる。爆音を響かせ、目に焼きついて消えない残光を僕にくれるだろう。
それを描こう。精一杯描こう。君らしい絵を、僕らしく。君が僕らしい絵を、君らしく描いたように。
自分が好きだと思えた、綺麗だと思えた希望を、自らの手で描き出そう。
「沙恵は知らないだろうな。二部からの花火はもっとずっと派手なんだ。きっと、沙恵にぴったりなのに」
家を飛び出す。まだ日は暮れてない。なら時間はまだたっぷりある。けれど逸る気持ちは抑え切れない。描きたい気持ちはなくならない。
無理があるってわかっていても。夜空に咲き誇る花々を、一つ残らず描いてみせたくなる。
描き終わったら、君に会いに行こう。僕は君みたいに、雑誌に掲載してそれを僕が見てくれたら……なんて考えられる奥ゆかしさを持ってないんだよ。
大好きな君らしい絵を描く。それだって、十分僕らしい。
そんな僕らしい絵を、描きに行こう。そして、それを君に見せてやる。持って行って、目の前で。
これが僕が描きたい絵なんだって、胸を張って言おう。
荷物をガタガタと揺らしながら、肩に食い込むカバンの紐の痛みなど気にならずに。僕は息を切らせて走り続ける。
立ち止まるのは、あの丘に着いてからで構わない。それからゆっくりと、準備をしよう。そうして、描き始めようか。
君が知らない、君と見た花火よりもずっと派手で、豪快な花火を。
君らしく、僕らしく描き上げよう。
タイトルはもう、決まっている。